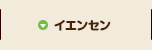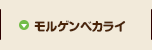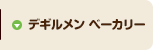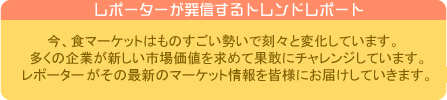

今回はそんな中から、イタリア、デンマーク、スイス、トルコのパン専門店を取材しました。
オリンピックやサッカーW杯など、「世界」を意識することが多い2014年。世界にはどんな種類のパンがあり、製法や味わいはどう違うのか。なぜその国のパンに魅かれ、出店するに至ったのか。そして、それらのパンを通してお客様にシェフは何を伝えたいかを取材してきました。
東京都文京区音羽にある「Pane & Olio(パーネ エ オリオ)」は2013年10月にオープンしたばかりのイタリアパン専門店。
イタリアパンのこだわりを大切にしながらも、日々、お客様の声を商品作りに生かすという、地域に密着したベーカリーです。
- Pane & Olio(パーネ エ オリオ)
- 住所:東京都文京区音羽1-20-13
- 電話:03-6902-0190
- 営業時間:10:00~18:00
- 定休日:日曜・祝日


「“イタリアのパン”ってあまりイメージがないですよね。 でも、食べてみると、とても日本人に合う食感なんです。硬いイメージのフランスパンに対して、イタリアパンの魅力は口溶け。外はサクッとしていて、でも中はモチモチした食感。イタリアパン、面白いな! と思ってお店を始めてみようと思いました」
イタリアパンの魅力に出会った店主の小林さん夫妻が、文京区音羽に店を構えたのが昨年10月。イタリアのパン技師ジャンカルロ氏に師事し、さらに都内の有名ホテルにイタリアパンを卸していたパン職人と一緒に研究を重ねた味は、開店からまだ半年も経たないうちに、地域住民から支持を集めました。
「このあたりは、食に対する意識が高い人達が多いですね。それだけにやりがいがあります。それと、イタリアパンが珍しいからか、『どうやって食べるの?』という声をいただくことも。『オリーブオイルをつけて食べると美味しいんですよ』『フォカッチャでサンドウィッチを作っても合うんですよ』といった食べ方も一緒にご案内しています」(小林さん夫妻)。

そうしたコミュニケーションが、新商品のアイデアや日々のパン作りにも役立つと言います。
「小さいお店なので、売り場と工房が直結しているんです。職人も『お客様はなんて言っていたの?』と気になるようで、お客様の声を聞きながら日々研究を重ねています。その結果、毎日のように新商品が生まれています(笑)」(小林さん夫妻)。
お客様の声を柔軟に取り入れながらも、こだわっているのは、原材料とイタリアの昔ながらの製法。たとえば、「イタリア食パン」(1斤450円)を作る際には、通常はショートニングやマーガリンを使用する油脂もオリーブオイルにすることで、独特の食感と風味を生み出しています。

小麦粉もイタリアから取り寄せた粉に、日本産の小麦粉を独自にブレンド。そして、丸1日かけて発酵させる“ビガ製法”を採用しています。
「北米の粉に比べ、ヨーロッパの粉は香りが豊かです。その粉を使い、“ビガ製法”というイタリアの伝統的な製法でパンを作っています。時間をかけて中種を発酵させると、香りと食感がさらによくなるんです。だからこそ、当店のパンは、まずは小麦の香りを楽しんでいただきたいですね」(小林さん夫妻)。
食感や風味はもちろん、亀の甲羅をモチーフにした「タルタルーガ」(170円)、バラの花びらを模した「ロゼッタ」(170円)、王冠の形の「インペラトーレ」(420円)など、見た目も楽しめるパンが満載。でも、まだまだ紹介したいパンはたくさんある、と小林さん夫妻は語ります。
「イタリアは共和国なので、地域ごとにたくさんの種類のパンがあります。その中から、まずは日本人に合ったパンを作っていますが、ゆくゆくはトスカーナ地方の無塩パンなど、イタリアならではのパンも紹介していきたいと思っています」
日本人で唯一の「コペンハーゲン製バン・製菓オーナーズ協会会員」である和田哲也さんが営むデンマークパンの店「イエンセン」(代々木八幡)。
デンマーク大使館を始め、デンマーク人が絶賛する本場の味を提供し続けています。
- イエンセン
- 住所:東京都渋谷区元代々木町4-3
- 電話:03-3465-7843
- 営業時間:[平日]6:50~19:00/[土曜]6:50~16:00
- 定休日:日曜・祝日


デンマーク人にとって、会議になくてはならないのがコーヒーとデニッシュ・ペストリー。代々木八幡にある「イエンセン」は月に2度ほどデンマーク大使館から注文を受け、夜中の12時から朝の7時まで、多い時で600個ものペストリーを焼き上げる“大使館御用達”のお店です。
「デンマーク人は“食べるために生きる”という国民性。それだけに、大使館やデンマーク企業からの注文がなくなったら僕の腕が落ちたということ。その時は引退します」

34年目を迎えた「イエンセン」、そして店主である和田さんの揺るぎない自信と誇りを感じる言葉です。和田さんがデンマークのパン学校に入学したいと考えたのは大学生の時。ただ、日本人の受け入れは前例がなく、当初は入学が認められませんでした。しかし、知人に紹介してもらったデンマーク人教師のツテを頼りに、様々な縁を介して遂には入学が認められ、本場の味と技術を学ぶ機会を得たのです。
また、日本に帰国してからは、「アンデルセン」でも指導したことのあるデンマーク人、ピーターセン氏と運命的な出会いを果たします。ピーターセン氏から直接指導を受けたことも、今の味を作り上げる上で欠かせなかったと言います。
「本当に、たくさんの人の縁で今の私も、この店もあります。それだけに、責任は重たいですね」(和田さん)。

フランスやドイツのパンに比べ、生地に含まれる卵の量が多いのがデンマークのパン(デニッシュ)の特徴です。また、生地全体に対して60~70%以上バターが入っていなければ、デニッシュと呼んではいけない決まりもあります。バターが多いためカロリーは高めですが、作り方次第で“重さ”は解消される、と和田さんは言います。
「日本で見かけるデニッシュ・ペストリーの多くは、口の中が油分でいっぱいになってすぐに飽きてしまいますよね。でも、本場で食べるペストリーは軽いんです。食べると層がボロボロと落ちて、口の中に油が残らない。そして、あっという間に食べてしまって、もうひとつ手を伸ばしてしまう。それが、本当の“デニッシュ・ペストリー”です」(和田さん)。
そんな和田さんが作るデニッシュの味は、本場デンマークからも認められています。「イエンセン」のマークに付けられた王冠は「女王が認めたパン」の証。デンマーク大使館からの推薦で審査員が来日し、1年以上の審査を経て「コペンハーゲン製バン・製菓オーナーズ協会会員」に認定されたのです。以降、「世界でデンマークの味を伝える人物」として、日本だけでなく、デンマークのテレビ、ラジオ、雑誌からも頻繁に取材の申し込みがあるそうです。
東京都府中市にあるスイス風パンの店「モルゲンベカライ」。
スイスには、地域や州ごとに特産のパンがあり、その数は数百種類にも及ぶと言われるパン文化の国です。その国で修行をした経験が生み出す味は、地域に親しまれています。
- モルゲンベカライ
- 住所:東京都府中市白糸台2-66-1
- 電話:042-351-0511
- 営業時間:9:30~18:30
- 定休日:日曜・隔週木曜


スイスの公用語のひとつであるドイツ語で、モルゲンは「おはよう、明日」、ベカライは「パン屋」という意味。毎朝の食卓に、そして明日も食べたくなるパンが並ぶお店として地域住民に愛されているのが、スイス風パンの店「モルゲンベカライ」です。パンの焼き上がった香りが心地よい店頭にはそれぞれのパンの焼き上がり時間が表示され、お目当てのパンを求めるお客様が途絶えません。
「スイスのパンと言っても、当初はあまり見向きもされませんでした。でも、宣伝も何もしなくとも、長く置いているとお客様も味の違いがわかるんでしょうね。少しずつ認知されるようになって、今ではスイスパンから順番に売れていきます」
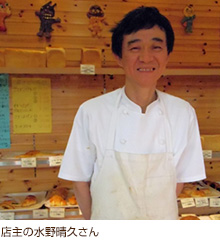
こう語るのは、店主の水野晴久さん。パン職人として働き始めてから7年後、一念発起してスイスに修行に行き、帰国後さらに7年間の経験を積んだ後、18年前にこの地で「モルゲンベカライ」を開業しました。
「パンの味を作るのは“発酵”です。とにかく、そこにはこだわっています。日本人独特の“旨味”は材料の味だけでは出せません。発酵させることで旨味が生まれるんです。パンの発酵時間は通常短めですが、少しでも長く発酵させてあげた方が美味しくなります」(水野さん)
ビガ発酵というこだわりの低温長時間発酵とスイスの伝統的製法によって、日持ちの良い、風味豊かなパンが生まれます。

店頭にはスイスの代表的なソフトパンで、牛乳と卵、バターをたっぷり使った「ツォップ」(小84円、大252円)、スイス各地で作られる伝統的なパン「ランドブロード」(315円)といった手作りのスイスパンが並びます。「ランドブロード」は、もっちりとした食感が特徴。噛むほどに深い味わいが楽しめます。
たくさんのパンが並ぶ中、予約が絶えず、売り切れることも多い人気商品が「食パン」です。発酵熟成の味を生かした、砂糖を使わない塩味タイプの「プルマンハード」(1斤252円、1本756円)、やわらかできめ細やかな生クリーム入り食パン「プルマンソフト」(1斤284円、1本850円)は、1本単位で購入するリピーターも。特に「ブルマンソフト」は、11時台、13時台、15時台、16時台と1日に4回も焼き上げ、その都度、売り切れてしまうほど愛されています。
また、毎日店頭に並ぶパン以外にも、日替わりの週間メニューを数種類ずつ用意。スイスパン独特の「ライ麦入りパン」を中心に、様々な味に出会うことができます。
「私ひとりで作っていますので、新メニューは出せても年に2、3種類。大事なことは、味にこだわった定番商品を毎日しっかり作ることだと思っています。お客様も、ここに来ればこれがある、と思ってきてくださっているわけですから」(水野さん)。
東京都豊島区に昨年5月にオープンしたトルコパン専門店「デギルメン ベーカリー」。
トルコ人のパン職人オメルさんが作る「本場の味」は、日本在住のトルコ人はもちろん、多くの日本人の舌も魅了しています。
- デギルメン ベーカリー
- 住所:東京都豊島区池袋2-22-3 池袋サンハイツ 1F
- 電話:03-5944-9119
- 営業時間:10:00~20:00
- 定休日:木曜


店名の「デギルメン」とはトルコ語で「製粉所」という意味。小さい頃から製粉所が身近な存在だったというオメルさんにとって、原点とも言える名前です。トルコでパンの修行を積んだオメルさんが来日したのが2010年。以降、レストランなどで働きながら最適な物件を探し、ようやく昨年、池袋に店を構えました。
お店に並ぶトルコパンは、トルコでは一般的な惣菜パンである「ポアチャ」(180円)、モチモチした食感が美味しい「ピデ」(200円)、ゴマがかかった「シミット」(150~180円)、トルコ風ソフトベーグル「アチュマ」(150~180円)、トルコの一般的なパイ料理「ボレッキ」(300円)など。それぞれ、味違いで毎日4~5種類を用意。また、パン以外でも、くるみとピスタチオをふんだんに使った「バクラヴァ」(300円)などの焼き菓子も充実しています。

「トルコにはたくさんの種類のパンがあります。原材料や厨房との兼ね合いからなかなか数が増やせないのがもどかしいですが、少しずつ種類を増やして、もっとたくさんの人にトルコパンを味わって欲しいと思います。トルコは朝・昼・晩と毎食パンを食べます。トルコのパンはまさに日本の米と同じ国民食なんです」(オメルさん)
小麦粉の起源が、トルコを源流とするチグリス川の畔、メソポタミア文明であると言われていることも、トルコにおけるパンの重要性を物語っています。
日々トルコパンを作る上で何より難しいのが、本場の味を再現するための材料調達です。
「砂糖や塩、基本的な調味料ひとつとっても、トルコと日本では味が全く異なります。その中で、日本で手に入る材料をどんな分量にすれば本場の味になるか、何度も試作を繰り返して、研究を重ねました」(オメルさん)。

たとえば、トルコパンの代表格とも言えるゴマをたっぷりとまぶした「シミット」。このゴマも、日本産とトルコ産では食感も味も全く異なるため、トルコ産のゴマが手に入らないか、日本のゴマでも同じ味にならないかを試行錯誤。現在は、トルコのゴマと日本のゴマをブレンドして使用しているといいます。また、日本で売っているピスタチオはアメリカ産がほとんどで、知人を通じてトルコ産ピスタチオを取り寄せることもあるそうです。
同様にパンの原料である小麦粉もトルコ産は入手が難しいため、日本で売っている小麦粉を何種類も試し、ようやく納得のいく配分を見つけることができたと言います。その粉を、トルコの都市コンヤという場所で採れた石を使ったこだわりの窯で毎日焼き上げています。
「将来的にはイートインスペースを設けて、トルコ名物のチャイとともにパンを楽しんでもらえるようにするのが夢ですね」(オメルさん)。
気候、そろえられる原材料、そして味覚も異なる日本において、何を変え、何を守るべきなのか。
どうすれば日本人にあったパンが生み出せるのか。
「世界のパン」を味わえる場所には、伝統と革新の精神が息づいています。
※店舗情報及び商品価格は2014年12月現在のものです