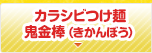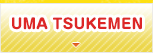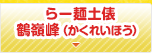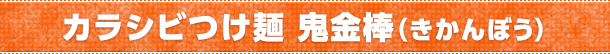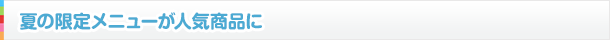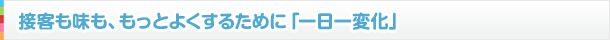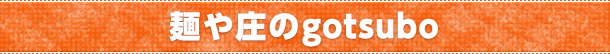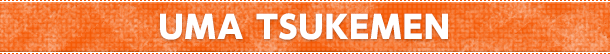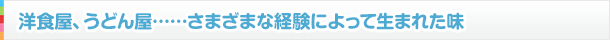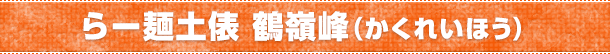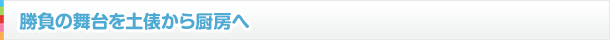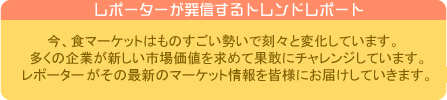

「激辛」「こだわり野菜中心」「パイ包み」「ちゃんこ」と拡がりを見せるつけ麺の“今”をご覧ください。
一度食べたら忘れられない、そして誰かに言いたくなるほどの「カラさ」と「シビレ感」で人気を集める「カラシビ味噌らー麺 鬼金棒(きかんぼう)」。その刺激を今度はつけ麺で味わってもらおうと生まれたのが「カラシビつけ麺 鬼金棒(きかんぼう)」です。
- カラシビつけ麺 鬼金棒(きかんぼう)
- 住所:東京都千代田区鍛冶町2-10-9
- 電話:03-6206-0239
- 営業時間:[月〜土(祝日含む)]11:00~21:30
[日曜]11:00~16:00 - 定休日:無休


「人に伝えたくなるラーメンが作りたかったんです」。
東京・神田に店を構える「カラシビつけ麺 鬼金棒」の代表、三浦正和さんが語る通り、唐辛子の「カラさ」と山椒独特の「シビレ感」というふたつの刺激が味わえるつけ麺は、他にはないまさにオンリーワン。三浦さんの狙い通り、口コミで広がった人気はメディアでも話題になり、さらなる反響を生み出しています。
元々は、刺激的な味噌味のラーメン店「カラシビ味噌らー麺 鬼金棒」として5年前に開業。その約1年後に、本店のすぐ近くにつけ麺に特化した「カラシビつけ麺 鬼金棒」をオープンしました。

「うちのような辛い味付けは、どうしても冬に比べて夏のほうが客足は鈍くなります。そこで、夏の限定メニューとして提供したのがつけ麺。おかげさまでそのつけ麺が好評をいただいたのですが、レギュラーメニュー化するにはオペレーションの都合などもあって無理がある。そんな時、お店のすぐそばに空きが出たこともあって、つけ麺専門店を出すことになったんです」。
本店もつけ麺専門店も、ベースの味は味噌。全国の味噌を50種類以上試して選び抜いた信州味噌が味の決め手です。ただ、つけ麺用の味噌にはさらにこだわりがあると言います。
「つけ麺用の味噌は、味噌ラーメン用の味噌からとれた味噌だまりを使っています。これはどこにも販売されてなくて、味噌屋さんがウチだけに特別に卸してくださったもの。元々の味噌も樽の中で約1年寝かせているのでコクがあるんですが、味噌だまりはさらに熟成されて濃厚な旨味があります」。

味の決め手である味噌へのこだわりはもちろんのこと、店のアイデンティティである唐辛子・山椒も世界中から選び抜いたものばかり。辛さとシビレはそれぞれ、「カラ抜き・カラ少なめ・カラ普通・カラ増し・カラ鬼増し」、「シビ抜き・シビ少なめ・シビ普通・シビ増し・シビ鬼増し」の5段階から組み合わせられるのも人気の理由のひとつ。辛さの違いは唐辛子の量かと思いきや、ブレンドから変えるというこだわりようです。
「唐辛子に関しては、日本、インド、韓国、中国の唐辛子をブレンドして使っています。あともうひとつ、『カラ鬼増し』で使っているのがオーストラリア産のトリニダード・スコーピオン・リッチテーラーという2011年にギネス認定された世界一辛い唐辛子です。山椒も、本場・四川のものを使っています。やっぱり香りから違いますから」。

辛さ・シビレを受け止め、濃厚な味噌スープに合うよう、麺にもこだわりが込められています。通常の味噌ラーメンでは、食感の違いが楽しめ、スープがよく絡まるように「三種混合麺」を使用。一方、つけ麺の場合はさらに濃厚なスープのため、シンプルな極太麺にして食感とスパイス感を楽しんでもらう工夫を施すなど、常に研究を重ねながらよりよいバランスを探っています。
「お店のスローガンが『一日一変化』。接客も味も、もっとよくするためにはどうすればいいかと常に考えています。実は山椒の量はオープン当初は今の倍の量を使っていたんです。でも、お客様の反応を見るとどうも入れ過ぎだったようで(笑)。そこから少しずつ調整して、一番香りもよくて刺激があり、美味しく食べられる量を見つけていきました」。
2月中には台湾でも新規店舗をオープンする予定。革新的な味はさらに世界観を広げていきそうです。
東京・新宿御苑の近くに店を構える「麺や庄のgotsubo」。この店で、新宿のオフィス街で働く女性客を中心に支持を集めるメニューこそ、野菜がふんだんに盛られた「ベジつけ麺」です。店名の通り5坪(6席)の店内には常にお客様の活気があふれています。
- 麺や庄のgotsubo
- 住所:東京都新宿区新宿1-32-15
- 電話:03-6388-9227
- 営業時間:11:00~15:00/17:00~22:00
- 定休日:日曜


新宿区を中心に、つけ麺専門店、油そば専門店など5店のラーメン店を手がける麺庄グループ。その代表を務めるのがラーメンクリエイターの庄野智治さんです。
「日頃から食べ歩きをして研究を重ねているんですが、ラーメン・つけ麺という料理の特性上、どうしても野菜の摂取量が少なくなってしまいます。キャベツなどの野菜トッピングがあればいつも注文するようにしていたのですが、それがヒントになって『だったら、濃厚なのに体に優しい健康的なつけ麺があれば喜ばれるんじゃないか』と考えてオープンしたのが、この『麺や庄のgotsubo』になります」。
そんな「体に優しい健康的なつけ麺」というコンセプトが凝縮されたメニューこそ、20種類以上の国産野菜がふんだんに盛られた「ベジつけ麺」です。

「ベジつけ麺のアイデアの元はイタリアの野菜料理、バーニャカウダ。あの料理を食べると必ず何か一個ぐらい知らない野菜が入っているんですよね。見たことがない野菜があるとなんだか楽しいじゃないですか。あの驚きみたいなことも取り入れたいと思い、バーニャカウダのようなつけ麺を作ろうとしてできたのがベジつけ麺です」。
選べる2種類のスープ(海老とトマトの鶏白湯スープ、生姜スープ)はどちらも濃厚で、スープであると同時にまさに野菜をディップするためのソース。それでいて、野菜のでんぷん質も多く含まれているため、余分な油の摂取を抑えながら食べ進めることができます。

ベジつけ麺で取り扱う野菜は契約農家から直接仕入れることもあれば、信頼を置く青果店から仕入れるなどして、季節に応じた新鮮野菜が盛られます。
「自然が相手なので野菜の仕入れは一番大変な部分であり、楽しさでもあります」と語る庄野さん。たとえば取材時には、通常の青果店ではまず並ぶことのない、京都産の「黒大根」のスライスが皿に盛られ、彩りにアクセントを与えます。
このベジつけ麺、季節の野菜をたくさん食べることができるのが魅力ではありますが、一方で、野菜にこだわるあまり料理としてのバランスを欠いてしまっては意味がない、と庄野さんは語ります。
「単なるサラダと思われてしまっては意味がありません。着地点はやっぱりつけ麺でありたい。野菜を抜いたとしても満足のいくつけ麺になるように濃厚なスープにしていますし、麺に関しても野菜のみずみずしさが引き立つよう、タピオカの粉を練り込んで打ち立てにこだわることで、モチッとした食感になるよう工夫を重ねています」。
そんな庄野さんのこだわり、そして研究心はとどまるところを知りません。
「今取り組んでいるのが、高タンパクで低脂肪なプレミアム豆乳のクリームを使ってスープを作ること。もっともっと健康的な素材を使って、新たなコクや旨味を引き出す研究をしていきたいと思っています。ラーメンは美味しくても体に悪い、と思われがちな食べ物です。そんな固定観念を払拭し、業界を活性化させるためにも、『野菜を食べるつけ麺』『健康で美味しいつけ麺』というコンセプトをますます進化させていきたいですね」。
お店はトレーラーハウス、店頭を飾る自由の女神イラスト。そしてつけ汁にはぷっくりふくらんだパイ生地……自由な発想で開発されたメニューが自慢の「UMA TSUKEMEN」は、テレビを中心にさまざまなメディアでも取り上げられることが多い人気店です。
- UMA TSUKEMEN
- 住所:東京都立川市西砂町1-3-15
- 電話:080-3427-4933
- 営業時間:[平日]11:30~15:00/18:00~23:00
[土曜・日曜]11:30~16:00/18:00~23:00 - 定休日:不定休


「店名の由来ですか? いろいろかけてるんですよ。『美味(UMA)い』とか。あとは『未確認生物』という意味のUMA。こんなつけ麺、他では見つけられないはずですから(笑)」。
東京都立川市に店を構えるつけ麺とラーメンの店「UMA TSUKEMEN」。店主の皆川富士雄さんが「他にはない」と自認するのが、この店の代名詞でもあるパイ包みつけ麺「極UMA つけめん」です。
「つけ麺はどうしてもスープが冷めやすいのが難点です。そこで、スープを冷めないようにするにはどうすればいいかを試行錯誤した結果、行き着いたのがこのパイ包みのアイデアでした」。

器から帽子のように膨らんだパイ生地の一部に穴をあけ、そのスペースで麺をつけ汁につけて食すのがこの店のスタイル。器にしても、熱が冷めにくく、熱々のスープでも手がやけどしないように、厚手の益子焼を使うこだわりようです。「極UMAつけ麺」と「極UMA味噌つけ麺」は通常のパイ生地を使用。「極UMAカレーつけ麺」はカレー味のスープに合うようにパイ生地にチーズがトッピングされています。そして一番人気だという「極UMA海老つけ麺」のパイ生地にはチーズに加えて小エビが練り込まれています。このパイ生地そのものも香ばしく、旨味が凝縮されています。
ラーメン店を開業する以前に洋食店でも腕を振るった経験を活かしたパイ包みのつけ麺は熱を逃がさないという利点とともに見た目のインパクトを生み、たちまち人気商品に。メディアでも取り上げられることも多く、ピーク時には2時間待ちを越える行列が生まれたほど、話題と人気を集めています。

もちろん、このパイ生地つけ麺は見た目のインパクトにとどまらず、美味しく食べるためのアイデアが包み込まれています。スープの中には極厚のチャーシューが眠っていて、パイ生地の隙間からスープを吸い込んだチャーシューを見つけた瞬間、つい笑顔になってしまうはず。また、この店のつけ麺スープは熱が冷めにくいからこそ、濃厚な味付けにもかかわらずサラッとした口当たりが特徴です。通常の麺だとスープが絡みにくいため、全粒粉の麺を使用することでスープをしっかり持ち上げるように工夫が施されています。
「パイ生地が焼き上がるのに8分間必要です。ただでさえ時間がかかる料理ですので、その8分間を有効に使って麺を茹でるようにしています。麺の茹で方も、わざと対流を弱くして、8分かけてじっくり、うどんのように茹でています。うちのつけ麺は太くてしかも全粒粉だから、一気に熱を加えてしまうと角が丸くなってしまうんです。実は若い頃、洋食屋とは別にうどん屋でも働いたことがあって、その経験が活きていますね」。

この全粒粉の麺もパイ生地もすべて自家製。仕込みには当然時間がかかってしまいますが、その手間ひまを惜しまない姿勢こそが愛される理由でもあります。
「麺とパイ生地は毎朝仕込んでいます。パイ生地がある分、他のお店さんよりも仕込みが面倒かもしれませんね(笑)。小麦粉は温度、湿度で仕込み加減が変わってくるので毎日試行錯誤していますけれども、同時にそれがやりがいだとも思っています」。
料理人としてさまざまな経験を積んだからこそ導き出せたアイデアとこだわりが生み出す味を求め、今日も遠方からの客足が途絶えません。
元力士の店主が、人気店「麺屋こうじ」で修行を積んだ後に開業したのが、横浜市鶴見区にある「らー麺土俵 鶴嶺峰(かくれいほう)」です。本格派のラーメン、つけ麺にちゃんこ料理のエッセンスが加えられた味わいは、美味しさとともに優しさに満ちあふれています。
- らー麺土俵 鶴嶺峰(かくれいほう)
- 住所:神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-25-6
- 電話:045-504-2207
- 営業時間:
昼の部[平日]11:15~15:00[土曜・日曜・祝日]11:15~16:00
夜の部[月曜・火曜・水曜・日曜]18:00~22:30[金曜・土曜・祝日前]18:00~23:00 ※スープ切れ終了あり。 - 定休日:木曜


暖簾をくぐって店の中に入るとまず耳に飛び込んでくるのは「いらっしゃいませ」のかけ声、そして店内に流れる相撲太鼓や相撲甚句の音色です。神奈川県横浜市鶴見区にある「らー麺土俵 鶴嶺峰」は、店名にある「土俵」の文字が示す通り、相撲がコンセプトのお店。店主の森康人さんは、かつて角界に籍を置き、「鶴嶺峰(かくれいほう)」のしこ名で土俵を舞台に勝負に挑んできた元力士です。そして現役引退後、勝負の舞台は土俵から厨房へと変わりました。
「相撲界には15年間在籍し、その後、和食の店やソバ屋、居酒屋などさまざまな飲食店を経験してきました。そして、ラーメンが好きだったこと、いつかは自分の店が持ちたい、という理由から、味だけでなく接客にもこだわりのある『麺屋こうじ』で5年ほど経験を積み、2012年11月にこの店をオープンしました」。

営業中であれば「本場所中」、仕込み時には「稽古中」の札が店先に掲げられ、人気メニューである「鶴嶺峰つけ麺」では、並盛り(250g)を「幕内」、大盛り(350g)を「小結」、以降、量が増すたびに「関脇」「大関」「横綱」と呼び名が変わるなど、随所に相撲にまつわる遊び心でお店を演出しています。
また、動物系のダシと魚介系のダシを長時間煮込んだ味わい深いスープの中に入っているのはチャーシューではなく軟骨入りのつくね。そしてトッピングではもち巾着が選べ、サイドメニューにはチャンコ御飯があるなど、相撲部屋のちゃんこ料理を連想させる味を楽しむことができます。

お店を演出するのは「相撲」というコンセプトですが、それ以上にこだわるのが美味しい料理を提供することだと、店主の森さんは語ります。
「元力士だったわけですから、相撲というカラーはどうしても出てしまいます(笑)。だからこそ、お客様に喜んでいただくためには味にこだわらなければ、と常々考えています」。
たとえば、トッピングで人気の「眠りチャーシュー」は、肉の旨味を最大限に引き出すために約1週間も寝かせた熟成チャーシュー。麺も横浜市の名店「くり山」で使用している自家製麺を特別に提供してもらうなど、美味しさのための手間ひまは惜しみません。
「麺は跳ね返るような弾力感ともちもち感、そしてのどごしの良さが特徴です。香りもいいですし、何よりうちのスープによく合うんです。絡み具合もバランスもちょうどいい。これはもう、くり山さんの麺しかないなと思い、縁もあって提供していただけることになりました」。

そして、美味しさを追求する上で意識するのは、土俵の形にも通じる「丸さ」だと言います。
「美味しいものっていうのはつまり、人を優しい気持ちにさせるものだと思うんです。ですので、作るときはいつもお客様が食べる姿を想像しながら、『丸さ』を出せればいいなと思っています。たとえば優しさだったり、なんか落ち着くね、ほっこりするよね、と感じていただけるのが理想です。一人一人のお客様が、笑顔になって店を出ることができる……そういう空間を提供していければと思っています。喜んでもらえるのが一番! それしか考えていません」。
※店舗情報及び商品価格は取材時点(2015年1月)のものです