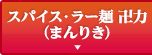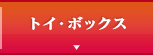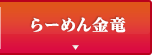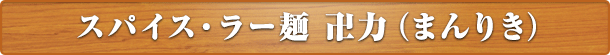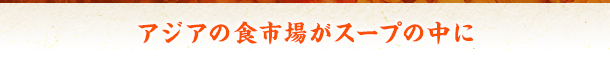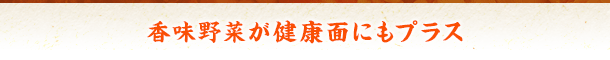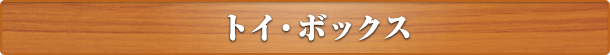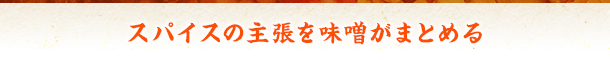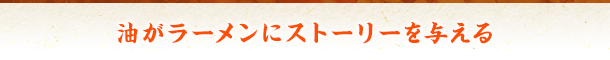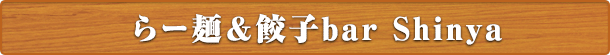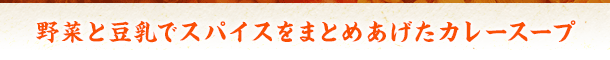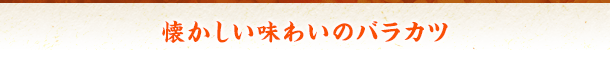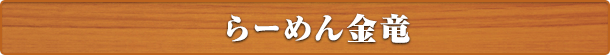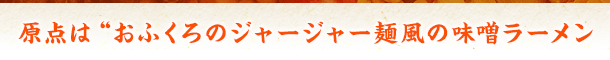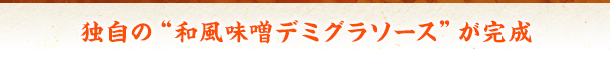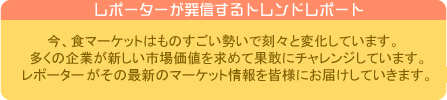

店長の大橋たかしさんは、神田にある「カラシビつけ麺 鬼金棒」にて修業中、スパイスの世界に魅了されます。2014年5月、西葛西駅前に幸せのシンボルとされる「卍」にあやかったラーメン店「卍力(まんりき)」をオープン。従来のラーメンとは一線を画す、大橋さんの編み出した「スパイス・ラーメン」は、食べるお客さまを幸せに、そして元気にします。
- スパイス・ラー麺 卍力(まんりき)
- 住所:東京都江戸川区西葛西3-16-5
- 電話番号:03-6848-1346
- 営業時間:[月曜~金曜]17:00~23:00/
[土曜・日曜・祝日]11:30~15:00、17:30~22:00 - 定休日:水曜(第1・3・5)


鬼金棒の「カラシビ味噌らー麺」は、味噌をベースに唐辛子と山椒がたっぷり効かせてあるのが特徴。大橋さんはさらに、スパイスに特化したラーメンの開発に取り組みます。豊富な食材で作り込まれたスープに、まず驚かされます。
「豚骨や鶏ガラの動物系に、煮干しやカツオ節、サバ節などの魚介系のだしをブレンド。基本は醤油ダレですが、トマトソースと酢が加わることで、酸味が生まれます。そこにカルダモン、コリアンダーなど14種のスパイスが絡むことで、独特のエスニックな風味を切り開くことができました」。
 「スパイス・パクチーラー麺」の、山盛りのパクチーをかき分け、思いのほかサラッとしたスープを一口含むと、塩味、甘味、辛味、酸味、そして苦味…複雑かつ刺激的なテイストがバランスよく口の中に広がり、アジア各国の魅力がぎゅっと詰まった味わいです。その独創的な一体感は、それぞれの味が中華鍋でしっかりとミックスされることで生み出されています。
「スパイス・パクチーラー麺」の、山盛りのパクチーをかき分け、思いのほかサラッとしたスープを一口含むと、塩味、甘味、辛味、酸味、そして苦味…複雑かつ刺激的なテイストがバランスよく口の中に広がり、アジア各国の魅力がぎゅっと詰まった味わいです。その独創的な一体感は、それぞれの味が中華鍋でしっかりとミックスされることで生み出されています。

そして、スパイシーなスープとともに魅力を醸し出しているのが「パクチー」。通常の「スパイス・ラー麺」にもパクチーは添えられていますが(ネギに変更可能)、パクチーラー麺は名前通り、丼いっぱいに緑の花が咲き、食べる前から南国の香りに包まれます。
こうして完成したスパイス・パクチーラー麺について、大橋さんはその効能を語ります。
「ひと言でどんなラーメンかと聞かれれば、『アジアン・ヌードル』というのがふさわしいでしょうね。たしかに辛いですし、香りも強く、クセのあるラーメンですが、スパイスには消化促進や食欲増進の効果があります。見た目ほど重くはなくて、のど越しがいいのが特徴ですね」。
低かんすいのストレート中太麺、さっぱりと柔らかいチャーシュー、色あざやかなブロッコリーなど、麺や具材もスパイスとの相性を考慮し、バランスよく配置されています。
大橋さんが切り開いた、スパイシー系ラーメンの新境地。西葛西に新たな「アジア食文化の拠点」が誕生しました。
昔ながらの商店街が息づく三ノ輪駅界隈にある「トイ・ボックス」は、店からあふれる行列が目印。もともと正統派の醤油ラーメンからスタートし、今でも醤油ラーメンが根強い人気のなか、店長の山上貴典さんは、スパイシー系の味噌ラーメンは「偶然の産物です」と話してくれました。いかなる偶然から、この芸術品のような味噌ラーメンが生まれたのでしょうか。
- トイ・ボックス
- 住所:東京都荒川区東日暮里1-1-3
- 電話番号:03-6458-3664
- 営業時間:[火曜~土曜]11:00~15:00、18:00~21:00/
[日曜・祝日]11:00~15:00 - 定休日:月曜


オープン以来、醤油、塩と提供してきた山上さんは、それまで研究を重ねてきた「味噌」の開発に取り掛かります。味噌ラーメン特有の「もったり感」を緩和するため、隠し味としてスパイスを投入することに。ところが、思わぬ誤算があったといいます。
「よくカレーの隠し味に味噌を入れるじゃないですか。あれとは逆に、味噌ラーメンの隠し味として、カレーなどのスパイスを入れてみたんです。すると、隠し味のつもりが、予想以上にスパイスが前面に出てしまって…でも、お客さまには思いのほか好評をいただくことになり、最終的にはスパイスの量を半分に調整し、独自のブレンドにこだわることで現在の味噌ラーメンに仕上がりました」。

山上さんが「スパイスラーメンではなく、あくまで味噌ラーメン」とこだわるスープ。丸鶏100%に昆布のだしに、「会津味噌(辛め)」「新潟天然麹味噌(甘め)」「麦味噌(香ばしい)」の3種をブレンド。そこに山椒、コリアンダー、ガラムマサラなどのスパイスを配合。一見、多様なスパイスで味が複雑化しそうですが、味噌がしっかりとすべての食材をまとめ上げ、見事に「スパイシーな味噌スープ」に仕上がっています。

スープを際立たせるもう一つの特徴が、「油」です。スープの表面をおおう透き通った油の一部は、「緑の油」。日本の味噌、東南アジアのスパイス、そこにイタリアンなテイストまで加味されているのです。
「味噌ラーメンは“重さ”がある分、後半、どうしても食べ飽きてくる傾向があるんですね。そこで全体にまろやかさを出すために、『チー油』と『緑オイル』(=パセリ入りのグレープシードオイル)を加えています。この二つを足すことにより重さを感じさせない、まろやかでキレの良いスープになります。しかも、油の膜の保温効果で、スープが冷めにくくなるんです」。
スープを飲むと、「味噌+スパイス」のコクとはまた違った、清涼な味わいが広がります。のど越しの良さでスープと相性抜群の中細ストレート麺、レアな仕上がりの鶏+豚モモ肉のふんわりチャーシューなど、スープ以外にも“匠の技”が光ります。
店名どおり“おもちゃ箱”のような楽しさを放ちながら、洗練された味わいをたたえた味噌ラーメンは、山下さんの言うとおり、一杯のラーメンの中で次々と異なる味に出会う“ストーリー性”を感じることができます。
都内屈指のラーメン激戦区である、高円寺南口。そこに新規参入するにあたり、「他店にはないことをしよう」と考えた店長の野尻真也さんは、カレー、スパイス好きなところから、「カレーラーメン」で勝負をかけています。そば店にあるカレーうどんの延長のようなものが多いなか、野尻さんのオリジナル・カレーラーメン作りが始まります。
- らー麺&餃子bar Shinya
- 住所:東京都杉並区高円寺南4-7-5
- 電話番号:03-5306-7405
- 営業時間:[月曜~金曜]11:30~14:00、19:00~23:00/
[土曜]16:00~23:00 - 定休日:日曜・祝日(不定休)


「カレーラーメン」というとどのような印象を持たれるでしょうか? 「カレーラーメン」といえば、カレーうどんのように醤油だしの上にカレールーを乗せたものか、あるいは、さらさらのカレースープに麺を投入したものをイメージする方も多いと思います。野尻さんは「しんや」のオープンにあたり、そのイメージを払拭する、革新的なカレーラーメン作りを試みます。
「もともとカレーやスパイスが好きだったのですが、エスニック風に行きすぎないよう和風を意識しつつ、単にカレー粉を溶いただけのカレーうどんのようにもならないよう、試行錯誤を繰り返しました」。

結果、オリジナルのスープの決め手となったのが、「野菜」と「豆乳」でした。鶏ガラと豚骨のだしに、玉ネギ、ニンジン、ニンニクなどの野菜を投入。そこに豆乳を合わせ、ガラムマサラなどのカレースパイスを調合することで、いわゆる“ベジポタ”風のトロトロスープが完成。見た目のこってり感に対し、野菜と豆乳ベースのため、ほどよくスパイスの角が取れ、まろみのあるヘルシースープに仕上がっています。

濃厚スープと中太ちぢれ麺の絡み具合は、パスタソースとパスタの関係にも似て、麺とスープがほどよく一体化。麺にスープをしっかりと絡めて食べるため、スープを残すお客さんはほとんどいないそうです。
さらに、「バラカツ伽辣麺」で存在感を放っているのが、丼の直径にも近い長さの“カツ”。
「カツカレーから思いついたのですが、カレーとカツって相性がいいですよね? しっかりしたカツだと重すぎるので、薄めの豚バラ肉を、細かい衣でカラッと揚げました。いろんなカツを試しましたが、これはスープと最高にマッチすると思います」
カリカリのバラカツは、スープに絡ませてもふやけず、香ばしいまま。大きさがあるので、麺を食べる合間に少しずつかじっていくのも楽しいものです。
ラーメン好き、カレー好きともに納得できるうえに、野菜と豆乳のヘルシーさ、バラカツのボリューム感まで加わった、欲ばりなバラカツ伽辣麺。スパイシーなだけではない、手の込んだ味わいの「カレーラーメン」です。
先代から40年以上続く老舗のラーメン店「金竜」。その原点は、店長・幸田洋介さんの“おふくろの味”にあったといいます。母親の家庭料理から始まった独特の味噌ラーメンが、やがて幸田さんの代になり、看板メニューとして一本立ちすることに。ここでしか味わえない、薬膳を思わせる「味噌×スパイス」のマリアージュの秘密に迫ります。
- らーめん金竜
- 住所:千葉県松戸市金ヶ作303-30
- 電話番号:047-387-3520
- 営業時間:11:30~14:45、18:00~20:45
- 定休日:水曜・木曜


店内のメニュー板には「味噌らーめん」の一品のみ。遠方から訪れるファンも多い独特の存在感を放つこの一杯のルーツは、幸田さんのご家庭にありました。
「味噌らーめんは開店当初からあるメニューですが、そもそも、私の母親が家庭料理として作っていた、ジャージャー麺風の味噌ラーメンが原点なんです。黒っぽくて甘みがあるため八丁味噌と間違われますが、メインで使っているのは仙台味噌。北海道とか、全国の味噌を試した結果、『仙台味噌+赤味噌』の組合せに落ち着きました」

ラーメン店としての発想ではない、「家庭の味」からのスタート。スパイシーでありながら飽きることのない一杯は、幸田家の温かな食卓から生まれ、アレンジされたものでした。

もちろん、単に素朴な家庭風味噌ラーメンではなく、その味わいは重層的です。ゴマや山椒、七味、コショウなどのスパイス類が盛られ、いかにもパンチのある外見ですが、スープを口にすると思いのほかすっきりとキレが良く、食後も胃にもたれません。
その秘密は、スパイスに絡む野菜にあります。青々とした三ツ葉とスパイスの層の下から、“野菜炒め麺”と呼んでもいいほどの野菜が姿を現します。
「長ネギ、玉ネギ、ショウガ、ニンニクなどの香味野菜をアメ色になるまで炒めて、そこに味噌や酒を合わせます。さらに、だしに使っている豚ひき肉が加わることで、“和風デミグラスソース”のようなコクのあるスープになります。うちはチャーシューは使っていませんが、肉好きの方でも満足いただけるのは、デミグラ風スープの深みのためではないでしょうか」。
地元の年配のお客様も多いのですが、スープまで飲み干される方も多いそうです。スパイス効果で、駅までの帰り道も体がポカポカと温かいままです。
「味噌ラーメン+野菜炒め+スパイス」のアンサンブルの妙で、家庭の味から“松戸の味”にまで広まった金竜の味噌らーめん。刺激的でありながら、ほっと心安らぐ一杯です。
※店舗情報及び商品価格は取材時点(2015年4月)のものです