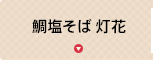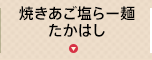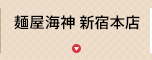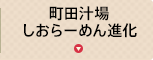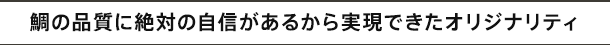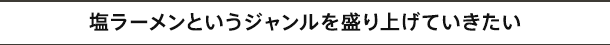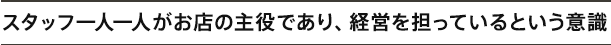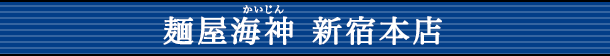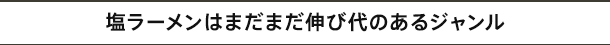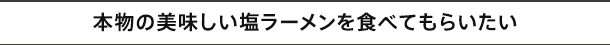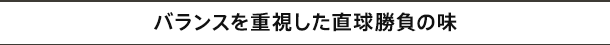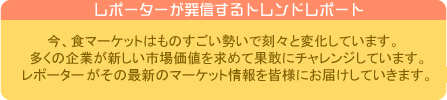

東京都新宿区曙橋で人気を誇る「塩つけ麺 灯花」。その店のすぐ近くに今年4月、2号店「鯛塩そば 灯花」がオープンし、早くも各メディアで注目を集めています。宇和島産真鯛を贅沢に使ったスープはここでしか味わえない逸品です。
- 鯛塩そば 灯花(とうか)
- 住所:東京都新宿区舟町12-13 石原ビル1F
- 電話番号:03-3354-3303
- 営業時間:[昼]11:00~15:00/[夜]17:00~24:00
- 定休日:日曜日


店頭を飾る提灯に大きく記された文字は「宇和島産真鯛」。この提灯と店名「鯛塩そば 灯花」が示す通り、この店の売りは「真鯛にこだわった塩ラーメン」です。
「2012年に開業した1号店では、塩に特化した店でもあまり見かけない『がっつり系の塩つけ麺』をコンセプトにしました。2号店を出すにあたり、つけ麺の次はやっぱりラーメンで塩に挑戦したいと、この店が生まれました」。
教えてくれたのは2号店店長の高橋登夢さん。代表の川瀬裕也さんとともに、二人三脚で店を切り盛りしています。スープを作る大きな寸胴に入っているのは真鯛と水の二つだけ。鯛の品質に絶対の自信があるから実現できたこの思い切りの良さが「灯花」の特徴であり、オリジナリティです。

「宇和島産真鯛との出会い。これが2号店オープンの根幹です。生産者の方と直接取引できていることもあり、品質には自信があります。この鯛を1日あたり約50kg、ラーメン一杯につき約1尾半ぐらいをふんだんに使ってご提供しています」。
鯛と水だけでは物足りなくならないのか? そんな疑問を払拭するのが、塩専門店として3年間培ってきたノウハウを活かしてつくる「塩ダレ」の存在です。
「1号店と2号店で塩は変えています。2号店では製造工程まで見学して納得した佐賀県玄界灘産の『一の塩』を使用。この塩に、鰹節、昆布、貝柱などの海産物の旨みを抽出してできた塩ダレが、鯛の風味を損なわずに、シンプルながらも力強い味を生み出します」。


こだわりのスープや塩ダレに負けないよう、麺は「しなやかさ」を追求しています。
「角張ったタイプや張りのある麺よりも、しなやかなタイプのほうが麺をすすったときにスープも一緒に口の中に入ってくるんです。他のラーメンと比べるとどうしても繊細なスープですから、麺とのコンビネーションで味わっていただくことを意識しています」。
さらに、麺を食べたあとに残ったスープをかけて味わう鯛茶漬け(昼・夜15食限定※単品注文不可)も、本来であればこれだけでもメインを張れる贅沢なひと品。高齢の方や女性客も多いという客層にあわせて、ご飯の量を選ぶことができる気配りも忘れません。素材と味の追求、そして細やかな気配りが功を奏してか、開店からわずか数ヶ月にもかかわらず、各種ラーメンランキングで軒並み1位の高評価を獲得しています。
「塩ラーメンのお店はどんどん増えていますが、まだまだラーメンの中のジャンルでいえば少数です。その中で認知され、反響をいただけるのはありがたいことだと思っています。これからも目の前の一杯一杯、お客様一人一人に集中して、身の丈にあった店舗経営をまずは心がけていく。その先に『あぁ、塩ラーメンってこんなに美味しいんだ!面白いんだ!!』ということをお客様に対してもそうですし、業界に対しても主張していくことで、塩ラーメンというジャンルを盛り上げていきたいですね」。
飲食店の競争が激しい新宿歌舞伎町において確かな存在感を放つ「焼きあご塩らー麺 たかはし」。他ではあまり見かけない「焼きあご」にこだわった塩ラーメンが好評を博し、今年2月の開店以来、右肩上がりの成長を遂げています。
- 焼きあご塩らー麺 たかはし
- 住所:東京都新宿区歌舞伎町1-27-3 KKビル1階
- 電話番号:03-6457-3328
- 営業時間:11:00~翌5:00(L.O 4:30)
- 定休日:無休(年末年始を除く)


高級素材「焼きあご」をふんだんに使った塩ラーメンで好評を博す「焼きあご塩らー麺 たかはし」。代表の高橋夕佳さんが開店までの経緯を教えてくれました。
「もともとは、東京・茗荷谷で塩ラーメン専門の店を営んでいました。そのときから、材料のひとつとして使っていたのが『焼きあご』です。塩との相性の良さは確信していたのですが、流通量が少なく、原価も普通の煮干しの5~6倍。そこで、まずは焼きあごの味をどうすればより活かせるかを研究するとともに、仕入れ先の開拓に時間をかけました。最終的には専用倉庫で管理することである程度大量に発注できる目処がたち、焼きあご専門店として開店することができました」

こだわりの焼きあごは長崎県の平戸瀬戸産。水揚げされたばかりの新鮮なトビウオから頭とはらわたを丁寧に取り、備長炭で焼き上げて旨みを閉じ込めた逸品です。
「塩は沖縄の天然塩を使用。塩ダレにも焼きあごを使っているので、寝かせて熟成させるのが鍵になっています。だいたい5日間から一週間寝かせることでアミノ酸が増え、旨みがより濃厚になるんです」。
こうしてできたスープと最適な相性だったのが栃木県佐野市から毎日取り寄せる青竹打ち麺。もっちりしつつも適度な縮れがスープと絡み、渾然一体の味わいを生み出します。


「ラーメン店に求められるのは個性」と語る高橋さん。唯一無二の「焼きあご塩らー麺」以外にも、高橋さんの出身地である新潟を意識した個性的なラインナップがメニューを彩ります。
「塩以外にも、新潟県の燕三条エリアのご当地ラーメンである背脂醤油も提供しています。塩一本でいくよりも、対称的な味を作っておくことで、カップルで来店された場合などにシェアしていただける良さが生まれます。それと、当店で特徴的なのは『白めし』ですね。新潟産コシヒカリをお店で精米し、小・中・大一律100円で提供しています。これだけ白米が出るラーメン店は珍しいんじゃないかというくらい、毎日ごはんは良く出ます」。
焼きあご塩・背脂醤油・白めしという三本柱が好評を博し、開店当初は1日平均150人だった来店者数は9ヶ月後には平均350人に増加。右肩あがりの成長の背景には、味の追求もさることながら、スタッフも含めた「経営者視点の徹底」がありました。
「当店では、アルバイトも含めスタッフ全員で毎日の売り上げデータを共有するようにしています。スタッフ一人一人がお店の主役であり、経営を担っているんだという意識を徹底することが、接客にもつながってくると思うんです。お店が舞台だとしたらスタッフは役者。人対人の商売だからこそ、どんなに疲れていても役者として演じきる。そんなモットーを日々心がけて経営しています」。
新宿駅南口近くに店を構える「麺屋海神 新宿本店」。その特徴は、季節ごとに変わる5種類の鮮魚のアラで炊いたスープです。雑居ビルの2階という難しい立地にも関わらず、魚介スープの優しい味わいを求めて列がたえない人気店です。
- 麺屋海神(かいじん) 新宿本店
- 住所:東京都新宿区新宿3丁目35-7 さんらくビル2F
- 電話番号:03-3356-5658
- 営業時間:[月曜~土曜]11:00~15:00、16:00~23:30/
[日曜]11:00~23:00 - 定休日:不定休


「当店の主役はスープです。ぜひ、全部飲み干して欲しい! そう思って、一杯一杯をご提供しています」。
取材に答えてくれたのは「麺屋海神」代表の遠藤悦子さん。季節ごとに変わる旬の鮮魚の「アラ」を贅沢に炊き上げた塩スープがこの店の自慢です。
「塩とアラの組み合わせは、私自身が好き、というのもありますが、お肉を食べられない方でも楽しめるラーメンはできないか、という発想がキッカケです」。
魚の味を凝縮した優しい味わいが支持を集め、今や吉祥寺や立川などにも支店を展開する人気店になった「麺屋海神」。ただ、2007年の開店当初は失敗続きだったといいます。

「まず、アラの仕入れ先を確保するまでが大変でした。そして、その仕入れたアラをお店で調理するわけですが、当初は上手く血抜きができずにスープが赤くなったり、えぐみが出てしまったりと上手くいかないことが多く、せっかくスープを作っても『これじゃダメだ』と、お店を開けられないことが何度もありましたね」。
また、開店当時はまだまだ塩専門の店が少なく、塩ラーメンを食べたい、という需要も少ない時代。その中で「塩」の認知を広めていく難しさと苦労もあったと振り返ります。
「それこそ、『塩ラーメン!? 味噌ないの? とんこつは?』と帰られるお客さんもいらっしゃいました。その都度その都度、『一度食べてもらえれば分かります』と説明して召し上がって頂いていました」。


店内に大きく掲げられた「本日のアラ」は季節ごとに5種類。ただ、季節によってはさっぱり系の魚が集まったり、脂がのった魚で濃厚なスープになったりと味わいに差が出ることも。その中で安定した「麺屋海神」の味になるよう、沖縄産、モンゴル産、中国産の3種類の塩をブレンドした塩ダレの量を微妙に調整することでこだわりの一杯が完成します。
「ここ1、2年の間だけでも、塩ラーメンの需要は急激に増えてきた感覚があります。でも、時代が変わり、お客様が増えても、私たちの味のベースの部分は変わりません。時代に流されず、しっかりと美味しいものを提供していきたいと考えています」。
看板メニューは昔から変わらず「あら炊き塩らぁめん」。繊細でシンプルなスープだからこそ、白髪ねぎ、みょうが、針しょうが、大葉、糸唐辛子の5種類の薬味の使い方次第で、味わいは千種万様な広がりを生み出します。また、季節や店舗ごとに、はまぐりやあさり、うにを使った商品を提供したりと、味の追求・開発にも余念がありません。
「塩ラーメンは、醤油や味噌、豚骨に比べればまだまだ市場は小さいですし、繊細かつシンプルでごまかしが利かない分、難しさもあります。でも、伸び代もまだまだあるジャンルだと思っています。その中で、上品な味わいを追求したり、和食をいただくという感覚を大切にしていきたいですね。『らぁめん』とメニュー表記を平仮名にしているのも、そんな思いからなんです」。
塩専門という誇りと、和の味わいを追求するこだわりがある限り、「麺屋海神」を求める列はさらに長くなりそうです。
東京都町田市の住宅地に店を構える「町田汁場 しおらーめん進化」。まだ塩専門店が少なかった時代から固定客を獲得し、その人気は衰えを知りません。素材にこだわり、手間を惜しまず作る塩ラーメンはまさに王道の味わいです。
- 町田汁場(しるば) しおらーめん進化
- 住所:東京都町田市森野3-18-17 WING森野103
- 電話番号:042-705-7122
- 営業時間:[火曜~土曜]11:00~15:00、18:00~21:00/
[日曜・祝日]11:00〜17:00 - 定休日:月曜日(祝日の場合営業、翌日休業)


ラーメン通が一度は訪れる有名店「せたが屋」グループ。その中で店長も務めた関口信太郎さんが塩ラーメンに特化した「進化」を開店したのが2007年のこと。以降、地道な店舗運営が功を奏し、今では町田駅前にも支店を構える塩ラーメンの人気店です。
「店を構えようと思い始めた当時は塩専門店なんてほぼなくて、『塩もあります』という店が多少ある程度。だからこそ、本物の美味しい塩ラーメンを食べてもらいたいと思いました。こだわったのは『塩ラーメン専門店』であること。醤油など他の味もあるとどうしてもそちらを注文してしまいがちですが、塩しかなければそれを注文するしかないですから」。

ただ、塩専門を掲げても「醤油はないの?」という客層も開店当初は多かったという関口さん。塩ラーメンを求める固定客がつくまでは1年近くの時間が必要だったと振り返ります。また、調理する上での難しさや気を使う部分もあったと関口さんは語ります。
「たとえば醤油ラーメンは醤油自体の味わい、味噌ラーメンは味噌そのものの味が全面に出てきます。でも塩ラーメンの場合、塩だけで味を構築することは難しい。結局、塩ラーメンにおける味わいの主役は『出汁』なんです。そうなると、その日作る出汁にちょっとブレが出ただけで、すぐにラーメン一杯の味にも影響が出てしまいます。それだけに、毎日真剣に味見をしながら、ブレが出ないように心がけています」。


看板メニュー「進化のしおらーめん」で使用する塩は、高知産天日塩、広島産藻塩、宮城産粗塩、ベトナム産天日塩、兵庫産粗塩の5種類。そこにあわせるこだわりの出汁は、2種類の地鶏と豚ゲンコツ、アクセントに香ばしく焼いた長崎産アゴを加え、さらに30種類以上の食材と一緒に約5時間炊き出してようやく完成します。ただ、開店当時と比べると、塩も出汁もまったく別のものになったといいます。
「塩ラーメンらしいスープにするには、ただ良い塩だけを使うのではなく、ちょっと粗い、苦味成分があるような塩を混ぜるとバランスがとれて美味しくなります。組み合わせや相性を見極めることが大事なんです」。
「進化のしおらーめん」とともに人気の「煮干塩」では、出汁に使う材料はもちろん、塩の種類も麺の種類も変えるこだわりよう。その絶妙なバランス感覚こそ、「進化」が人気店として支持を集める理由です。そして、こだわりと研究心が生み出す味わいに自信と誇りがあるからこそ、麺の堅さや大盛りの注文は受け付けないことにしています。
「最後の一口まで美味しく食べていただけるよう、バランスを意識して『一杯』を作っています。大盛りにするとどうしても味に飽きてダレてしまいますし、麺を固めに茹でると小麦粉の味があまり感じられません。しっかり茹できったときの麺の甘みまで味わっていただきたいですね」。
開店当時と比べれば塩専門店も増え、年々競争が激しくなる塩ラーメンの世界。それでも「本物を出せばお客様は来てくれる」という信念のもと、直球勝負を続けていきたいという関口さん。今後は自家製麺にも挑戦するなど、その“進化”の道はこれからも続きます。
※店舗情報及び商品価格は取材時点(2015年11月)のものです