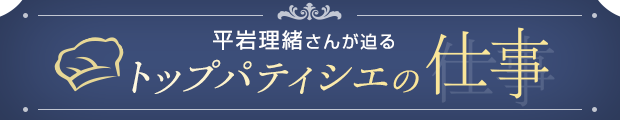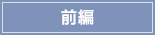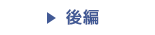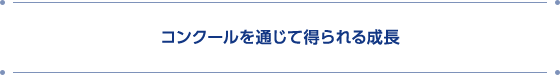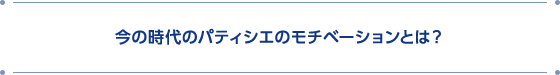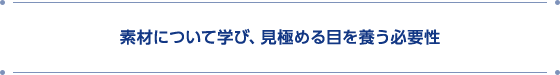菓子職人の方々へのインタビュー連載。今回は、「パティスリー タダシヤナギ」の柳正司シェフです。日頃は、神奈川県海老名市のお店にいらっしゃることが多いのですが、この日は東京都目黒区にある八雲店でお話をお伺いしました。日本洋菓子協会連合会や東京都洋菓子協会のお仕事で、日本各地や世界各国へのご出張も多く、日々ご多忙です。そんな中で、今後、若いパティシエ達は何を目指すべきか、そのためにスタッフの方とどのように接しているかなど、お話をお伺いしました。
- 平岩
- 柳シェフ、お時間をいただきありがとうございます。5月には上海で開催されていた「Bakery China 2019」にお仕事でいらしていましたし、6月には埼玉県洋菓子協会による技術コンクールの審査を担当されていましたね。7月には、11月に韓国で開催される「トップ・オブ・パティシエ・イン・アジア 2019」の日本代表を決定する選考会もあるので、ご準備でお忙しいことと思います。ですが、多くのコンクールで、最近は以前に比べて出品数が減っているというお話を伺います。ご自身も多くのコンクールに出場され、現在は審査をなさるお立場として、現状についてどのように感じられていますか?
- 柳
- 「働き方改革」と言われ、労働時間を短縮しようという中で、正直なところ、コンクールに参加する人数は減っています。
うちの店では、今は大型の細工物というよりは、味覚部門を中心にやっています。自分がよく言うのは、「勝つためにはまず素材選びが大事」だと。味が出づらい素材もあるので、そのようにアドバイスもするのですが、スタッフの中には「自分はどうしてもこの素材でやりたい」とこだわりすぎて、全体の味がなかなか決まらないことがあります。実際に試さないと納得しないのでやらせていますが、コンクールは、自分の実力に見合った準備が必要です。早く決めなくてはその時間が無くなるんですが・・。 - 平岩
- 思い入れが強すぎると、かえって縛られてしまうのかもしれませんね。
- 柳
- 普段の菓子作りでも同じで、プティガトーを考えるにしても、自分のアイディアから抜け出せない、ということがある。一度、捨てることによって新しく出てくることもあり、その勇気が必要だといった話もスタッフにします。
いずれにしても、気迫がないとなかなか賞は取れない。“「ジャパンケーキショー」で銅賞を取ったら立派だ”と言っています。コンクールは、チャレンジすることで、本人にどれだけ成長がもたらされるかというのが大事なんですね。やってみることで、色々な学びを得られます。2-3回やって結果が駄目だと、疲れて続かなくなってしまう。それを乗り越えつつ、デザイン面でも味の面でも、どれだけパティシエとしての実力を上げて、創造力を鍛えていくかということなんです。 - 平岩
- 柳シェフご自身が、コンクールに対して、そのように取り組んでいらしたからこそ、今がおありになるのですね。
- 柳
- いきなり上を目指すのではなく、1つずつ目標をつくり、それを達成していくことです。普段の仕事をびしっとするとか、日頃から色々なことに気が付くといった働きぶりが、実は全てに通じます。たとえば、衛生や掃除はとても大切。掃除を真剣にやるというのは、関係なさそうでいて、それも繋がっているんですよ。うちの丸井ファミリー海老名店の厨房は、もう17年経っていますが、掃除をしっかりしていて、今でも綺麗に使っています。




- 平岩
- 細やかに気配りできることが、パティシエとしての将来的な活躍に繋がっていくのですね。
ただ、最近は、若いスタッフの方達のモチベーションが変わってきた、というお話も、複数のシェフ達から伺います。 - 柳
- 変わっていますね。時には、「本当にパティシエになりたいのかな?」と思うこともありますよ。
自分が「クレッセント」のシェフパティシエを務めた時代には、いつかは河田勝彦シェフ(「オーボンヴュータン」オーナーシェフ)や、島田進シェフ(現「パティシエ・シマ」オーナーシェフ)のようなシェフになれるのだろうか?と思いながら取り組んでいました。大山栄蔵シェフのような菓子をつくりたいとも憧れましたね。1977年に大山シェフが「マルメゾン」をオープンされた際、自分は調布にあった「ピュイダムール」という店で働いていて、その店のオーナーが大山シェフと親しかったので何度か伺っていたのですが、オペラの生地がシロップでひたひたで柔らかく、手で持つと跡がついてしまうほどでした。そのためパレットナイフにのせて台紙の上に置くように注意されたのですが、それがとても印象的でした。それまでの自分達の仕事では、サイドテープを巻いたケーキを手で持ってのせていましたが、わざわざパレットを使うという手間をかけても、このやり方で表現するということに、「これがフランス本場の菓子か!」と感動したものです。 - 平岩
- それは初めて伺いました。大山シェフとは、その頃からの長いお付き合いでいらっしゃるのですね。
- 柳
- その後、フランスに行くつもりで、フランス語も勉強していました。朝6-10時までカセットテープが擦り切れるまで繰り返し聞いて、フランス語の先生のところにも通っていましたよ。
- 平岩
- 柳シェフもそうですが、河田シェフや大山シェフといった、業界の大先輩世代の方々のお若い頃のお話をお伺いしていると、皆さんハングリー精神が凄かったんだな、と感じます。
- 柳
- 「ピュイダムール」は、アーモンドもホールを皮からむいて使っていましたし、粉糖もローラーで挽いていました。サロンも営業していて、ソルベも氷と塩で冷やしてつくっていましたよ。飴細工は、「三笠会館」にいらした藤堂栄男シェフに習ったりしていました。
職人の仕事は、繰り返しになります。それが楽しめるかどうかが重要ですね。お寿司屋さんの仕事なども同様で、単純な分、楽しみや自らの成長を見出すことがより難しい。その中で発見していかないといけません。たとえば、「怒られるのが1回減った」といったことでも、小さな喜びを感じられるようにならないと。 - 平岩
- 柳シェフは、ずっと昔から変わらず、そのように仰っていましたね。お会いして間もない頃、15年ほど前に、製菓学校の学生さん達にそう話していらしたのが、今でも印象に残っています。
- 柳
- 自分は、今思えば若さゆえに勢いで「クレッセント」のシェフになれてしまいましたが、なってみると、ものすごい重圧がありました。週に1回はメニューを変えなくてはならず、それはもう、メニュー名までも、コースに含まれている料理と同じようなフランス語表現が続かないようにとか、細かく気を遣わなくてはならないんです。最初は、アイディアを出し惜しみしたりするのですが、自分の中のデセールのレパートリーなんて、すぐに出し尽くしてしまう。グランドメニュー以外に特別な会食や外務省へのケータリングもあったりして、毎日追われて・・ストレス性の不整脈を発症したほどです。
自分は仕事が出来ないということを晒してでも、とにかくお客様に喜んでもらえるようにしようと、カッコつけるのをやめて、必死にやりました。あの当時があって、今の時代があるのだと思います。期限が決まっている仕事でも、乗り越えてきた経験があれば、大丈夫だと見極められます。



- 平岩
- 最初に、素材を見極めることの大切さについて話されましたが、柳シェフは、素材の研究についても、とてもご熱心でいらっしゃいますね。お若い頃からずっと、様々な試作や試食を繰り返していらしたのですね。
- 柳
- 「クレッセント」は格式の高いグランメゾンのレストランで、贅沢に素材を使うことができましたので、バニラにしても、タヒチバニラとブルボンバニラの違いなども、実体験をもって学ぶことができました。
今は35%の低脂肪生クリームはごく普通に使われていますが、当時、タカナシ乳業に「北生47%」という生クリームがあり、それも美味しいものでしたが、今のような低脂肪生クリームは無かった。食後のデセールにより軽やかさを求め、自分が希望して、日本での38%生クリーム開発のきっかけとなったのです。 - 平岩
- いまや、現代フランス菓子をつくるうえで、ムースなどには35%生クリームが欠かせないですね。
小麦粉についてはいかがでしょうか? - 柳
- 「ピュイダムール」の頃から「スーパーバイオレット」と「スーパーカメリヤ」を使っていたので、もうずっとそれです。他の小麦粉を使ったこともありますが、今はこの2種類に絞って、フィユタージュ(パイ生地)ならば薄力粉と強力粉を半々といった配合にしています。粉を変えるだけでも、食感や口どけ、火通りなどが大きく変わります。粉に関する詳しい勉強は、もっとしたいですね。
- 平岩
- やっぱり、さらに勉強なさるのですね! それから、以前に伺ったお話で、店に届いたフルーツピューレやチョコレートを、味見もしないで常に同じだと思っていてはいけないということを、熱く語ってくださったことがありました。
- 柳
- 自分は、実力が至らないうちにシェフになったので苦しみましたが、その分、とにかく試作を繰り返しました。素材に対しても固定観念にとらわれず、届いたものは必ず検品をします。料理人は皆、味見をするでしょう。それと同じで、今でも常にサンプリングをしています。状態が悪い時には受け取らずに返すこともありますが、いい時には褒めるんです。人間ですから、怒られてばかりだとやる気が出ませんよね。でも、悪い時にはしっかり言って、「ここはチェックが厳しいぞ」と。フルーツは特にそうなんですがプレッシャーをかけないと、いいものは厳しいところに届けて、そうでないところにはあまりよくないものを持っていく、というふうになってしまうんですよね。スタッフにも、検品の時には、「シェフから怒られるので」と言っていいからと伝えていて、シビアに見るよう言っています。
- 平岩
- 農作物は年によっても出来が違い、ピューレやチョコレートにもブレがあるというのをイメージできない若い方も増えているでしょうね。
- 柳
- ものすごく変わることもありますよ。自分しかわからなくて、君たち、なんで気づかないんだ?とスタッフに言うこともありますね。メーカー側が、知らないうちにレシピを変えているといったこともあります。



※店舗情報及び商品価格は取材時点(2019年6月)のものです。
最新の店舗情報は、別途店舗のHP等でご確認ください。