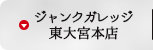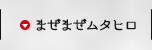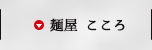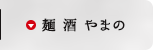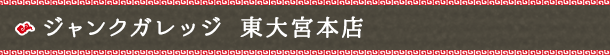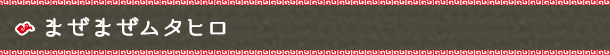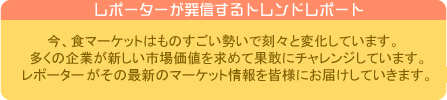

今回は、「まぜそば」「台湾まぜそば」を扱う店舗を取材しました。今後、つけ麺のように大きな拡がりを見せるだろう「まぜそば」の現在をご覧ください。
現在のまぜそば人気に火をつけたといわれているのが、「ジャンクガレッジ」です。
東京都・大崎で創業し、2008年に埼玉県に移転しました。移転先の東大宮本店でも多くのファンを集め、「まぜそばのパイオニア」として味の追求を続けています。
- ジャンクガレッジ 東大宮本店
- 住所:埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-47-4
- 電話:048-662-0036
- 営業時間:11:30~15:00、18:00~25:00
- 定休日:無休


まぜそばのパイオニア、といわれる「ジャンクガレッジ」。
現在は埼玉県を中心にチェーン展開するほどの人気店ですが、この人気店と「まぜそば」の誕生は、2007年にさかのぼります。
「ジャンクカレッジの創業者である高山竜が、ラーメン二郎横浜関内店で食した『汁なしラーメン』に感銘を受け、それを発展させて生まれたのが当店の『まぜそば』です。とにかく、新しいもの・独創的なものを作りたい、という思いが強かったと聞いています」。
こう答えてくれたのは、ジャンクガレッジ東大宮店の店長である葛西尚さん。葛西さん曰く、ジャンクガレッジの独創性の象徴が、「無料トッピング」というアイデアであり、これがお客様の支持を集めているそうです。

「トッピングにベビースターなんて、なかなか発想できないですよね。食感も楽しめるし、『まぜそば』ならでは!の魅力だと思います。
当店では、全部で8種類の無料トッピングを用意。基本的には、全トッピングをオススメしています。全部入れてもケンカしないところがお客様に喜ばれている理由だと思います」(葛西さん)。
「このトッピングが『まぜそば』ならではの『楽しさ』を生み出しています。たくさんのトッピングを自分で選ぶことができる、まぜて食べる、という楽しさの演出が大切だと考えています。 味以上のものを提供する、エンターテイメント性のある店舗を目指していきたいですね」(葛西さん)。
無料トッピングもさることながら、ジャンクガレッジが革命的、と評される秘密が「麺」にあります。

「当店のこだわりは、やっぱり麺ですね。他店のまぜそばや油そばでは中太麺が一般的だと思いますが、当店は極太麺。“バシバシ”した弾力が特徴です」(葛西さん)。
そんなこだわりの麺も、創業当時から試行錯誤によって、常に細かな変化を続け、現在の麺に至ったそうです。
「初期は2種類の違う麺をブレンドしていたと聞いています。極太麺が7割、中太麺が3割。まざった時の食感の違いを楽しんでもらおうという、遊び心もあったようです。
また、中太麺だけの時もありました。そういう試行錯誤を重ね、2年前に『ジャンクガレッジは、やっぱり極太だろう』と、今のオーション(日清製粉の小麦粉)100%の特注極太麺になりました」(葛西さん)。
また、麺の茹で時間も、天候や季節に応じて微調整。毎日スタッフ全員で試食を行い、麺の状態を確認してから開店するのが決まりになっているそうです。
「まぜそばはシンプルなようでいて、実は作る工程では手間ひまがかかります。これまでにもたくさんの変化を遂げて今があるように、現状のまぜそばもゴールだと思っていません。常に進化し続けられるお店でありたいと思います。
まぜそばを出す店が増えている中、ジャンクカレッジが一番美味しいと思えるように頑張っていきます」(葛西さん)。
東京都国分寺市で人気のラーメン店「ムタヒロ」。
煮干しそばの1号店、鶏そばの2号店に続いて、3号店として昨年オープンしたのが、まぜそばをテーマにした「まぜまぜムタヒロ」です。
味はもちろん、遊び心とサービス精神で地域の方々に愛されています。
- まぜまぜムタヒロ
- 住所:東京都国分寺市本町2-13-8
- 電話:042-320-4880
- 営業時間:11:30~15:00、18:00~23:00
- 定休日:火曜


新宿の人気ラーメン店「凪」で修行をした牟田伸吾さんが、新井博道さんとともに「中華そばムタヒロ」を創業したのが2011年。すぐに人気店となり、同じ国分寺に2号店「鶏そばムタヒロ」を開店。
そして、昨年6月に開店したのが、まぜそばをテーマにした3号店「まぜまぜムタヒロ」です。
「牟田が修行をしていた縁で、ムタヒロでは全店、凪さんと同じ多加水極太ちぢれ麺を使っています。
もちっとした食感は、ラーメンはもちろん、油そばにも合うだろうということで、1号店でも開店当時から油そばを出していました。この油そばが好評を博していたこと、そして、学生の街に合う、ジャンクでボリューム満点のものにしようということで、3号店のコンセプトが決まりました」(新井さん)。

また、国分寺がある東京多摩地区は、油そば発祥の地。
このお店から、改めてその点を打ち出していきたい、という考えもあったとのこと。そのため、ベースは1号店で出している「油そば」と麺もタレも同じ。違うのは、麺とより絡まるように角切りチャーシューを豚バラ肉に変更したこと。
そして、「野菜増し」と「麺の大盛り」を無料にしたことだそうです。
「だから、『油そば』と謳っても良かったんですけど、親しみやすさを出すために『まぜまぜ』というネーミングにしました。『まぜまぜ』って、語感が可愛いじゃないですか(笑)」(新井さん)。

「ムタヒロ」全店の共通モットーは『たのしい、おいしい、また来たい』。
「まぜまぜムタヒロ」でもこのモットーを実現するべく、さまざまな工夫が施されています。
たとえば、サービスとして提供されるご飯とスープ。このスープを器に入れればラーメン風に、麺をスープに浸してつけ麺風にすることもできます。
また、残った麺や具材にご飯を混ぜて食べる「めし割り」という食べ方もあれば、スープとご飯、両方投入して「おじや」として食べることも。
「楽しみ方を、お客さん自身でも見つけていただければと。ひとつの商品で二度、三度美味しく味わって欲しいんです」(新井さん)。
「まぜまぜ」とともに2枚看板なのが「カリーまぜまぜ」。カレーらしさを出すために、具材には人参、そしてジャガイモの代わりにポテトサラダをトッピング。ポテトサラダが加わった分、麺がもたついて食べにくくなる場合もあることから、通常の「まぜまぜ」よりもラードを多めに入れて喉ごしが良くなるように、という細かい工夫も施されています。
「これからも既成概念に捉われず、新しいことや楽しいこと、そしてお客様とのコミュニケーションを大切にしていきたいと思っています。将来的には国分寺に限らず、都心にも店舗を増やしていきたいですね」(新井さん)。
東京・南千束に今年1月にオープンしたばかりの「麺屋こころ」。
名古屋のご当地グルメ「台湾まぜそば」の元祖といわれる「麺屋はなび」で修行を積み、満を持して東京にやってきました。
その本場の味は、早くもリピーターを獲得しています。
- 麺屋こころ
- 住所:東京都大田区南千束3-6-9
- 電話:03-6421-9375
- 営業時間:[平日]11:30~15:00、18:00~22:00/
[日曜・祝日]11:30~15:00、18:00~21:00 - 定休日:月曜

「初めて『はなび』の台湾まぜそばを食べた時の衝撃は忘れられないですね」。

そう語るのは、麺屋こころの大将・石川琢磨さん。
かつて名古屋でラーメン店を営んでいた石川さんでしたが、ある日、地元で人気を得ていた「麺屋はなび」の台湾まぜそばを食べたことで人生が大きく変わります。
「ビジュアルも色もキレイな上に、とにかく美味しい。これはもっとたくさんの人に食べてもらわなきゃダメだ。できれば、まだ台湾まぜそばの文化がない東京の人にも知ってもらいたい」と、なんと自分のお店を辞めて、「麺屋はなび」の店主・新山直人氏の下に弟子入り。1年間の修行を経て、東京に出店するに至りました。
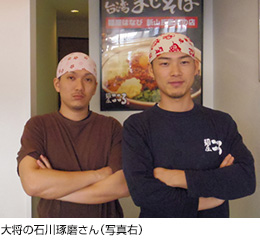
石川さんのこだわりは、東京用に変更を加えたり、自分流のアレンジを加えたりせず、あくまでも元祖「台湾まぜそば」である、「麺屋はなび」の味を忠実に再現することです。
「タレに使う醤油はもちろん、細かいところまで『はなび』と全て一緒です。東京用にカスタマイズする考え方もあるんでしょうけど、変えたらダメだと思ったんです。元祖の味を知ってもらうことこそが大切なんだと。麺に関しても、水の量や小麦の分量も含め、製麺屋さんと交渉を重ねて、東京でも『はなび』で使っている麺とほぼ一緒のものを再現することができました」(石川さん)。
素材だけでなく、調理法にいたるまで、石川さんのこだわりは徹底しています。
「まぜそばはスープがない分、冷めやすいです。温かいまま提供できるように丼を温めておくことは常に心がけています。そして難しいのが麺の湯切りです。普通の湯切りではなく、麺棒であえて傷をつけながら湯切りをしています。これによってタレとの絡みが良くなります」(石川さん)

一見、簡単そうに見えるこの作業も、普通にやると麺が切れてしまうため、その力加減にも技が必要だといいます。
また、「麺屋こころ」で使用する麺は全粒粉の小麦粉でできているため、もっちりとした食感に加えて、ほんのりとした甘味が特徴。湯切りの際にしっかりまぜることでグルテンが生まれ、さらに甘味が増して美味しくなるとのこと。
麺に乗る具材も、もちろん「麺屋はなび」と同じラインナップ。
海苔・青ネギ・九条ネギ・ニラ・ミンチ・ニンニク・魚粉・卵黄が敷きつめられた丼は、見た目も鮮やかです。
「やっぱり、丼を提供した時に、『おぉ!』と驚いてもらえるように意識しています。そして、その具材と麺を、お客様自身でしっかり混ぜていただくことでより美味しくなる。それこそが、まぜそばの魅力だと思います」(石川さん)
「とにかく、一度食べてもらって、香りから味から感じて欲しい」と語る石川さん。
少しでも元祖の味を広めるべく、さらに店舗数を増やす計画も進めているそうです。
東京都練馬で昨年4月にオープンした「麺 酒 やまの」が打ち出す、「台湾まぜそば」は、特製台湾ミンチ「052(オーファイブツー)」が濃厚な味わいを生み出し、一度食べたら病みつきです。
- 麺 酒 やまの
- 住所:東京都練馬区豊玉北5-23-11
- 電話:03-3557-7099
- 営業時間:[平日]11:30~14:00、18:30~26:00/
[土曜・祝日]11:30~14:30、18:30~25:00/
[日曜]11:30~14:30、18:30~23:00 - 定休日:月曜


練馬区を中心に、数多くの人気店を手がける「とらのこグループ」が、昨年新たにオープンさせたのが「麺 酒 やまの」。
店名の通り、昼は麺を、夜はお酒を中心に楽しんで欲しいというコンセプトのもと、東京23区内にも関わらず非常にゆったりとした店内を誇り、家族連れや団体でも気兼ねなく利用できるのが自慢です。
そしてこの店で提供しているのが「まぜそば052」。
「052」は名古屋の市外局番。名古屋のご当地グルメ「台湾まぜそば」にインスパイアされて生まれた商品です。
「スタッフ間の遊び心で、ひき肉を『052(オー・ファイブ・ツー)』と呼んでいます。お客様が、何だろう? と興味を持ってもらえるキッカケになればと思っています」。

そう語るのは、店主の西村貴宏さん。台湾まぜそばを打ち出すことになった経緯についても教えてくれました。
「グループ代表を務める鈴木信介の師匠にあたる方が2年前に他界されました。とてもお世話になった方だったので、恩返しの意味でも、その方に縁のある名古屋の味で何か打ち出せないか、という話になったんです。そこで注目したのが、名古屋で人気を博していた『麺屋はなび』さんの「台湾まぜそば」でした。
ちょうどグループとして、もっと若者に支持をいただける商品を展開したいという思いもあり、その意味でまぜそばは、見た目・味・ボリュームとも若者向きで最適だったんです」(西村さん)。
まぜそばの魅力は「ジャンクさ」と語る西村さん。特に、具材が満載で、見た目にもインパクトがあるのが魅力だといいます。

「まぜそばは、たくさんの具材をしっかりまぜて食べるのが美味しいし楽しい。そこが油そばと一番違うところじゃないでしょうか。具材がしっかり絡むよう、麺はあえて傷をつけてドロドロ感を出しています。それでいて、モチモチ感も残すのが難しいところです」(西村さん)。
ニンニク・ネギ・ニラ・特製ミンチ・魚粉・海苔・卵黄という6種類の具材に加え、自慢の追加トッピング・トロ豚(角煮※300円)はその大きさに驚かされます。
また、見た目ほど食後に油感やクドさ、必要以上の辛さが残らないのも台湾まぜそばの特徴です。
「台湾ラーメンのイメージからか、ただただ辛い、と思われがちです。でも、辛さ以上にひき肉の旨味を楽しんで欲しいし、優しさも出していきたいと思います」(西村さん)。
その優しさの秘訣が「自家製こんぶ酢」。一度火にかけているので、通常の酢に比べてマイルドに味を調えてくれるといいます。逆に辛さを足したい人にはタバスコを用意。他の香辛料と比べ、酸味があるからマイルドな辛さを楽しめるそうです。
そして、まぜそばには無料でご飯が付いてくるので、「追いメシ」として残った具材&タレに絡めて食べれば、最後まで美味しさを満喫できます。
それは「楽しさを大切にしたい」という内容です。
トッピングが自由に選べたり、混ぜ具合も自分で好きなように調整できたりと、まぜそばは食す前の最後の工程が、お客様に委ねられている商品です。
だからこそ、お客様がリラックスした状態でまぜることができるように、お店側にも「楽しさ」を提供する意識が強いのでしょう。エンターテイメント性に溢れるまぜそばは、今後ますます人気を博していくのではないでしょうか。
※店舗情報及び商品価格は2014年12月現在のものです