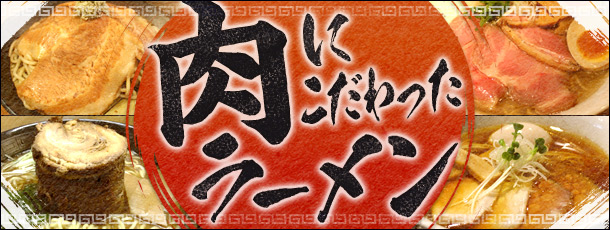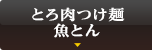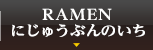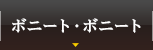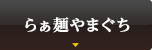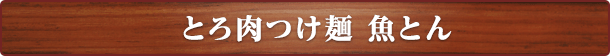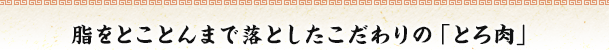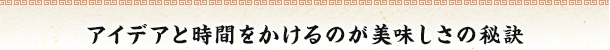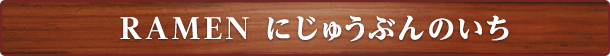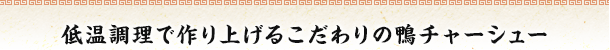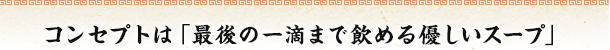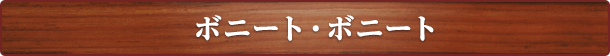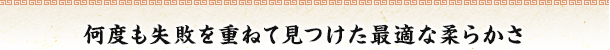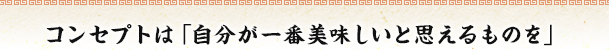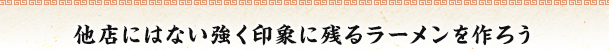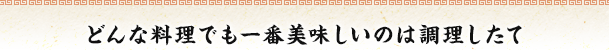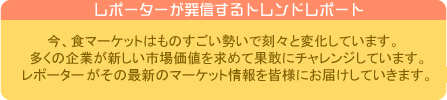

今回はそんなラーメンの内、“肉”にこだわり抜いたラーメンを取材しました。ちょっとしたアイデアだけはなく、徹底してこだわることでお客様にインパクトと驚きを与えます。新メニューの開発や提案に是非参考にしてください。
フィリピン出身のカンラス・ウェンディさんが店長を務める人気のつけ麺店「とろ肉つけ麺 魚とん」。この店の自慢は、噛む必要がないほど柔らかく仕上げた「とろ肉」です。こだわりのとろ肉とともに食べるつけ麺は、ファンの心を捉えて離しません。
- とろ肉つけ麺 魚とん
- 住所:東京都千代田区神田小川町1-7 神田小川町ハイツ1F
- 電話:03-3233-3377
- 営業時間:[平日]11:00~21:00/[土曜・日曜・祝日]11:00~15:00
- 定休日:不定休



「お肉が1枚売れるたびに心が痛むんです。お肉が愛おしいから? いやいや、その理由もありますけど、それよりも、仕込みが大変だからです(笑)」。
麺を覆いつくさんばかりのバラ肉の虜になったファンが、今日もお店の前で列を作ります。このバラ肉こそ、店主が「嫌になる」と冗談めかして言うほど手間をかけて仕込む店の名物であり、店名にも冠せられている「とろ肉」です。
「とろ肉の仕込みは週に2回。その日は朝6時に来て、お肉を一度下茹でして脂を落とし、そこから香味野菜と一緒に13時間とろ火で煮込みます」。
じっくり時間をかけて煮込むのは、味や柔らかさの追求とともに、しっかり脂を落とすためでもあります。
「13時間かけて煮込むと余分な脂が浮き出てくるので、そこで一旦スープから取り出し、そのまま丸1日。そうするとまた脂が出てきます。その脂を取って、今度は冷蔵庫のなかで半日寝かせるとまた脂が出てきます。仕込みはようやくこれで完了です。あとは注文を受けてから1枚ずつスライスして温めますが、そこでまた脂が出てくるので、それを取ってからお客様にお出ししています。そのくらい、脂は徹底的に落としています」
麺の上で圧倒的な存在感を放つとろ肉は見た目以上に柔らかく、口のなかで噛む前にほぐれてしまうほど。しかも、徹底的に脂を落としているのでしつこくなく、女性にも人気の逸品です。


実はこの「とろ肉」、店長であるカンラス・ウェンディさんの故郷・フィリピンで親しまれている豚肉料理をヒントに作ったものだと言います。
「フィリピンの人は、お金をかけずにアイデアと時間をかけて美味しく食べる秘訣を知っているんです」とウェンディさん。同様に、この店には至るところにウェンディさんのアイデアが込められています。
そもそも、この店を始める前は、この場所で営業していたカレー屋の従業員だったウェンディさん。ところが、その店が店じまいすることになり、縁あってウェンディさんがお店を受け継ぐことに。その過程で、ウェンディさんの発案で業態をカレー屋からつけ麺の店に変更し、今の「とろ肉つけ麺 魚とん」が生まれました。そんなバックボーンがあるからか、今もつけ麺のスープで人気なのは「カレーつけ麺」です。
さらに、このカレースープに合うようにと、元々提供していた中太麺に加えて、平打ち極太麺も選べるようにしたのもウェンディさんのアイデアだといいます。
「ある日、武蔵野うどんを食べに行ったらとても美味しくて、それがヒントになりました。カレーは『ツルツル』っと食べる麺よりも、ご飯に近い感覚で『もぐもぐ』食べるスタイルが合うんじゃないかと思ったんです」。
中太麺、平打ち麺の両方を楽しみたい人には、2種類の麺を一皿で楽しめる「合い盛り」も人気です。次から次へと新規軸を打ち出すウェンディさんの、次なる計画とは?
「今はラーメンも提供していますが、つけ麺だけで勝負することも考えています。その方がロスが少なくなりますし。あとは、お店の看板である『とろ肉』をもっと強く打ち出していきたいですね。通販で……というお声がけをいただいたりもしていますが、まだ手が回らない状態です。でも、そのうち、何かやっていきたいと思います」。
人気ラーメン店「山頭火」で修行を積むこと9年。名店で腕を磨いた職人が東京の下町、町屋 で開店したのが「RAMEN にじゅうぶんのいち」です。低温調理で仕上げたこだわりのチャーシューと、最後まで飲み干せる美味しいスープが自慢です。
- RAMEN にじゅうぶんのいち
- 住所:東京都荒川区東尾久2-19-9 西脇ビル1F
- 電話:03-3809-6100
- 営業時間:11:30~14:30/18:00~20:00
※水曜・土曜は昼のみの営業
※夜営業売り切れ次第閉店 - 定休日:月曜



東京・町屋の下町情緒あふれる住宅街のなかに店を構えるラーメン店「RAMEN にじゅうぶんのいち」。店主の佐藤潮人さんが1月20日生まれだったことからつけた店名です。
店の看板メニューは「特製芳醇鶏だしらーめん」。塩と醤油のふたつの味が選べます。そしてこのラーメンが「特製」たる所以は、なんといっても麺の上に美しく並べられた鶏、豚、そして鴨のチャーシューたち。特に、他店ではなかなかお目にかかれない鴨チャーシューは、適度な食感が野性味あふれる力強さを感じさせ、独特の存在感を放っています。
「私もラーメンが大好きでよく食べ歩きをしていますが、新小岩にある『麺屋一燈』さんのチャーシューには驚きました。低温調理で作り上げたチャーシューは本当に美味しかった。一燈さんは鶏と豚肉を使っていましたので、私は鴨のチャーシューを加えて出来たのがこのメニューです。おかげさまで『鴨を食べたい』と注文される方も多く、休日だと売り切れてしまう場合もありますね」。
低温調理で仕上げるだけでなく、鴨肉特有のクセを和らげるため、香辛料のローズマリーを使って臭みをなくす工夫も施されています。
「お肉の臭み消す香辛料は限られています。有名なものでは八角がありますが、好き嫌いが分かれる香辛料です。いろいろ試したところ、ローズマリーが一番しっくりきました。お肉の味も楽しんでいただきたいのですが、一番はラーメンに合うかどうか。スープの邪魔をしないのがローズマリーでした」。

佐藤さんは北海道旭川市出身。その旭川発祥で全国的に人気のラーメン店「山頭火」で15歳の頃から働いていたという、生粋のラーメン職人です。
「山頭火のラーメンとは味も見た目もだいぶ違うかもしれないですけど、根っこの部分では山頭火テイストを参考にしています。特にスープの取り方だったり、タレの作り方だったり。山頭火と一緒で、コンセプトは『最後の一滴まで飲める優しいスープ』です」。
その言葉どおり、すっきりした味わいが美味しい塩ラーメンは、最後まで飲み進められるよう、塩分濃度にもこだわりが込められています。
「うちのラーメンは他店よりも若干塩分を抑えているので、最初は味が薄いと感じるかもしれません。でも、食べ進めて温度がちょっと冷めたときに塩がクッキリしてくるはず。和風のお吸い物やお味噌汁のような感覚で作っています。最後まで飲めて、毎日飲みたくなるスープが理想です」。
このスープに合わせるべく、開店からまだ2年なのに、麺もすでに2回変更したといいます。
「最初は博多ラーメンのように白くて細い麺を使っていましたが、今使っているのは全粒粉を練り込んだ麺になります」。
極細麺にもかかわらず、噛むとさっくりとした食感があり、スープに負けない存在感が魅力です。麺、そしてチャーシューの食感を交互に楽しめるのも、「特製芳醇鶏だしらーめん」の特徴のひとつといえるでしょう。
素材のひとつひとつにまで徹底的にこだわった逸品は、地域住民の日々の食事に彩りを与えています。
鰹節に徹底的にこだわったラーメンを作ることで人気のラーメン店、「ボニート・ボニート」。3種類の鰹節を独自にブレンドして作るこだわりのスープとともに、この店のもうひとつの名物が柔らかく煮込んだ煮豚。その圧倒的な存在感は、お客様に驚きを与え続けています。
- ボニート・ボニート
- 住所:東京都品川区小山4-1-8
- 電話:03-3792-7713
- 営業時間:
[平日]11:30~14:15/18:15~21:45
[土曜・日曜・祝日]11:30~15:00/18:15~21:45 - 定休日:月曜(祝日の場合翌日)



東京・武蔵小山にあるラーメン店「ボニート・ボニート」。この店で「煮豚めん」を注文すれば、他では見たこともない、まさにオンリーワンなラーメンに出会えます。ラーメンどんぶりの中央に、高さ約6cmの円柱が鎮座……これこそ、ボニート・ボニートが誇る「正油あらびき煮豚めん」です。
「以前は、6枚の煮豚を並べていたんですけどね、ある時ふっと『ブロックのまま出したほうがインパクトあるな』と閃いて常連客に出してみたら、『えぇっ!? 大将、これ食べ応えがすごいですよ!」と驚いてくれて(笑)、そこから今のスタイルになりました」。
笑いながら誕生秘話を語ってくれたのは、「ボニート・ボニート」の大将、城下宣博さん。
「これだけのブロックで出すと、ちゃんと柔らかくないと食えたもんじゃない。でも、うちは中まで柔らかく作っているからね。最近じゃ、女性客でもわざわざ食べに来てくださる方がいらっしゃいますよ」。
師匠はいない、という城下さん。この煮豚に関しても試行錯誤を続け、何度も失敗を重ねながら、味付け、柔らかさともに最適な塩梅を見つけて今に至ると言います。
「いつも大きな寸胴をひとつ、煮豚専用にしています。開店前に火を入れて仕込むんですが、その後火を消しても、店を開けている間中ずっと撹拌させなきゃいけません。温度が一点に偏らないようにしなくちゃいけないし、なんといってもお肉は冷める時に味を吸っていきますから。あとは自分の感覚で夜にスープから上げて冷蔵庫で一晩冷やす。冷やさないと柔らかすぎて包丁が入らないんですよ。もっと柔らかくすることもできるんですけど、それも切りにくい。今がちょうどいい柔らかさだと思います。年末なんかだと「おせち用に」って、この煮豚だけ買って帰るお客様もいらっしゃいますよ」。

城下さんのラーメン作りのコンセプトは、自分が食べて美味しいかどうか。
「うちの煮豚は豚バラで作っています。でも、よくお客様から『これで豚バラなの?』って聞かれるくらい、しっかり脂を落としています。というのも、脂っこい煮豚とかチャーシューって、私自身が食べられないんです。自分が食べられないものはやっぱり人様に出したくないんですよね」。
同様に、この店のこだわりであるスープも、「自分が一番美味しいと思えるものを」という信念のもと、野菜はすべて国内産、そして3種類の鰹節をブレンドして作った粗挽き粉がベースになっています。店名にある「ボニート」とは、スペイン語で「カツオ」のこと。旨味成分が凝縮されたこだわりの鰹節は、この店の象徴でもあります。
「師匠も弟子もない、私が自分で考えて作ったのがこの鰹節の粗挽き粉。粗挽きの仕方も、大きすぎるとノドに引っかかったりするので、毎回、自分で挽いています」。
自然由来のものしか使っていないから子どもにも安心して食べさせられる、と休日は家族連れで訪れるお客様も多いといいます。
「この間も妊婦さんがね、『入院前の最後の食事』って、うちに来てくれました。あと意外なのが、お医者さんの常連客が多いんですよ。うちのラーメンは食べてもノドが渇かないし、翌日むくんだりしないのがいい、って言ってくださる方もいらっしゃいます。正直なところ、好き嫌いの分かれるラーメンだと思っています。でも、それがオンリーワンっていうものだと思うんですよね」。
ここでしか味わえないスープ、出会えない煮豚を求め、今日もお店は賑わいを見せます。
鶏だし、鰹だしの2枚看板を打ち出して、ラーメン激戦区の高田馬場・西早稲田エリアに店を構える「らぁ麺やまぐち」。スープや麺の素材と製法にとことんまでこだわった店主がもうひとつ追求したのは、鶏チャーシュー、豚チャーシューの調理方法でした。
- らぁ麺やまぐち
- 住所:東京都新宿区西早稲田2-11-13
- 電話:03-3204-5120
- 営業時間:
[平日]11:30~15:00/17:30~21:00
[土曜・日曜・祝日]11:30~21:00(中休み無し) - 定休日:無休



東京でも屈指のラーメン激戦区、高田馬場・早稲田エリアで「らぁ麺やまぐち」が開店したのは2013年1月のこと。もともとはサラリーマンで、趣味でラーメンを作っていた店主の山口裕史さんは、東京・立川市にあるラーメンスクエアで開催された「ラーメントライアウト」という新人発掘企画で入賞したことをキッカケに一念発起。いくつかの店で経験を積んだのち、この地で遂に自分の店を開店しました。
といっても、トライアウトで評価を得たラーメンと、今、お店で出しているものは全く別ものだといいます。
「西早稲田で出店することが決まってから、この辺りのラーメンをひと通り調べました。さすが激戦区といわれるだけあって、私が開店準備をしていた数ヵ月の間だけでも数軒が廃業していたのを見て、普通のあっさりしたラーメンだと印象に残らず、埋もれてしまう! と危機感を覚えました。だからこそ、他店にはない強く印象に残るラーメンを作ろうと思ったときに、鶏と魚介を合わせるという醤油ラーメンのオーソドックスな作り方ではなく、鶏なら鶏、魚介なら魚介、両極端に振ってみようと思ったんです」。
その結果生まれたのが、「鶏そば」と「追い鰹中華そば」の2つの味。そしてスープにこだわるだけでなく、他店との差別化を意識してこだわり抜いたのが「鶏と豚のチャーシュー」でした。


「一般的にチャーシューって、大量に仕込んで作り置きしておくもの。でも、どんな料理でも一番美味しいのは調理したてのはず。そこで、特製のタレで漬け込んでおいた鶏肉を注文ごとに茹で、出来たてのものをトッピングすることにこだわりました。鶏肉の表面に葛粉をコーティングすることで、しっとりとした鶏チャーシューになっていると思います」。
「特製鶏そば」を注文すると、この鶏チャーシューが2枚、そして豚チャーシューも2枚トッピングされ、かなりのボリューム感です。
「豚チャーシューは低温調理で仕上げています。ただ、一般的な70度前後のお湯で煮ていく低温調理だと脂が美味しくない。そこで、オーブンを使った低温調理で、じっくり2、3時間かけて焼いています。これで、肉の旨味が残ったチャーシューに仕上げることができました」。
さらに、この店でぜひとも味わいたいメニューが「地鶏とろ丼」と「ロースト豚丼」。サイドメニューとは思えない完成度を誇ります。
「『地鶏とろ丼』はこの店を始める前に勉強させてもらった福島県郡山市のラーメン店『正月屋』さんで提供している人気メニューに、自分なりのアレンジを加えて提供しています。もうひとつの『ロースト豚丼』は、チャーシューと同じ低温でローストした豚を薄くスライスして載せたもの。ラーメン屋のチャーシューって厚さで評価されることが多いので、じゃあその逆、薄いからこその食感を楽しんでもらおう、と開発しました」。
他店にはない味と工夫が評価され、ラーメン激戦区であっても「らぁ麺やまぐち」は確かな存在感を放っています。
※店舗情報及び商品価格は取材時点(2015年1月)のものです