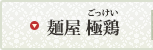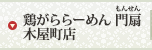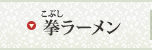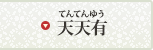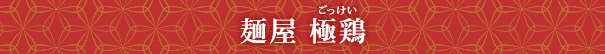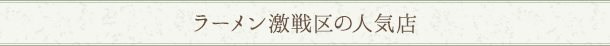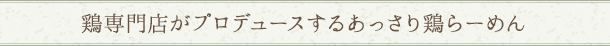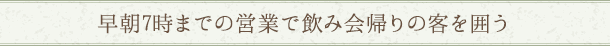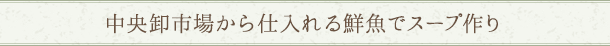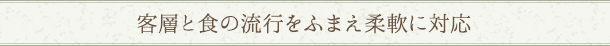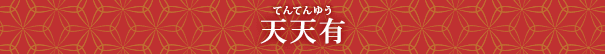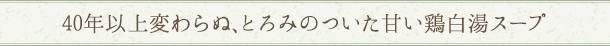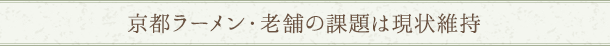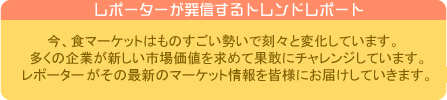

そんな京都の老舗ラーメン店、今注目のラーメン店を取材しました。 その味もさることながら、素材具材へのこだわり、お客様をもてなすお店のこだわりも必見です。京都だけでなく全国でも人気の京都ラーメンをご覧いただき是非商品開発に役立てて下さい。
京都市の中心部から車で約20分、ラーメン店20~30軒が点在する通称[ラーメン街道]にある「極鶏(ごっけい)」。ラーメン激戦区にありながら休日は150人以上の行列ができることもある大人気店です。ラーメンは、濃厚な鶏白湯スープの「鶏だく」と、3つのバリエーションの4種類。まろやかなスープと、エッジの立った固めのオリジナル麺、存在感のあるトッピングのバランスが絶妙で、全国のラーメン好きからも注目を集めています。
- 麺屋 極鶏(ごっけい)
- 住所:京都府京都市左京区一乗寺西閉川原町29-7
- 電話:075-711-3133
- 営業時間:11:30~22:00(スープがなくなり次第終了)
- 定休日:月曜


2011年5月のオープン以来、関西だけでなく全国のラーメンマニアが押し寄せる「極鶏(ごっけい)」。お店があるのは、叡山電鉄一乗寺駅から徒歩約5分、老舗から新店までラーメン店が集まる激戦区「ラーメン街道」。郊外の住宅街でファミリー層が多い地域ですが、京都造形美術大学、京都工業繊維大学、京都大学が近くにあるため、学生アパートも多く見られます。
「もともと美容師を目指していたオーナーがふと思い立ち、ラーメン屋で10年修行。その間に独自のスープを研究し、唯一無二の鶏白湯スープを完成させました。一乗寺はすでに有名店が多いラーメン街道として知られており、物件探しの段階ではこの場所を避けていたそうです。しかし京都市内をくまなく探しても条件に合う物件が見つからず、この地に開業することになりました。開店当初は『本当にお客さんが来るのだろうか』『舌の肥えたラーメン好きに気に入ってもらえるのだろうか』と、不安でいっぱいだったと聞いています(店長・佐々江博則さん)

「極鶏(ごっけい)」の看板メニュー「鶏だく」の特徴は、どろっとした濃厚な鶏白湯スープ。しかし、食べると意外ながらあっさりしており、優しい甘みが口いっぱいに広がります。「オーナーは、“他にない、誰にも真似できない味”にこだわって開発したと聞いています。見た目のインパクトが強い反面、味は驚くほどまろやかというギャップも作戦のうち。鶏白湯スープは開店前にオーナーが作っており、詳しい材料や作り方はスタッフにも知らされていません」(佐々江さん)
強い個性を持つスープに合わせているのは、老舗製麺会社「棣鄂(ていがく)」で作ってもらっているオリジナルの中太麺。角をつけた麺を固めに茹でることで、歯ごたえの良さを出しています。分厚い鶏チャーシュー、極太の柔らかメンマはボリュームと柔らかさが自慢。「鶏だく」のバリエーションとして唐辛子をスープ一面に入れた「赤だく」、自家製のにんにくマー油入りの「黒だく」、魚粉入りの「魚だく」があり、すべて700円。学生が多い地域なので、ご飯はおかわり自由で提供しています。

現在の課題は、行列客への対応。約10人は店舗の中で待ってもらい、店舗の外の行列は1時間以内に案内できる人数まで。お客さんがそれ以上増えると整理券を配布しています。店舗には駐車場や駐輪場がないため、お客さんへの説明も必須です。
1年前までは昼営業と夜営業の間に休みを入れていましたが、行列解消のため、通し営業に変更しています。
「ラーメンを作る、洗い物、ホール、行列対応の役割をスタッフ4名だけで行っています。お客様への気遣いをもっと丁寧にしたい、リピーターを大切にしたい、将来的には店舗数をどんどん増やしていきたい、と、課題が数多くあるため、正社員の確保を急いでいます」(佐々江さん)
濃厚ながらも優しい味わいのラーメンは、近隣の学生の口コミから評判が広まり、コアなラーメンファンの心までもわしづかみに。「コラーゲンがたっぷりで嬉しい」という女性客がここ1年で増えたのは、嬉しい誤算のようです。ラーメン激戦区にありながら行列のできる店として有名になったのは、個性が際立つスープと、麺やトッピングでメリハリをつけた味のバランスの良さが優れていたからに他ありません。
京都市の郊外、伏見区に本店がある焼き鳥専門店「門扇(もんせん)」が展開する「鶏がららーめん 門扇(もんせん) 木屋町店」。メインターゲットは、飲み会帰りの学生やサラリーマン、そして朝方に訪れる、近隣の飲食店スタッフ。鶏ガラスープを使った「鶏らーめん」は、お酒を飲んだ後でもするりと食べられるあっさりとした味付け。同じスープを使ったチキンカレーも人気です。
- 鶏がららーめん 門扇(もんせん) 木屋町店
- 住所:京都府京都市中京区木屋町四条上ル二筋目西入ル 四条KGビル1F
- 電話:075-255-7123
- 営業時間:19:00~翌7:00
- 定休日:月曜(祝日の場合は火曜)


阪急京都線河原町駅から徒歩約3分。京都の繁華街である河原町通りと飲食店が並ぶ木屋町通りの間、車も通れないほど細い路地にあるお店「鶏がららーめん 門扇(もんせん) 木屋町店」。焼き鳥専門店のぎおん店で、鶏がらスープを単品メニューとして提供していたところ、「麺を入れてラーメンにしてはどうだろう」という声がお客さんからもスタッフからもあがり、ラーメンとしてメニューに出したのが「鶏がららーめん」の始まり。その味が口コミで広まるにつれ、焼き鳥を食べずにラーメンだけを求めるお客さんが増えたため、2009年にこちらの木屋町店が開店しました。
「門扇(もんせん)」は焼き鳥専門店2店舗、鶏がらラーメン店2店舗、おばんざいとらーめんのお店1店舗、フランチャイズで横浜と台湾の店舗を展開しています。また、鶏ラーメン、チキンカレー、鶏チャーシューなどを通信販売しています。

鶏がらスープはモミジと呼ばれる足の部分と、くさみ消しとしてニンニクや香味野菜を炊き、一日寝かせてからラーメンに使用。夏と冬で鶏ガラの品質が若干異なるため、スープを炊く時間などを調整して品質の安定に努めています。
お酒を飲んだ後でもすっと食べられるよう、スープはコクがあるのにあっさり。喉ごしのよい細ストレート麺で、トッピングは大根とニンジンの千切りとネギ。自家製の鶏チャーシューと茹でた白菜も入り、鶏ナベのような感覚でいただけます。麺が1/2の量の「鶏ラーメンミニ」、手ごねのつくねを乗せた「つくねらーめん」、野菜たっぷりの「野菜ラーメン」、ピリッと辛い「担々麺」は、すべて鶏がらスープがベース。枝豆、鶏から揚げといった一品料理の他、お酒も揃えているため、ラーメンを注文せずに2軒目、3軒目として利用するお客さんも多いそうです。

「飲み屋さんが並ぶ歓楽街・木屋町という場所柄、飲み会帰りのお客さんがメインターゲットです。店は19時から開けていますが、平日も休前日も一番忙しい時間帯は終電前後の23時~深夜1時。次に忙しいのは、近隣の飲食店が閉店したあとの朝4~5時です。このエリアには早朝まで営業している店が少ないため、朝7時まで店を開けています」(店長・永代一成さん)
木屋町は10年以上「オフィス街・烏丸に店も客も流れて売り上げが減った」といわれ、厳しい状況が続いています。しかし、5年前には4~5軒しかなかったラーメン店が、2014年の現在は約20店舗にまで増えました。
「格安の居酒屋さんなどカジュアルなお店が増えていますね。他の飲食店が流行ってくれないとうちにもお客さんが流れてこないので、木屋町全体が盛り上がるのは歓迎です。近隣にラーメン店は増えていますが、朝7時まで営業しているのはうちだけなので特に気にしていません。飲食店が隣接する歓楽街のため、他店の従業員とのコミュニケーションが密なのも木屋町の特徴。他店のスタッフに聞いたと口コミで訪れるお客さんが多く、助かっています」(永代さん)
同じ鶏がららーめんを提供するぎおん店は徒歩約10分の距離にありますが、一品料理、コース料理を数多く揃えており木屋町店とはターゲットがまったく違います。場所の特性をうまく見極めてお店の個性を活かしたのが成功の理由でしょう。近年は百貨店帰りの女性客や、豚肉を一切食べないイスラム圏の外国人が19時~という早い時間に訪れるようになったといいます。新たなファンを獲得しつつある「門扇(もんせん)」は、将来的には大阪や東京への出店を視野に入れており、さらなる拡大に期待が持てます。
JR嵯峨野線丹波口駅より徒歩約10分。京都水族館のある梅小路公園の北側に位置する「拳ラーメン」。中央卸市場のすぐそばという立地ならではの、旬の鮮魚と黒地鶏のスープを使ったラーメンが自慢のお店です。魚介ベースの「塩系」「醤油系」を主軸に、濃厚魚介のスープを使った「豚ニボWING」、一ヶ月限定の凝ったラーメンなどを提供。基本を大切にしつつ、攻めの姿勢も見せるユニークな展開は、ファンを飽きさせることがありません。
- 拳(こぶし)ラーメン
- 住所:京都府京都市下京区朱雀正会町1-16
- 電話:075-351-3608
- 営業時間:11:30~14:30/18:00~22:00
- 定休日:水曜


オーナーの山内健吾さんは、もともと和食の料理人。祗園の割烹や居酒屋で経験を積む中で出会った“鶏ガラ”に魅了され、ラーメンを独自で研究。住宅街・千本三条で出したラーメン店を移転リニューアルという形で出店したのが、今のお店である「拳ラーメン」です。
「電車でのアクセスが良くなかった千本三条の店がそこそこ流行ったので、立地は関係なく勝負できると思い、2011年、梅小路公園前に移転オープンしました。開店当時は予測していなかったのですが、2012年に梅小路公園内に京都水族館がオープン。2016年は交通科学博物館が開業予定となり、京都では話題のエリアになりつつあります」(山内さん)
メインのラーメンのベースは隣接した京都中央卸売市場で仕入れる季節の魚介、オマール海老、鯛、マグロ。魚の頭をコンベクションオーブンで低温長時間で焼いて作るスープに、黒地鶏のスープを3:7で合わせ、さらに自家製エビ油を加えて完成させています。基本のラーメンは「塩系」「醤油系」の2種類。オマール海老の頭を焼き上げ、豚骨と濃厚味噌を合わせたスープにちぢれ麺を合わせた「石焼オマール味噌つけ麺」、ローストした豚骨を煮込んだ濃厚スープの「豚ニボWING」など独自開発のラーメンも展開しています。1ヶ月限定のラーメンは、昼・夜それぞれ20食のみ用意。山内さんの遊び心とこだわりが詰まった内容で、2014年12月限定メニューは「デミグラス骨付きチキン焼き混ぜそば」です。毎年12月24、25日の2日間は赤カブでピンク色に染めたスープのつけ麺が登場します。

「鮮魚のスープは生臭さが強く出やすいため、火加減や煮込み時間を細かく調整して管理しています。2014年1月までは塩で包んだ塩釜チャーシューを作っていましたが、現在は昆布で肩ロース豚肉を包んで焼く“昆布〆チャーシュー”を使用。ベーコン、鶏ハムはすべて手作りで、メンマは自家製生醤油タレで煮込んでいます。チンゲン菜やタマネギなどの有機野菜は滋賀県の契約農家から直接届けてもらっています」(山内さん)と、素材にも調理にも繊細なこだわりが見られます。
「豚ニボWING」の豚骨と鰹節を合わせた濃厚な魚介スープにうまくからむのは、製麺会社「棣鄂(ていがく)」が開発したウィング麺。断面が漢字の『人』の形のユニークな麺で、イチ早く取り入れたのが「拳ラーメン」。現在ではつけ麺店だけでなく、イタリアンレストランのパスタとしても使用されています。

「店舗が千本三条にあった頃は肉体労働者のお客さんが多くマニアックなラーメンも受け入れられていました。梅小路公園前に移転した現在は、ファミリー層やサラリーマン、年配のお客さんがメインに。鮮魚スープのベースは変えていませんが、内装を明るい印象にしたり、BGMを洋楽にするなどイメージ向上に努めています。和食、イタリアンなどプロの料理人やおしゃれなカップルが増えているので、スープやトッピングはその都度マイナーチェンジをはかっています」(山内さん)
和食出身のオーナーならではの繊細な味付けや美しい盛りつけ、あっと驚かせる手腕は、一般客だけでなくプロの料理人からも注目を集めています。お客さんの層や食の流行をとらえ、柔軟に対応する姿勢なのは人気店の必須条件だといえるでしょう。
京都市の住宅街・一乗寺が「ラーメン街道」と呼ばれるようになったはるか昔、1972年創業。屋台が前身の天天有(てんてんゆう)は、鶏白湯のスープに中太麺の「中華そば」を40年以上同じスタンスで提供。奇をてらっていないのに、いつの時代も新鮮さと懐かしさを同時に感じられるラーメンには、お客さんをほっとさせる秘密がたくさん詰まっています。
- 天天有(てんてんゆう)
- 住所:京都府京都市左京区一乗寺西杉ノ宮町49
- 電話:075-711-3255
- 営業時間:【月曜~土曜】18:00~26:30/【日曜・祝日】18:00~25:30
- 定休日:水曜


京都市の住宅街・一乗寺にある「ラーメン街道」。約20~30軒のラーメン店が密集する全国でも珍しいエリアです。1972年創業の天天有(てんてんゆう)は、京都市内で老舗といわれるお店。コンビニのカップラーメンやパーキングエリアなどで販売されている袋麺の監修も行っており、全国的に名前が知られている有名店です。
前身は、父親が引いていた屋台。1972年に「天天有(てんてんゆう)」として店舗をかまえ、現在はオーナーの漆畑嘉彦さんが店を切り盛りしています。全国に同名の店舗がありますが、実はまったく関係がないのだとか。2014年現在、のれん分けという形で展開しているのは京都市内5店舗、大阪1店舗、九州1店舗です。
「直営でもフランチャイズでもありません。それぞれの店舗の方向性、ノウハウは同じですが、味の完全再現は目指していません。別の店舗で作るスープは味が違って当たり前。僕は一乗寺の店で毎日スープを作っていますが、もし他のキッチンで同じ品質のものを作れといわれても完全に再現できる自信はありません。その場所で、その場所に合った最高のものを作ることができるなら、一乗寺店のスープを100%再現する意味などありません。スタッフも立地条件も異なるため、メニュー展開や戦略はそれぞれの店舗に任せています」(漆畑さん)

「中華そば」の特徴は、驚くほどの量の鶏ガラを11~12時間じっくり煮込んだ鶏白湯スープ。自然なとろみがついた甘めのスープは懐かしくもあり、ガツンとした豚骨の濃いめラーメンに慣れたお客さんにとっては新鮮でもあります。
「それでも、味の志向には流行があります。もっと美味しくしたいと日々試行錯誤した結果、現在のスープは昔に比べてかなり濃くなっていますね。お客さんの7~8割は大学生なので、おなかにしっかりたまるラーメンを提供したいという気持ちもあります」(漆畑さん)

老舗ラーメン店として安定した経営を行っているようにみえますが、オーナーの悩みは材料費の高騰と、新たな展開への躊躇です。
「僕にとってのラーメンは“安い・うまい・ボリューム満点”という3つの要素が基本。しかし近年、小麦や鶏ガラといったラーメン作りに欠かせない材料が値上げされ、危機を感じています。もうひとつの課題は、お客さんがラーメンに求めるものが、昔と今で違ってきているということ。昔のラーメンはファストフードの位置づけでしたが、今のラーメンは“行列もいとわないレジャー”。常にお客さんを引きつけるために新しいメニューを開発してみたいのですが、メニュー数を増やすと提供までの時間がかかるのがネックで踏み切れずにいます」(漆畑さん)
調理はすべて漆畑さんが担っており、全27席のお客さんが一度に注文したとして、お客さんがストレスを感じない15分以内にすべてのメニューを出し終わるようにしているそうです。サービススタッフの数を増やしても調理時間は変わらないため、新たな試みに挑戦する余裕がないのだとか。
漆畑さんがもっとも注力しているのは、最高の状態に仕上げたラーメンを、お客さんを待たせることなく毎日提供すること。目の前にいるお客さんを一番大切にする、という姿勢をもっとも大切にしているため、店舗拡大や量販店での商品開発では柔軟な態度で管理を行っています。若い学生のお客さんが「懐かしい」というラーメンは、世代を超えた永遠のロングセラーだといえます。
※店舗情報及び商品価格は取材時点(2015年1月)のものです