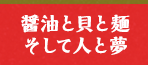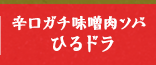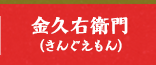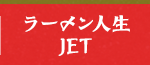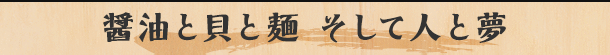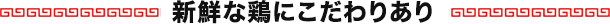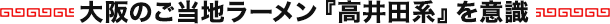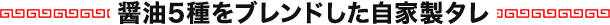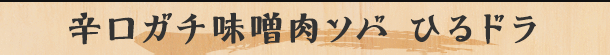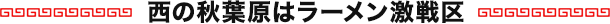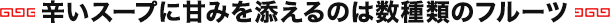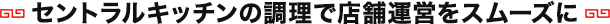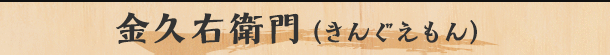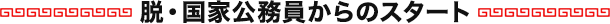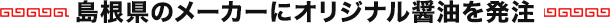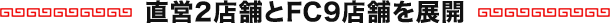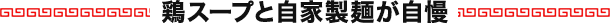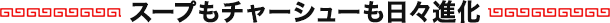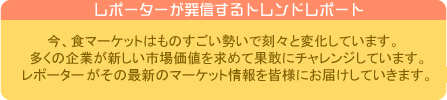

2016年2月、JR塚本駅から徒歩2分の場所にオープン。[醤油と貝と麺 そして人と夢]という店名は、運営会社のコンセプト『人も夢もともに成長させよう~ヒューマン&ドリーム イグジスト』にちなんで付けられました。店名は長いため、“人と夢”と呼ばれています。店長の濱西さんは弁天町にあった人気店[麺や 西や]を手掛けていた方で、ラーメン好きには知られた存在。こちらのお店は近隣に住む幅広い世代のお客さまがほとんどですが、昔からの顔なじみも足を運んでいるそうです。
- 醤油と貝と麺 そして人と夢
- 住所:大阪市西淀川区柏里3-12-22
- 電話番号:06-6472-8186
- 営業時間:11:00~14:30、17:00~22:30
- 定休日:不定休


ラーメンは<中華そば><肉そば(中華そばのチャーシュー大盛り)><鳥と蛤の塩らぁめん><鳥白湯つけ麺>の定番が4種。ほかに、和え麺、約2ヶ月間の限定ラーメン、鶏の唐揚げや蛤の酒蒸しなどの一品メニューも揃えています。
人気を二分しているのが、中華そばと、鳥と蛤の塩らぁめん。ラーメンのスープは、鶏ガラスープ・鶏節の和風スープ・鶏白湯の3種をつくっています。
スープに鶏を使用しているのは、運営会社が焼鳥などの鶏料理店も展開しているため。鶏ガラスープにも鶏白湯にも新鮮な朝びき鶏を使用、鶏節の和風スープには2種類の鶏を組み合わせるなど、鶏に強くこだわりをもっています。
また、中太麺と全粒粉細麺は大阪府枚方市の「ミネヤ食品」、和え麺とつけ麺の中太ストレート麺は京都「棣鄂(ていがく)」にオーダー、と2つの製麺所を使い分けているのも特徴です。


商品開発において、店長の濱西さんが目指したのは、「地域の方に愛される、飽きのこないラーメン」です。「濃厚なスープのラーメンだとインパクトが強いため、毎日食べると飽きてしまうのではと思います。ここは住宅街が近いので、幅広い年代の方がさらりとお召し上がりいただけるような気軽な味を目指しました」。
特に意識したのは、大阪のご当地ラーメン『高井田系中華そば』です。東大阪市の高井田と、隣接する大阪市東成区を中心とするエリアで昔から愛されてきたラーメンで、黒い醤油スープと太い麺、辛みを感じる青ネギの角切りのトッピングが特徴です。

中華そばは、醤油タレを合わせた鶏ガラスープに中太麺、トッピングはチャーシュー、メンマ、太く刻んだ青ネギのみというシンプルな一杯です。高井田系は広く知れ渡っているわけではないため、多くの関西人は見慣れない黒いスープに驚くそうです。
「高井田系のスープはしょっぱいので飲まない人が多いそうですが、当店では塩気を抑える代わりに甘みを加えています」と、濱西さん。
口に含んでみると最初に塩気を感じますが、あとから柔らかな甘さが広がります。意外なほどあっさりしているため、飲み干すお客さまも多いそうです。
味の決め手は、自家製の醤油タレです。和歌山県[湯浅醤油]など醤油メーカー3社・計5種類の醤油に酒、みりん、砂糖を合わせ、味に奥行きを持たせています。ちなみに、お店で取り扱っている醤油は全9種で、ラーメンにより使い分けているそうです。
イベリコ豚のバラ肉でつくるレアチャーシューは、コクのある脂が特徴です。甘みのある脂が溶け出るため、チャーシューの周囲だけスープの味が異なるのも計算された仕掛けとのことです。
「長く愛されるためには、値段と味以上の価値が必要だと思います。私が大切にしていることは、笑顔での接客と店の清潔感ですね。ラーメンがどんなに美味しくても、この二つがなければお客さまはまた来ようと思いませんから」と、濱西さんは語ってくださいました。間接照明やおしゃれな雑貨のある飾り棚のある内装も、心地よい空間づくりの工夫のようです。
2015年6月オープン。場所は、アニメやゲームのマニアが集まる通称『オタロード』がある日本橋でんでんタウンです。
ラーメンのメニューは、辛さに特化した『ガチ味噌肉ソバ』のみ。お店を手掛けているのは、株式会社『ウォームハート』。代表の井川真宏さんは、児童施設のボランティアなどを通して食の楽しみを広げる活動を行う[関西ラーメン向上委員会]の理事も務めています。
今回は、店長の武田さんにお話しをお伺いしました。
- 辛口ガチ味噌肉ソバ ひるドラ
- 住所:大阪市浪速区日本橋5-10-14
- 電話番号:06-6641-2888
- 営業時間:11:00~15:00、18:00~21:00 ※土・日・祝は11:00~21:00
- 定休日:無休

学生や20代~30代の若い層が買い物に訪れる浪速区日本橋。町を挙げたイベントが開催される日には約20万人も動員がある電気街で、西の秋葉原ともいわれています。近年は、ラーメン店の出店が続く激戦区でもあります。
[ひるドラ]は、谷町九丁目[らーめんSTYLE JUNK STORY]、阿倍野[麺と心 SEVEN]に続く3店舗目としてオープンしました。店名は、『ひる』=太陽が輝くように、明るく楽しい空間でたくさんの輪が広がるように。『ドラ』=ドラゴンが火を噴くような、辛くて旨いラーメンを提供したい、という想いを込めて付けられました。


「ラーメン店が多いエリアだからこそ、個性的な味で勝負したい」「若い人たちに、おなかいっぱい食べてもらいたい」という想いで開発されたのが、辛口の<ガチ味噌肉ソバ>です。ラーメンは一種類のみですが、辛さやトッピングを変えたり、ニンニクを抜いたりして好みの味をつくることができます。
スープは、豚のコラーゲンが多い部位をベースに数種類のフルーツ、辛味噌を合わせています。さらに14種類の香辛料、ラー油、焦がしニンニク入りの自家製香味油を重ねています。
「砂糖やみりんを使うと、べたっとした甘さになってしまいます。パンチがありながらじんわりと優しい甘さを感じられるのはフルーツのおかげですね」と、武田さ
ん。辛さは自家製パウダーで調整しており、0~7段階から選べます。
常連のお客さまは、麺を食べ終わった後のスープに白ご飯を投入してチゲ鍋風にしたり、唐揚げをスープに浸してからご飯にのせて丼にしたりと、自由に楽しんでいるそうです。

系列3店舗のラーメンのスープと麺は、すべて大阪市内にあるセントラルキッチンで製造されています。その理由は、品質の安定や衛生管理のためです。また、店舗での労働時間の短縮も目的のひとつだそうです。
「店舗のキッチンでイチから調理をすると、どうしてもスタッフの労働時間が長くなってしまいます。スタッフが疲れていたら、美味しいラーメンづくりがおろそかになってしまうかもしれません。調理をセントラルキッチンに任せているため、私たちは店舗運営に集中できています」と、武田さん。
そのぶん、大切にしているのは接客です。注文用の自販機を設置していないのは、「今日は暑いですね」「どこから来られたんですか」といったちょっとした会話を通じてお客さまと関わりを持ちたいからだそうです。
社名『ウォームハート』には、“食を通して味も雰囲気も楽しんでほしい”というコンセプトが込められています。平日も週末もお客さまの約6割が常連さんなのは、味の良さだけでなくスタッフさんの人柄やアットホームな雰囲気のおかげなのでしょう。
看板ラーメン『大阪ブラック』を武器に、関西のラーメン界で勢力を広げつつある[金久右衛門(きんぐえもん)]。
関西を中心に、ショッピングモールやアウトレットモールなどに11店舗(2016年5月現在)を展開しています。
また、大阪・伊丹空港やJR大阪駅、高速道路のSAなどでおみやげ用の生ラーメンも販売しています。
今回は深江橋にある本店で、オーナーの大蔵義一さんにお話をお伺いしました。
- 金久右衛門(きんぐえもん)
- 住所:大阪市東成区深江北3-2-8
- 電話番号:06-6975-8018
- 営業時間:11:00~15:00、土曜 11:00~16:00
- 定休日:日曜


オーナーの大蔵さんは、国土交通省で9年勤めた元・国家公務員。
「仕事にやりがいを感じていましたが、自分が進んでいく道とゴールが見えてしまっていたことに、くすぶりがありまして。長い下積みを必要としないラーメン屋ならなんとかなるだろうと思い、仕事を辞めて1ヶ月で物件を契約。スープをつくった経験ゼロ、目指す味もなしという状態でスタートしました」。
1999年、3人目のお子さんが生まれたばかりの頃に大阪・玉造で開店しましたが、1年ほどで閉店。のちに現在の本店がある深江橋に移りますが、数年間は売り上げが伸びない日が続きました。それでも大蔵さんがあきらめなかったのは、地元の人たちの応援があったからだそうです。
「大阪市内では、“お客さまの声”のようなアンケート用紙は要らないんですよ。誰にでも受け入れられる味をつくると、『こんなラーメン、どこにでもあるやんか』。奇抜な味は『こんなん食えるか』と、地元の方は言いたいことをストレートに伝えてくださる。お店をしばらくお休みして商品開発に取り組んでいたら『なんでずっと店を閉めてるんや』と、気に掛けていただきました」(大蔵さん)。
大蔵さんは、自分自身のことをまず気遣ってくださる地元の方々の期待に応えねばならないと、“普通”と“奇抜”のあいだを狙うラーメンの開発に着手しました。
看板メニューの<大阪ブラック>は、味ではなく先にネーミングを思いついたそうです。「大阪の町を黒字にして元気にしたい」という想いから味をイメージし、2010年に完成させました。
鶏ガラと豚骨を炊いたスープに合わせる醤油タレは、熱に強い濃口醤油を圧力鍋で凝縮させ、独特の旨みを引き出してつくっています。醤油は、島根県松江市の[松島屋醤油]でつくってもらっている完全オリジナルです。スープは、真っ黒な見た目に反して塩気はかなり控えめで、ふくよかな香りがすっと鼻をくすぐります。麺は細麺か平打ちの太麺が選べます。西日本では細麺が好まれますが、つるりとした平打ちの太麺も好評だそうです。
<大阪ブラック>と人気を二分するのが、薄口しょうゆタレを使った<金醤油ラーメン>。また、濃口と薄口の醤油をブレンドした<紅(くれない)醤油ラーメン>もあります。


展開する11店舗のうち、9店舗はフランチャイズです。そもそも積極的にFC展開を行っておらず、現在も特に募集はしていません。しかし店舗が広がっていったのは、お客さまの「自分がフランチャイズのオーナーになるから、ぜひ営業させてほしい」という声に応えたからだそうです。
フランチャイズ店ではレギュラーメニューとして上記3つのラーメンを置いており、スープは各店舗で、醤油タレは本部で調理されています。スープの味が店舗により多少異なっていても、醤油タレが同じであれば軸がブレないという理由からです。レギュラー以外のメニューについては各店舗の裁量にまかせています。
「独自のメニューがあれば、お店の個性がアピールできます。また、メニューを開発できることがFCオーナーさんのやる気につながると考えているからです。お店の外観やインテリアについても、こちらからのオーダーは一切なし。自由に楽しめる店舗経営をお願いしています」(大蔵さん)。
2016年5月には直営2店舗目を東大阪にオープン。座席数66席、駐車場15台がある、初となるロードサイド店です。これまで本店では取り込みにくかったファミリーや高齢者を呼び込むことで、ファン層の広がりを期待しているそうです。
JR福島駅から徒歩2分の場所にあり、昼も夜も多いときには50~80人、約1時間30分の行列ができる人気店[ラーメン人生JET]。大阪・東成区で、関西に新風を起こした鶏魚介系[きんせい]が2010年、店名を変えて移転オープンしたお店です。東成区のお店は50mほど移転し[ラーメン人生600]という名前で営業しています。
- ラーメン人生JET
- 住所:大阪市福島区福島7-12-2
- 電話番号:06-6345-7855
- 営業時間:11:00~15:00、18:00~23:00
- 定休日:無休


オーナーの山本孝弘さんは、元トラック運転手。
仕事で全国を回るなかでさまざまな種類のラーメンに出会い、ラーメンの魅力に開眼。
29歳のころ、本業が休みの日に大阪府高槻市にあったラーメン店[きんせい]で修業し、2006年に大阪市東成区で自分の店として2号店をオープンさせました。
8坪10席という小さな店だったため福島区に移転し店名も変更しましたが、当時のお客さまより「東成の店も続けてほしい」との声があり、現在は山本さんの右腕として働いていたスタッフが店長となり2号店として[ラーメン人生600]を運営しています。

メニューは、数量限定の醤油・塩のほか、鶏煮込みそば、カレーラーメン、つけ麺があります。
また、黒さつま鶏『黒王』の丸鶏と胴ガラを贅沢に使用した丸鶏醤油そばを土日限定メニューとして展開しています。
中でも、お客さまの7割がオーダーする人気ラーメンが<鶏煮込みそば>です。
ベースは、鶏ガラ、鶏ゲンコツと水だけを10時間以上煮込んだ鶏白湯スープ。和歌山の野尻醤油など3種の醤油と魚介ダシや昆布を合わせたタレを重ねています。鶏の細かい繊維がたっぷり入った、ぽってりと重めのスープも特徴です。
合わせているのは18番の中太・平打ちタイプの麺で、大阪市内にある専用の製麺室で製造しています。
香りの豊かさ、適度なコシ、スープに負けない力強さのバランスを重視し、国産の中力粉のみを使用。平打ちのような麺というと重い印象がありますが、こちらの麺は絹のような舌触りを感じられるように一日寝かせるなどの工夫をしています。
山本さんのもうひとつのこだわりは値段です。ラーメンは730円~で、つけ麺は830円~。ごはん付きは+100円、カラアゲ3個とごはんのセットは+350円です。「ラーメンは、誰もが気軽に楽しむ大衆食だと思っています。そのため当店では、定番のラーメンなら大盛やごはん付きを選んでも1000円以下。地元の高校生がおこづかいで食べられる価格を設定しています」(山本さん)。


全国のラーメンファンだけでなく、欧米やアジアの外国人観光客などが美味しい一杯を求めて足を運んでおり、お店の外は常に行列ができています。
「特に気を使っているのが、オペレーションの徹底です。よそのラーメン店は麺の茹で時間が1分~1分20秒くらいだと聞いていますが、当店は4分かかります。そのため、いかに待ち時間を短縮するかという工夫が必要になります。スタッフ5名中、1名は並んでいるお客さまの対応をしています。オーダーに迷っているお客さまとお話しし、並んでいる時間に食券を購入してもらうといったお願いをしています」(山本さん)。
毎日お客さまが絶えない人気店ですが、店舗数を増やすことは考えていないそうです。
その理由は「新たに支店を作って、食材やスタッフを管理する時間を増やすよりも、美味しいラーメンづくりに集中したい」という考えから。
「常にチャレンジ精神でいるため、スープもチャーシューも日々進化させていますね。<鶏煮込みそば>のスープは1週間前に火加減や時間を変えたばかりですし、豚バラと肩ロースのチャーシューも3日前に豚もも肉に変えたばかり。自分が感じる“美味しい”の一歩先を歩まなければ、お客さまに飽きられてしまいます」と、山本さんは語ります。
※店舗情報及び商品価格は取材時点(2016年6月)のものです