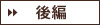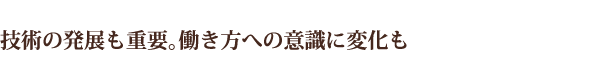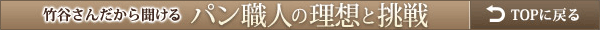「竹谷さんだから聞けるパン職人の理想と挑戦」。今回は特別企画として、竹谷さんとともにパン業界を支え続けている3名のシェフにお集まりいただき、これからのパンづくりについて語っていただきました。メンバーは、日本のフランスパンの第一人者である仁瓶利夫さん、「パン・ド・ロデヴ普及委員会」の技術顧問であり「パン工房ボワドオル」の店主・金林達郎さん、全国にファンを持ち気鋭のシェフを次々に輩出する「ベッカライ ブロートハイム」の店主・明石克彦さんという、パン業界の歴史を築いたシェフたちがパンの未来について語り合いました。
- 竹谷
- 本日はお忙しいところ、お時間をいただきありがとうございます。
- 仁瓶
- こちらこそありがとうございます。
- 竹谷
- 初めてお会いしてから数十年経ちますが、このようにじっくりみなさんとお話するのは、初めてですね。
- 明石
- そうですね。このような機会をいただけたこと感謝しています。
- 金林
- 今日は楽しみにしてきました。よろしくお願いします。
- 竹谷
- では、早速始めましょう。最初は「製パン技術の伝承」についてお話していきたいと思います。
- 明石
- 製パン技術は複雑化しているにも関わらず、それを若い世代に伝えていく時間は圧倒的に不足しています。
- 竹谷
- 昔であれば、ゆっくりと時間をかけて、つまずきながら成長していくこともできましたが、人材不足からベーカリーに就職したらすぐに仕込みを任されてしまうのが現状ですからね。
- 金林
- 帝国ホテルで働いていた時に痛感しましたが、1日7時間半の労働時間内で、学べる内容には限界がありました。もちろん、決められた仕事はこなせます。しかしながら、そこからより成長したいと思うならば、やはり自分自身でやる気を持って、製パン技術に向き合う時間をつくらなければならないでしょうね。
- 仁瓶
- 昔であれば、長く働くことが美徳とされました。今は、お客様、スタッフ、経営者、そしてその家族、それら全ての人々の「幸せ」の総量をどれだけ大きくしていくかが、企業の課題になっていると思います。しかし、現状は多くのベーカリーのスタッフに「幸せ」ではなく「しわ寄せ」がいってしまっています。
- 竹谷
- そうですね。7時間半で仕事が完結するシステムは経営者側がつくっておかなければいけないでしょう。しかし、その時間内に、技術の伝承まで行おうと思うと難しいですね。
- 仁瓶
- そこで参考にしたいのがヨーロッパのシステムです。日本では製パン学校を出てから、就労経験なしにベーカリーに就職する場合が多いですが、ヨーロッパでは、学校で学びながら、ベーカリーでも働くというシステムになっています。これを日本でもしっかりと構築することが大切だと思います。
- 竹谷
- それには、ベーカリーだけでなく各メーカーや企業、学校の協力も必要不可欠ですよね。そういった協力体制がもっと確立していけば「製パン技術の伝承」を全てベーカリーの店主が背負うことなく、よりよいパンづくりを行っていけるでしょうね。



- 明石
- スタッフの働き方に対する意識の確認も重要だと思います。
- 金林
- 独立してベーカリーの店主になりたいのか、それともベーカリーで働ければいいのかという確認ですよね?
- 明石
- はい。その確認はどこかで必ず必要になっていますね。意識の違いによって、しっかりとその人にあった働き方にしてあげることも必要だと思います。もちろん、やり過ぎてしまうとベーカリーは成り立たなくなるので、バランスを考えつつですが。
- 竹谷
- ここでもう一つ考えなくてはならないのは、やはり「勉強する時間」は長くなってもいいが、「本来のパンをつくる時間」は短縮すべきだということです。
- 明石
- そう考えると、30年程前に竹谷さんが講習会でお話された「生地玉冷蔵(低温長時間発酵)」や、「生地玉冷凍」の技術は、パン業界に大きな変化をもたらしましたね。
- 金林
- 「技術の伝承」という問題を考えた時に、やはり「ベーカリーフォーラム」の存在は、私たちにとってとても大きな存在だったと感じられますね。
- 竹谷
- フォーラムの開催時間は18時~21時。本来ならやっと休める時間に開催していたので、参加するとほぼ睡眠時間がなくなってしまうにも関わらず、毎回多くの人が足を運んでくれていました。明石さんは皆勤賞でしたね。
- 明石
- 非常に有意義な時間を過ごせる場でしたし、何よりも楽しかった。新しい技術や自分がまだ知らないことなど、行くたびに刺激を受けていました。
- 竹谷
- 今の若手にもこのような場があれば「技術の伝承」の問題も解決していくのではないでしょうか。
- ※ベーカリーフォーラムとは…
竹谷さんが日清製粉勤務時代に発足し、昭和61年から毎月1回16年間継続されたベーカリーのための勉強会。同フォーラムは若手技術者を中心にスタートしましたが、それらの方々が現在では業界の中心となり、業界の発展に大きな役割を果たしたています。


※店舗情報及び商品価格は取材時点(2018年3月)のものです。最新の店舗情報は、別途店舗のHP等でご確認ください。