


- 平岩
- スタッフの方には、お店の商品開発を任せることもありますか?
- 藤生
- うちの生菓子には、伝統菓子を含めた定番品と、季節ごとの品があるので、責任者には、1人1品、季節の品を考えてもらっています。それに加えて、スーシェフには、「こういう目的で」とか「この食材を使った」といった課題を出してつくってもらったりね。自分1人で考えた時より、変化も出る。そのまま出すこともあるし、直してもらうこともある。
- 平岩
- 採用された方は、励みになりますね。品数も豊富で、個性に富んだコンフィズリーや焼き菓子含め、ギフトも充実されていますが、お菓子について、今後何か、新たにつくっていきたいものとかやっていきたいことはありますか?
- 藤生
- 実は、ショーケースの中の生菓子は、これまであまり見直してこなかったのだけれど、ウィーン菓子の「ツッカベッカライ・カヤヌマ」の栢沼さんのように、「これが自分のお菓子」だという代表的なお菓子を増やしていきたいと思っています。
- 平岩
- 8月には、ご著書『パティスリー・ドゥ・シェフ・フジウの現代に甦るフランス古典菓子』も上梓されました。ファンや関係者にとって念願でしたし、お菓子業界にとって、価値ある一冊となられましたね。
- 藤生
- 山名将治先生のフランス菓子研究会「パティスリー会」に参加して、ずっと一緒にやってきた中で、その活動を本にという話もありましたが、山名先生のご意向もあり、実現に至らなかった。雑誌の連載という話から始まって、そのまとめを主体にして、書籍という形で出すことができました。
また、新しい形になったパティスリー会では、古典からルセットを学ぶだけでなく、メーカーの皆さんにご協力いただいて、素材を学ぶという面も広げたけれど、それも意義のあることだった。 - 平岩
- 小麦粉の勉強会もありましたね。日清製粉さんのフランス産焼き菓子用粉「エクリチュール」の特長など、私も、この勉強会を通じて色々学びました。藤生シェフほどのベテランのシェフになられると、使い慣れている材料を別の物に変えるのは、ちょっと抵抗がありそうなものですが、新しい素材との出会いに対しても、柔軟でいらっしゃいますね。
- 藤生
- 「レジャンデール」は、強力粉とは知らず、それまで使っていたものが廃番になるというので、フールセックに試してみて、一番風味があると感じたので選んだ。
- 平岩
- 「レジャンデール」は、メーカー側でもパン用強力粉、と捉えていらしたそうなので、それをお菓子に使うというのは意外な活用法だったとか。さらに、主にパスタの原料に使用されているデュラム小麦粉をタルトに使われたりもしていますね。
- 藤生
- メーカーの人が持ってきてくれた物は、すぐに試作してみるんだけど、それですぐに商品に採用するというのではなく、しばらく経ってから、そういえば・・と思い出して使い始めるということが結構多い。「エンジェライト」という薄力粉も、持ってきてもらってしばらくしてからの「古典菓子勉強会」でロールケーキに使ってみて良かったので、今お店でも使っている。


- 平岩
- これからのお菓子業界に対して思うことや、こうあってほしいと思われることはありますか?
- 藤生
- パティシエ業界には、その世代ごとのリーダーのような人がいて、フランスで働いていた時も、グループを仕切ってくれ、自分の時には、「オーボンヴュータン」の河田さんや、「サンルイ島」の遠藤さんがそうだった。ただ、今は、業界に対して、「こういうことを考えなくては」と希望を出せる人、それを吸い上げる所というのが、昔よりも少なくなっている気がします。
最近、30-40代のシェフ達と一緒に仕事をする機会があって、例えば、多摩洋菓子協会の「古典菓子勉強会」を一緒にやっている、「アカシエ」の興野君や「パクタージュ」の齋藤さん、「アディクト・オ・シュクル」の石井さん。川口「シャンドワゾー」村山君など、自分が店を起ち上げた頃の情熱とモチベーションを、今、ちょうど持っている世代だと思う。今後、彼ら世代にはさらに活躍してほしい。 - 平岩
- 洋菓子業界も、世代交代の時期に来ていますね。早めのご年齢で引退を宣言される方も出てきていますし、一方で、生涯現役を貫かれるのだろうな、という職人さんもいらっしゃいます。
- 藤生
- 今年1年目の社員は4人入りました。来年入社の新しいスタッフを、大体夏に決めるのだけれど、彼らを5年後に送り出す時に、この店をどういう形にしているかということを考えます。
- 平岩
- フジウを卒業しても、渡仏して、帰国後にまた戻ってこられる方もいらっしゃいますね。それだけ、藤生シェフを慕っていらっしゃるからだと思いますし、そういう先輩方の存在は後輩の方々の励みにもなりますね。
お話をお伺いして、藤生シェフのもとから、すぐれた人材が続々と巣立っていかれる理由が、これまで以上によくわかった気がします。今日は、貴重なお話をどうもありがとうございました。



藤生義治シェフ プロフィール
東京製菓学校を卒業後、都内の洋菓子店に勤務し、1969年に渡欧。パリ「ジャン・ミエ」、ウィーン「ハイナー」で修業し、スイスの「コバ製菓学校」を卒業。帰国後、現在「オーボンヴュータン」オーナーシェフである河田勝彦氏が手掛けていた埼玉・浦和の「かわた菓子研究所」に勤務。80年、東京・立川の「エミリーフローゲ」シェフに就任。93年に自店を開業。現在、国内外での技術指導や後進の育成に尽力。フランス古典菓子の研究にも力を注ぐ。


パティスリー・ドゥ・シェフ・フジウ
東京都日野市高幡17-8
TEL:042-591-0121
営業時間:9:00~20:00
定休日:なし
京王線高幡不動駅から徒歩1分。ショーケースの中は、サンマルクやガトーバスク、オペラなどフランスの伝統菓子が存在感を放っています。ヴィエノワズリーや焼き菓子も豊富で、スペシャリテの「ソーシソン・オ・パン・ヴリュ」をはじめ、古典のレシピ本から再現されたお菓子と出会えるのも、このお店ならでは。ヌガーやキャラメル、クッサンといった小さなコンフィズリー類は、心が躍るような愛らしさ。フランスの地方菓子などが描かれたギフトボックスもおしゃれで、詰め合わせギフトとして大人気です。
平岩
藤生シェフには、これまでにも取材をさせていただいたり、講習会に参加したりしてきましたが、今回は、お店のスタッフの方との接し方やマネージメントについて、より具体的なお話をお伺いできました。特に“交換日記”には感動!先日、OBの方から伺ったエピソードですが、仕事が辛くてお店を辞めたいと伝えた時に、藤生シェフから、「ここを辞めるというなら、パティシエの仕事自体を辞めるのでなければ認めない。ここでやっていけないなら、他のどこに行っても続かないぞ」と諭されたそう。その方の一生を引き受けるつもりだという、強い意志の伝わるお言葉だと思いました。卒業生の皆様はもちろん、多くの後輩のパティシエの方々から慕われている藤生シェフ。改めて、その理由に納得いたしました!
これからも、色々とお教えいただけることを楽しみにしています。こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。
※店舗情報及び商品価格は取材時点(2017年9月)のものです。
最新の店舗情報は、別途店舗のHP等でご確認ください。

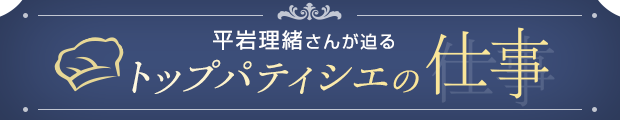
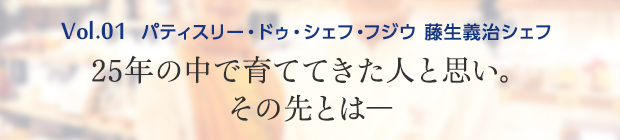
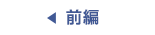
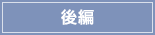


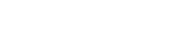

藤生シェフ
インタビューの後、パリとリヨンを訪れて、卒業生が働いているお店を訪ねることができました。リヨンには、自分の大好きなコンフィズリーのお店もあって、パリ以上に好きな町です。先日は、うちの後にフランスへ行って働き、戻ってきてスーシェフをやっていた子がシェフパティシエを務めるパティスリーが都内にオープンしたので、OBの一人と平岩さんも一緒に、訪ねてきたんだよね。それぞれが頑張っていて、会いに行けるのが嬉しい。自分もまだまだやりたいことが色々あって、若い世代との交流や新しい素材との出会いも、大いに刺激になっています。
2018年1月に、著書の発刊記念講習会を開催しましたが、それも、うちのOBが裏方で色々と手配をしてくれていました。平岩さんにはMCをやってもらいましたね。ありがとう。