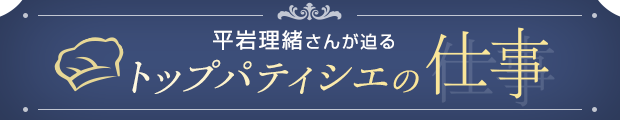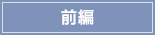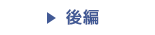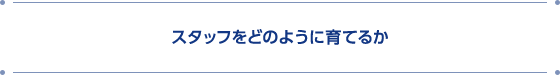菓子職人の方々へのインタビュー連載。今回は、「パティスリー レザネフォール」の菊地賢一シェフです。今回は、2018年4月、師匠である棟田純一シェフの店「季の葩(ときのは)」を譲り受ける形でオープンした中野店でお話をお伺いしました。恵比寿店と行き来しつつ、企業とのコラボや海外の仕事もこなし果樹農家の見学などにも積極的に参加されています。1978年生まれと、次世代を担うパティシエのお1人。今後の目標や菓子業界への思い、スタッフをどう育成するかなど、展望をお伺いしました。
- 平岩
- 菊地シェフ、こんにちは。恵比寿の本店に伺うと、いつもお客様でいっぱいという印象ですが、中野店は、喫茶スペースもあって広々しているので、お邪魔にならずにゆっくりお話をお伺いできますね。
- 菊地
- 中野店は2018年の4月30日にグランドオープンしたので、もう1年以上が経ちました。
- 平岩
- 恵比寿本店は2012年11月のオープンでした。厨房も手狭になっていらっしゃる様子だったので、より広い場所を探そうというお考えはあったかと思いますが、そんな時に、師匠の棟田シェフからのお声がけは、タイムリーでしたね。恵比寿本店と中野店のお菓子のラインアップは、少し変えていらっしゃいますね?
- 菊地
- こちらは、「季の葩」の頃からのお客様のリクエストを受けて、恵比寿とは違うお菓子も出しています。「パイシュー」もその一つで、「季の葩」で人気だったものを復活させました。同じ品であっても、各店舗で価格も変えています。
- 平岩
- それは意外でした。店舗が違っても、同じ品ならば同じ価格なのかなと思っていましたが・・。
- 菊地
- 去年のオープン後、夏がすごく暑かったこともあって、こちらの中野店で、お客様が離れていくのが感じられたんですね。
「価格が高いんだろうか?うちのお菓子が口に合わないんだろうか?」と自問自答を重ねて、価格を安くしてもまずは口にしてほしいという思いで、同じケーキでも恵比寿より安く販売するようにしました。 - 平岩
- そうだったのですね。考えてみれば、お店の場所によって家賃も違う訳ですから、価格もそれに合わせて変わるというのは、納得できる理由ですよね。会員カードもあったと思いますが、それは2店舗共通ですか?
- 菊地
- スタンプカードは店ごとに別にしていますが、会員カードは共通です。
- 平岩
- 会員登録してカードを使うと、買い物の金額に応じてポイントがたまるんですよね。お店としては、会員の方向けにDMなどを送ることができるメリットがあります。この店舗をオープンするにあたって、新たにPOSレジを導入したと仰っていましたよね。会員カードはそれと紐づいているのですね。
- 菊地
- 2店舗共通でデータを管理できるPOSレジは、売り上げ構成比などもわかって便利ですね。
近々、自動つり銭機も導入しようと予定しています。レジ締めをしようとして最後に金額が合わず、何度も計算しなおしたり。そういう時間やストレスは無駄なので、無くしていきたいです。




- 平岩
- 今、スタッフの方はどのくらいいらっしゃるのですか?
- 菊地
- 2019年は春に4人辞めて、8人が新たに入社しました。今、製造販売含めて、恵比寿本店は12人、中野店は13人でやっています。
恵比寿店は夜遅くまでお客様がいらっしゃる立地なので、10時~22時の営業なんです。そのため、朝と夜のシフト制で交代しています。スタッフの人数がいると賑やかですし、休みの人が出ても調整がしやすい。棟田シェフのところで働いていた時も人数が多くて楽しかったです。人が少ないと、息が詰まってしまう。人数が多いと適宜、気の合うグループに分かれるので、居場所が出来ていいですね。 - 平岩
- 中野店のオープンの時は、かなりの行列が出来ましたよね。
- 菊地
- チラシを配ったりした訳ではないのですが、想像以上に、150人くらいのお客様が集まってくださったんです。
- 平岩
- ここにあった棟田シェフの「季の葩」からのお客様も、楽しみに待っていてくださったのでしょうね。
お店側にとって、店舗を増やすことのメリットというのは何ですか? - 菊地
- 仕入れ量が増えるので仕入れ値が下がり、利幅が増えます。でもそれも、このくらい購入するからもう少し安くなりませんか?といったように、業者さんに自分で交渉しなくてはいけないですね。また、個人のお客様はもちろん、企業などの販売先も増えます。
- 平岩
- では逆に、店舗が増えることで難しくなるのは?
- 菊地
- スタッフ、在庫、金銭など、様々な管理が難しくなります。でもそれが、面白さでもあるんですよね。
- 平岩
- オープン以来、スーシェフを務めていらした清家達也(せいけたつや)シェフも、独立されて、2019年1月、川崎市の宮崎台に「パティスリー・ル・ネグレスコ」をオープンされましたね。
- 菊地
- 人を育てることも、難しいですがやりがいがあるなと思います。あまり仕事が出来ないなと思っていた子が、1年経ってみたら意外と出来るようになったり。
- 平岩
- スタッフの方を育てるのに、具体的に、意識しているのはどんなことですか?
- 菊地
- 求めることを直接的に、具体的に伝えるようにしています。「ちゃんとやっておいて」ではなく、「○時までに○○をやってね」というように。そのために、どうしたら実現できるのかを各自に考えてもらいます。そのチェックのために、先輩についてもらうようにしていますね。
自分自身がつくるよりも、つくってもらう方が難しいんですよね。でも、菓子店で働いている彼らは、つくるのが夢で来ている。昔、「ビゴ東京」の藤森二郎シェフに、「みんな、シェフと仕事したくて来てるんだから、一緒に仕事をしないと駄目だよ」と言われたことがあって、本当にそうだなぁと思い、彼らの中に入って、一緒に作業するようにしています。 - 平岩
- 任せることも必要ですが、やっぱり、シェフがいらっしゃると、職場の雰囲気が違いますよね。
最近、お菓子屋さんは、労働時間や休暇への配慮、消費税や裏面表示など、様々な変革を迫られていて、大変だという声が多いですね。ある菓子店が、「今の体制では美味しいものをつくれないので、今年はクリスマスケーキをつくるのをやめる」と宣言したのが、パティシエの方々の間でも話題となって、理解できるという声もある一方、お客様のことを考えるとそうもいかないという声もあり、菓子店が直面する現実の難しさを浮き彫りにしていました。 - 菊地
- クリスマスはお客様にとって幸せな楽しいイベントですが、その楽しいシーンに協力できないというのは、自分達にとって寂しいことです。2018年の中野店のクリスマスは、それまで恵比寿店でつくっていたのに比べて、台数が大幅に増えて、初めての年ということもあり、本当に大変でした。苺の価格も上がっていましたし、もう苺のクリスマスショートケーキはやめようか?と考えたくなることもあります。でも、そこだけで利幅を考えない方がいいんですね。たとえば、こちらでは利益があまり出なくても、その分、お歳暮の焼き菓子で利益を補填しよう、といった考え方をしています。




※店舗情報及び商品価格は取材時点(2019年8月)のものです。
最新の店舗情報は、別途店舗のHP等でご確認ください。