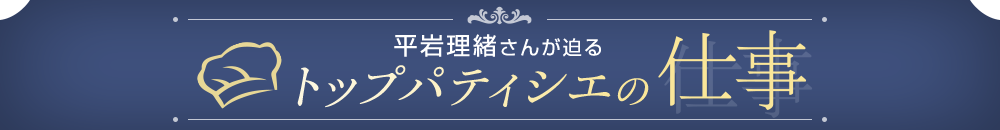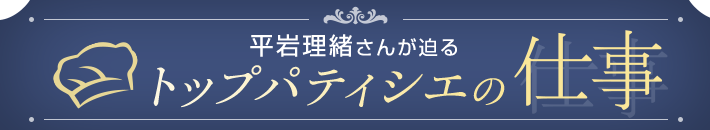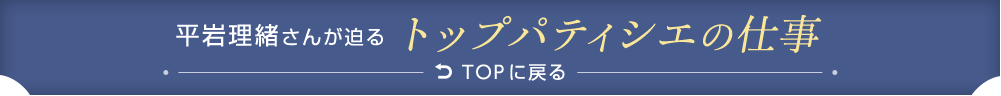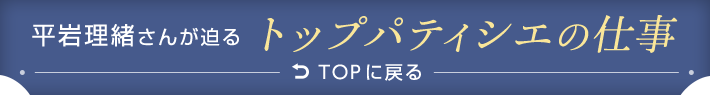菓子職人の方々へのインタビュー連載。今回は、世田谷区・下高井戸「パティスリー・ノリエット」の永井紀之シェフにお話をお伺いしました。今春、還暦を迎えられ、お店も間もなく30年に近づいていらっしゃいます。今や貴重と言える、古き良きフランス菓子店のあり方を示唆する豊富な品揃えは圧巻。それを実現してきた中で、若い職人に対して感じることや伝えたいこと、これからのご自身の生き方についてなど、いつも通りのズバッとした物言いで、語ってくださいました。
コロナ禍を経た最近の変化
- 平岩
- おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。2020年は「クラブ・ドゥ・ラ・ガレット・デ・ロワ」のコンテストも一般会員の参加が無く、2021年1月のフランス大使公邸での献上式も開催されなかったので、お会いするのは久しぶりですね。でも、3月に大阪で開催された「2021モバックショウ」(第27回国際製パン製菓関連産業展)では「クラブ・ドゥ・ラ・ガレット・デ・ロワ」のトークイベントがあって、会場にいらしていたのですよね。
- 永井
- おはようございます、久しぶりだね。大阪から帰ってきたばかりです。展示会の開催も久しぶりだったよね。正直、来場者はやはり少なめだったと思う。出展社も少なかった。材料屋さんとかで試食も出せないとなると、展示会に出たり見に行ったりする必要が無くなっちゃうよね。機械なんかは、実際に見てみたいというのがあるけれど。
- 平岩
- 2020年からの新型コロナ禍によって、製菓業界も、大きな変革を迫られましたね。お店でも、この一年で変えられたことはありますか?
- 永井
- 昨年9月に、新宿髙島屋への出店をやめました。「パティシェリア」という日替わりセレクトショップでの、生菓子の販売も含めて。


- 平岩
- えっ、そうでしたか。最近、デパ地下にも以前ほど行っていなくて、気づきませんでした・・。ここ数年、商業施設への出店契約を終了された個人店オーナーシェフは多いですね。一方で、お店をオープンされて数年くらいの若い世代の方は、宣伝効果という意味もあって、新たに入られるところもありますが。
- 永井
- 自分はこの先、休みはしっかり取る体制にしようと思っています。外に出店していると、店が休みの日でも携帯電話に連絡が入ってきたりしていましたが、それも無くなった。自分自身は人生ずっと休まないで来たので、じっとしているのが辛くて、1日グダグダしているというのは、罪悪感があるんだけどね。もう60歳、還暦だからね。人生の2周目に入ったので、改めて、仕事の仕方、生き方を考えています。もともと、「商売」というのが好きな訳ではないから。
- 平岩
- お休みの日に、ご趣味などお仕事以外のことに充てる時間も増えていらっしゃるでしょうか?
- 永井
- 昔はバイクでふらっと、1人で箱根に行ったりもしていたけれど、最近はバイクも乗らない。年を取るってそういうこと。何だか、色々とおっくうになってくるんだよ(笑)。
業界内の集まりも少なくなって、皆でお酒を飲むという機会も格段に減ったから、人間ドックの検査結果の数値はよくなったよ。家で飲むというのはあまりしないからね。1人で飲むのは、思考回路がぐるぐるするから、精神衛生上よくないんだよ。
- 平岩
- 本当に、昨年から、あらゆる集まりも講習も中止やリモートになっていますものね。どこのお店に伺っても、「最近、店の人間以外、誰とも会ってない」と仰るシェフが多いですよ。
コロナ禍で、人と会って話せないストレスなども社会問題になっていますが、製菓業界でも他人事ではないですね・・。

「働き方改革」の中でも求め続けたい菓子店としての理想
- 平岩
- 話は変わりますが、最近、「働き方改革」を意識すると、品数を絞らざるを得なくなったというお話もよく聞きますが、「ノリエット」は相変わらず、見事な品揃えですね。フルラインナップで凄い!と嬉しくなりました。
- 永井
- 自分は、フランス菓子店のあり方を考えた時に、初めからこういうイメージを持っていたからね。最初は、金銭的な理由とか、若いスタッフがついてこられなくなってしまうとか、理想通りにいかないことはありましたが。
自分が、どういう菓子屋を求めているか、どういう風に表現したいか、人に何を訴えたいかということを、形にしていくことが、自分達の仕事だと思う。理想は人によって違うから、その中で、しっかり商売したいという人もいるだろうけれど、自分は、これまで20数年かけてやってきたように、今後も店をつぶさずにやっていたい。長くやっていけば、自然と、そういう店を求めているお客さんが来る店になるんです。そのためには、ある程度、町中でやる必要はありますが。
- 平岩
- 永井シェフも、少しずつ、求める理想を実現していらしたのですよね。今の時代に、それを続けていくのは、より難しいかもしれません。
- 永井
- 「働き方改革」と言われるのは、日本でもフランスでも同じ。労働条件がよくなるというのはいいことだけれど、捨てないといけないことも出てきます。
これからの若い人達は、選択肢が減っていくという大変さがあると思う。何でもインターネットというのでも、本人達がよければそれでいいのかもしれないけれど。フランスに行った結果として、自分は人にこういうことを伝えたい、と思ってそれをやってきた人間としては、「時代がこうだから」と受動的になってしまうのは、可哀想だなと思う。自分達の時代は、正式な労働ビザが取れず、危険を冒すのと引き換えにでも、どうしても本場へ行きたい、という思いがあった。受動的ではなく、能動的に考えて行動していたと思う。



- 平岩
- 永井シェフの世代は、労働ビザ無しでヨーロッパへ行って働いていらした、いわゆる「ノワール(黒)」と言われる方達も、まだ多かったですね。
- 永井
- モバックショウで、「モンプリュ」の林周平シェフと、「パティスリー エトネ」の多田征二シェフと話しましたが、パティスリーで手作りされるものと、工業品との違いが、日本ではきちんと認識されていない。「コンビニの○○が美味しい」というのと同じレベルで語られているんだよね。それは、マスコミの責任と言える一面もあるかもしれませんし、そこに乗っかっている作り手もいるかもしれませんが・・。「うまく量産できる人間がうまくやれる」みたいな世の中になってしまっていると感じます。
- 平岩
- マスコミのあり方について言われるのは、私自身、そちら側の人間でもあるので、少々胸が痛いです。職人の方々が思いを込めて手作りされているものの価値を、しっかりと伝えていきたいと思ってはいるのですが・・。
- 永井
- 大手の会社は、どんどんブランドチェンジしていけますが、個人はそうもいかない。「ブランディング」って、本来、技術ではないんです。店の内装から何から自分でするのが、本来の「物づくり」。物づくりに向いている人間は、つぶしが効きます。それは、思考回路のことなので、手先が器用かどうかという問題ではないんです。
たとえてみると、あらかじめ出来上がった形のブロックで何か作るというのではなくて、自分で形を削って、切ってはめて、自分で物を作れるか?ということ。決まった形でしか物事を考えられない若い人が増えているなとは思います。
日本の学校教育は、そういう能力を伸ばす方向ではないので、やはり親の影響が一番大きいのかな。家の中でも色々と工夫させないと。昔は子どもの頃に、風呂のマキ割りとかそういう仕事を、怒られながらコツを掴んでいった訳だよね。俺なんて、親父に褒められたことなんてなかったよ。そうやって常にものを考えていた。人って、そういうのが染みついているもので、後から直すのは難しい。

※店舗情報及び商品価格は取材時点(2021年03月)のものです。最新の店舗情報は、別途店舗のHP等でご確認ください。