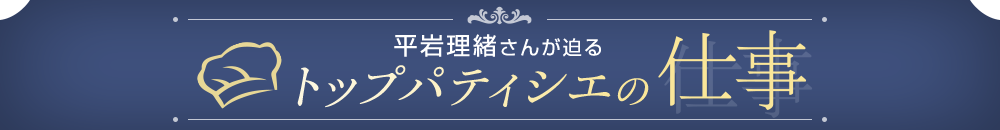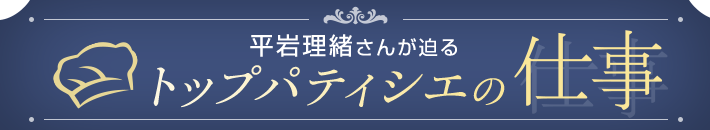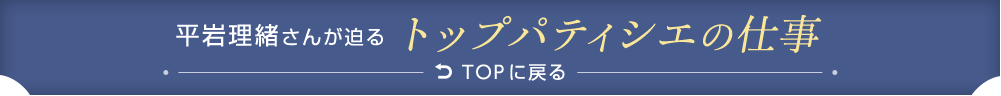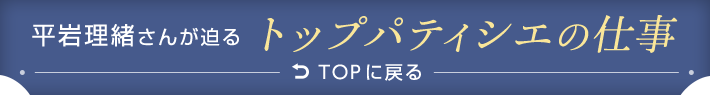看板商品の誕生の由来
- 平岩
- ここで、少しお店の商品についてもお伺いしたいと思います。「ゴンドラ」の代表作と言えば「パウンドケーキ」ですね。このお菓子は、どのように生まれて看板商品となったのですか?
- 細内
- パウンドケーキ自体は、創業当時から作っていましたが、当初は、一般的な直方体のパウンド型を使っていました。
私が一緒にやるようになった昭和30年代に、父の思いつきで丸缶形にしました。当時、日本でもクリスマスケーキが人気となって、スポンジ生地を焼くための丸缶の型をたくさん入手したので、クリスマスだけで使うのはもったいないと、パウンドケーキにも使うようになったのです。
- 平岩
- 私も大好きなお菓子です。販売も缶入りで、今、缶入りクッキーなんかは流行っていますが、缶入りのパウンドケーキというのは現在でも珍しいと思います。ギフトにもぴったりですよね!ご自宅向けに、日持ち短めで、缶入りでないバージョンも販売されているのですね。
- 細内
- 中身だけ欲しい、と仰るご近所の方もいらっしゃったからね。そういう方には密閉容器に入れて下さいと伝えています。缶に入れているのは風味を逃さないためということもあるんです。日本には四季があって、いつも同じ気温や湿度でないから、お菓子には「18℃以下で保存してください」と書いてある。そうすると、夏は冷蔵庫に入れることになるけれど、缶に入れることで冷蔵庫の匂いからも守ってくれる。美味しさを保つための工夫なんですよ。マドレーヌもうちの看板商品です。フランス・ロレーヌ地方のコメルシーの伝統的なマドレーヌは、貝殻の形をしていますよね。戦後の日本では、昭和20年代後半から、神田にあった「エスワイル」のマドレーヌが評判になっていて、これはアルミカップの型で焼いていました。
うちは戦争で型が焼けてしまったこともあり、薄い丸の型を新たに作り、紙ケースも作ってそれで焼くことにしました。
紙ケースにしたことで、型からはがす時に生地が無駄になってしまうということもなくなった。これも工夫のひとつですね。


- 平岩
- 「エスワイル」は、横浜の「ホテルニューグランド」初代総料理長を務めたスイス人、サリー・ワイル氏に師事した大谷長吉氏によるお店ですね。後に「帝国ホテル」シェフパティシエとなられる加藤信先生が、こちらで修業されていました。
「マドレーヌ」は今もお店の人気商品ですね!裏側に「Madeleine」という文字と「ゴンドラ マドレーヌ」という文字が印刷されていて、焼き面ではなく、印刷面を見せてディスプレイされているのですね。フチにちょっとフリルのついた可愛らしい形です。
- 細内
- フリルは貝殻のイメージ。うちは、配合は本場と変えずに、混ぜ方などを変えることで、いかに日本人好みの、口どけのいいお菓子にするかということを追求しています。ほらこのミキサーを見てごらんなさい。うちは針金の太さなんかも変えて、ふんわり軽い生地になるように工夫しています。
ヨーロッパと日本は気候風土も違い、日本は湿気も多いから、喉越しがよく口どけのいいお菓子が求められるんですよ。うちのマドレーヌは、実は、「フランス菓子」とは思っておらず、「欧風銘菓」と謳っています。フランスって、ヨーロッパの歴史の中で見ると、実はお菓子については後進国なんだよ。スペインやイタリア、オーストリアなんかの方が、より早く菓子の文化が進んでいた。だからうちは「フランス」にはこだわっていないの。店のロゴも、イタリアのゴンドラをイメージしてデザインしたものですよ。
- 平岩
- そうだったのですね。仰るとおり、このマドレーヌは、本当にふんわりしっとりですよね。配合はマドレーヌの基本に忠実で、アーモンドパウダーなども加えていないし、ともするとパサパサしがちなところ、すっと口どけていきます。
細内シェフの世代の方は、加藤信先生もそうですが、まずスイスで学ばれた方が多いですよね。お店には、スイスの伝統菓子「エンガディナーヌッストルテ」などもありますし。フランスだけでなくヨーロッパの他の国もご覧になっていらした方ならではの見方かもしれませんね。

値上げや働き方改革を見据え、これからの菓子店に必要なこと
- 平岩
- お店の製造スタッフの方は、何人いらっしゃるのですか?長く勤めている方も多いのでしょうか?
- 細内
- 製造は10人います。そうですね。10年以上勤めている人も多いですよ。うちの店を経てフランスに行ったりもしていますね。
自分はこの建物の6階に住んでますが、毎朝5時に起きて厨房に入ります。昔は若手ほど早く出社したものだけど、今は逆に、オーナーはやっても若い方にはやらせないよね。
- 平岩
- 82歳となられた今も、バリバリの現役で厨房に入っていらっしゃるというのは、まさに生涯職人という生き方ですね。
週40時間と言われる労働時間の法規問題がありますから、今はオーナーシェフ以外、朝早くから夜遅くまで働くということはなくなっていますね。もちろん、そのよさもありますが、限られた時間で、先人の方々ほどの技術を身に付けられるのだろうかという懸念もあります。販売の方も正社員ですか?
- 細内
- うちは製造も販売も担当し、全員正社員です。職人も必ず店から経験を積まないと駄目ですね。「菓子産業」ならそういうのが無くてもいいかもしれませんが、町の菓子店というのは、代々、利用してくださるようなお得意様もいらっしゃいます。お客様のご希望をどこまで聞き入れられるか?というのを見極め、努力しなくてはならない。お客様とじかに接することが大切です。
- 平岩
- 最近、菓子業界でも、原材料の価格をはじめ、電気代や送料など、様々なものが値上がりして、皆さん、商品価格の値上げをせざるを得ないという状況になっていますが、どのように対応されていますか?
- 細内
- 物の値段が上がったら、必要な値上げはします。でも、粉やバターの値段が上がったとしても、他とのバランスというのはあって、たとえば卵の価格は下がったり。そんなに大騒ぎする必要はないんです。私達が使っている材料の多くは、「生き物」でしょう。来年はまた、同じものではない訳です。だからうちは、粉もクリームも「どこ産」とか気にする必要はないと思っています。
値上げしたとしても、理解してもらえるようなものを作って、商売をしていかないと。うちがそれを出来るのは、昭和40年頃から営業方針を切り替えて「卸売り」をしていないからというのもあります。流通経費を取られるということが無いですし、自分が好きなものを作っていけるんです。
- 平岩
- そうですね。日本の菓子店は、もともと、ヨーロッパに比べて価格が安すぎるという傾向もありました。 これからの菓子店は、値上げをしても受け入れていただけるような品を作ることや、そういう売り方をするというのが 必要になりますよね。 さらにこの先、細内シェフがやっていきたいと思っていらっしゃることは何ですか?
- 細内
- 来年で90周年なので、100周年は自分の手で迎えたいと思いますね。うちの息子、滋之(しげゆき)は、大学には行きましたが、そこで改めて考え、また私の仕事をする姿を見て店を継ぎたいと言ってくれました。
日本では、お店を続けていくという事は、とても大変なこと。お菓子づくりだけでなく、経営や法律についてもきちんと勉強していないと。ぼけっとしていたら、店だって無くなってしまう。でも、工夫してやっていかなくてはならないからね。
昔の人間は苦労しているから、何があってもやっていけますよ。
- 平岩
- 今日は、色々なお話をお聞かせくださいまして、どうもありがとうございました。これまでのインタビューともまた違った、グローバルな視野をお持ちの細内シェフならではの貴重なお話をお伺いすることが出来て、大変勉強になりました。こういったお話、若い世代の方々にも伝えていかなくてはならないな、と改めて思います。学びが多かったです!

細内進シェフ プロフィール
1939年、東京都生まれ。 老舗「ゴンドラ」の2代目として生まれる。1961年、21歳で渡欧。アジア人として初めて、「スイス国立リッチモンド製パン製菓専門学校」で学び、日本人として初めてパリの名店「ルノートル」で修業。「全日本洋菓子工業会」副理事を務め、業界の発展に尽くしてきた。1996年に「現代の名工」を受賞。1890年には先代の善次郎氏も受賞しており、食品業界では珍しい親子2代での受賞となった。現在も3代目の滋之氏と共に、朝から厨房に立つ。

※店舗情報及び商品価格は取材時点(2022年05月)のものです。最新の店舗情報は、別途店舗のHP等でご確認ください。