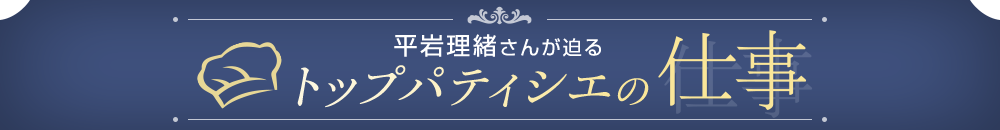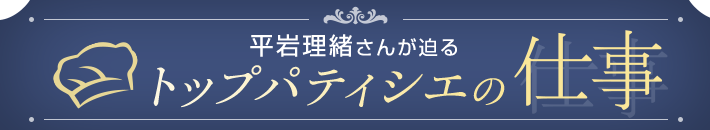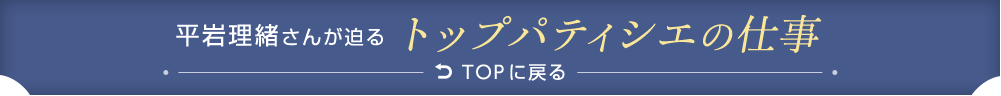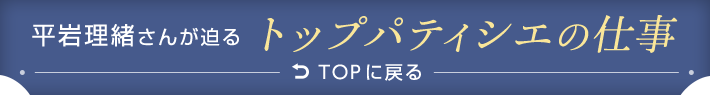菓子職人の方々へのインタビュー連載。今回は、2013年の開業以来、都内・関西圏に続々と出店されてきた「パティスリーアンドカフェ デリーモ」の江口和明シェフをお訪ねしました。様々なチョコレート商品と共に、カフェやサロン店舗で提供するパフェも大人気!2020年に始めたYouTube動画配信は、お菓子づくりのコツ指導が評判で、チャンネル登録者数は2023年3月現在18万人超え。従来の枠に縛られない経営方針や、この先の目標、今後の製菓業界への思いを伺いました。
- 平岩
- 江口シェフ、こんにちは。昨年の春、2022年1月に「大丸東京店」4階にオープンした一番新しいお店、「デリーモ東京カフェ」にお伺いさせていただきましたが、お会いするのはそれ以来ですね。先日、京都出張の際に、ジェイアール京都伊勢丹の「イートパラダイス」内にある「パティスリー&カフェデリーモ 京都店」に寄らせていただきました。
今は、東京都内と関西とを合わせて、全部で何店舗ですか?
- 江口
- こんにちは。現在、都内と京都・大阪・神戸に合計7店舗です。2013年に赤坂で開業し、今年の12月17日で10周年になります。
- 平岩
- 商業施設内へのご出店が多いですよね。新型コロナ禍中は、休業せざるを得ない期間もあったかと思います。最近の状況はいかがですか?
- 江口
- 施設側の方針で休業しなくてはならない、でも家賃は発生するといった状況もありました。赤字です。
京都店を例にあげると、コロナ禍前が10割のお客様だったとして、それが1にまで減り、最近、やっと4くらいまで戻ってきたという感じです。関西の商業施設内の店舗でも、やっと、イベントをやってもOKかなという雰囲気になりました。


- 平岩
- 大変な時期を乗り越えていらした秘策はあったのでしょうか? コロナ禍中にイートイン席を撤去された菓子店も多いですが、「デリーモ」はイートイン併設の店舗が多いですよね。効率の点でどうなのでしょうか?
- 江口
- コロナ禍中は、物販の製品原価を上げていく方針を取っていました。そして私は、「お菓子屋さんはカフェをやった方がいい」派なんです。
- 平岩
- 昨今は、出来るだけ原価を抑えようとするお店が多いように思いますが、むしろ逆だったのですね?
そして、イートインをやると人件費がかかり、面積あたりの売上で考えると坪効率が悪くなると考える方が多いように思うのですが・・それも逆と? ぜひ、詳しく教えてください。
- 江口
- 物販というのは、面積が決まっていて、その分しか商品を置けないものなんです。そのため、別の場所で製造していたとしても、店舗の坪効率をどんどん上げられるという訳ではありません。
カフェ営業については、メニューを運ぶ人と下げる人とのバランスが大切で、スムーズに回転させ、効率を上げることが必要です。
この「東京ミッドタウン日比谷店」などは、パフェが売れているとよく言われますが、実は売り上げの3割強は物販です。「デリーモららぽーと豊洲店」は物販のみの店舗で、利益率は高いのですが、利益額そのもので言えばカフェありの店舗の方が高いです。
- 平岩
- 物販だけだと、店舗の面積に応じて売上の上限があり、カフェ併設の方が、売上金額を上げる余地が大きいということですね?
ただ、最近は人手不足で、カフェ営業に手が回らないというお店もあるようですが・・。
- 江口
- 「人を集めるのは大変だよね?」とよく言われます。たとえば、5人でやっていたとしたら、1人でも辞めると影響が大きいですよね。でも、スタッフが多ければ1人欠けても回すことが出来るでしょう。私は、製造スタッフが4-5人といった規模の店だと、今後さらに10年続けられるかどうか自信が無いです、自信が無いからこそ、基本人員を増やす選択をしました。
- 平岩
- 確かに、近年は、そのくらいの人数規模で開業されるお店が増えているかもしれません。
なるほど。続々と店舗展開をしている「デリーモ」を見て、江口シェフはすごい!と思われている方も多いと思いますが、トータルでのスタッフの人数が多い方が、融通が利くという考え方なのですね。
- 江口
- 若いスタッフ達は、ある程度、多店舗展開しているような有名な店で働きたいという希望を持っていることも多いです。
- 平岩
- お客様に対してだけではなく、就職希望者に対するブランディングにもなっているのですね。

商品開発の考え方
- 平岩
- 今はどのお店も、「効率化・働き方改革」を進めようとしていると思いますが、「デリーモ」のパフェやお菓子の開発方法や、品揃えについての考えも教えていただけますか?
- 江口
- たとえば、生地の種類自体は少なく、厚みを変えるなどして使い分けています。一方、パフェのパーツなども全て自家製で、既製品を使うことはしていません。アイスクリームも、バニラをベースに、フルーツのコンフィを混ぜることで10種類程のバリエーションを作り出しています。
また、レシピを数値化することで、誰でも容易に計算することが出来るようにし、コミュニケーションコストを徹底して減らすことも目指しています。

- 平岩
- 労働時間の短縮を目指すと、「半製品を仕入れて使う」という選択肢がよく取り上げられますが、そこは敢えて手作りで、視点を変えた効率化を進めていらっしゃるのですね。以前、講習会でお伺いしたお話では、レシピも、数式の入ったエクセル管理で統一してあり、必要な量の数量を変えたら、他の数値も全て自動計算されるようになっているのでしたよね?
「コミュニケーションコスト」という概念は、従来、この業界であまり一般的ではなかったように思いますが、「情報伝達や意思疎通のためにかかる時間や労力」ということですよね。特に、菓子店のように複数名が分業で取り組む仕事においては、コミュニケーションコストを減らすための工夫も大切ですね。
- 江口
- 生菓子の数は、最初の開業店舗には20種類あったものを、15種類に減らし、今は8-10種程にしました。
昔は、朝一番に、ショーケースに色々な生菓子が並んでいることが素晴らしいと思っていたのですが、むしろ、必要な時間帯に揃っていることの方が重要だと気づきました。
- 平岩
- 確かに、特に商業施設内の店舗が多い「デリーモ」各店では、朝、その日に持っていく手土産を買わなくてはならない、といった需要はあるかもしれませんが、その時間から生菓子を豊富に揃えておく必要はないかもしれませんね。
- 江口
- かつては、目線が「パティシエ」を見ていたんです。憧れのシェフ達がいて、自分もあのようになりたい!と思いながら、いつの間にか品数が増えていきました。でも、今、品数を絞っても売上はむしろ上がっています。
- 平岩
- 今、日本でもフランスでも同じく、人手が足りないという話をよく聞きます。決められた労働時間内で製造するには、品数を絞らなくてはならない。その結果、職人としての技術を習得する機会が減って、人を育てるのが難しいという問題があると思いますが、どのように考えていらっしゃいますか?
- 江口
- たとえば、うちの店にはカスタードクリームを使うお菓子がほとんどありませんが、これはやめずにずっと炊いていて、色々な製法を試したりしています。スタッフ達に自由にやらせたら、よりいい物が出来たということもありました。
グラサージュも同じように自家製で炊いていて、常に、より美味しいものを作ろうとしています。
- 平岩
- 今は、カスタードも全自動の機械で炊けますし、仕上げの艶がけ素材も様々な機能性を備えた既製品がありますが、そういったものを導入する、というのではないのですね。菓子職人として続けていきたい、次世代に伝えていきたい仕事というのは、人によっても違うと思いますが、何を優先するかの見極めが必要になっていますね。
- 江口
- カスタードを使ったお菓子の話ですが、シュークリームなどは、値段の高い商品とは見てもらえない、高級感を感じてもらえない品なんです。だから、うちがシュークリームをやるのは、イベント時に、注文を受けてからカスタードクリームを絞る、詰めたて販売をするような時だけです。今は、コンビニのシュークリームだって美味しくなっていますから、専門店がやるという特別感が必要です。
うちの焼き菓子の中で人気の「フィナンシェブロンドキャラメル」も、普通のフィナシェならコンビニでも売っています。コンビニは『フィナンシェ』というお菓子の認知を広めてくれているのであえて同じ商品を作らずより付加価値の高いものを作る方が共存できる道が開ける気がします。

- 平岩
- 私もこの数年、「専門店が、コンビニや大手チェーンのスイーツに対抗するにはどうしたらいいか?」というテーマで質問をいただくことがとても多いのですが、「彼らが市場の裾野を広げてくれているので、専門店が出す、より価値の高いものも理解されやすくなった」と解釈し、前向きに捉えていくことは大切ですね。
- 江口
- 「パフェ」にしても、今、お取り寄せできる「冷凍パフェ」なども広まっています。でもそれが、うちがやっているような、店に来ないと食べられないパフェを引き立ててくれると考えています。自分達は「モノ」だけを販売している訳ではなく、空間やシーンを売っているんです。
今年の1月、「ガレット・デ・ロワ」をイメージし、1杯ごとにフェーヴも付けた「パフェ・デ・ロワ」というのを1日100食程度限定で販売したら、非常に反響があり、この施設の向こうの端まで行列が出来た程でした。「ガレット・デ・ロワ」って、一般の方が1台購入するのは、まだまだハードルが高いと思うんです。業界外の方にも、もっと知ってもらえるようにと思ってやりました。


- 平岩
- 「ガレット・デ・ロワ」をパフェにするとは、斬新なアイディアですね。確かに、若い世代の方にとっては、そのような形からの方が入りやすく、フランスの伝統菓子としての「ガレット・デ・ロワ」を知っていただく最初のきっかけになるかもしれません。

※店舗情報及び商品価格は取材時点(2023年01月)のものです。最新の店舗情報は、別途店舗のHP等でご確認ください。