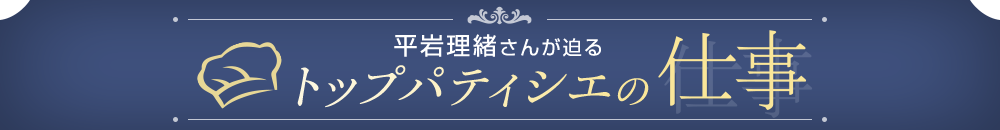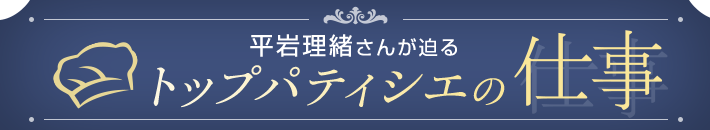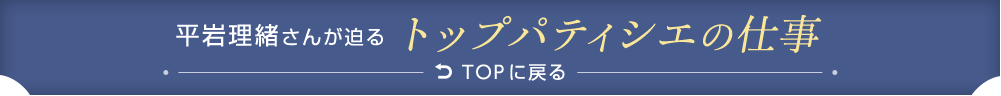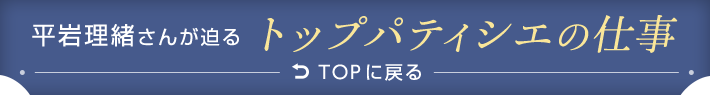菓子職人の方々へのインタビュー連載。今回は、2020年に神奈川県川崎市の鷺沼で「ル・マルディ」を開業された赤塚ユミシェフをお訪ねしました。製造担当はご自身のみ。焼き菓子を中心に揃える、こじんまりとした“ビスキュイトリー”です。製菓学校卒業後に渡仏し、MOFの店でも修業。2000年に鷺沼でオープンした「パティスリー・ドゥ・ムートン・ルージュ」は2014年に閉店しましたが、その後、この町で再度スタートを切った経緯や、日々の働き方、目指すことなどをお話しいただきました。
- 平岩
- 赤塚シェフ、こんにちは。オープン時間の11時にお伺いしましたが、開店をお待ちのお客様がいらっしゃいましたね。今日は、お忙しいところありがとうございます。お1人で作っていらっしゃるのに、相変わらず焼き菓子の種類が豊富ですね!
- 赤塚
- こんにちは。朝から全てが揃う訳ではなく、途中で追加出ししていくものもあります。
販売手伝いのスタッフは1人いますが、製造は1人なので、今日は厨房でお話させていただきますね。
- 平岩
- 今は、木・金・土・日の週4日、営業されているのですよね。最近は、週休2日はもう当たり前で、特に人数が少ないところは、週3-4日だけ営業、というパターンのお店も増えてきました。ただ、完全にお休みされているという訳ではなく、定休日のうち2日くらいは仕込みの日、といった場合が多いですね。
最初にオープンされたパティスリー「ムートン・ルージュ」は、パティシエールを志す女性のスタッフの方々が、ここで働きたいと集まり、一緒に働いていらっしゃいましたね。
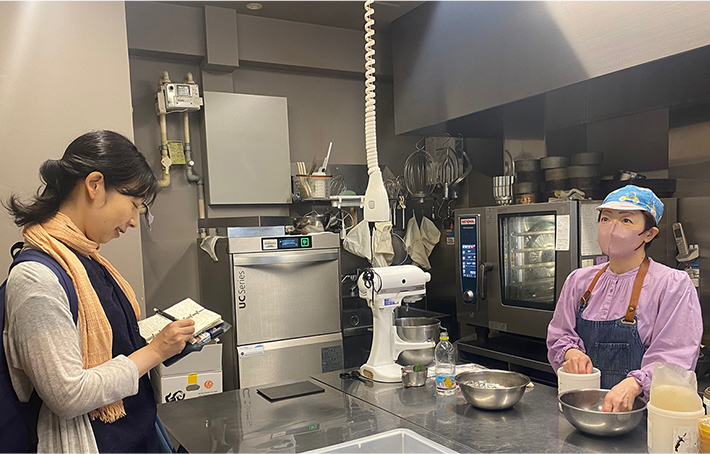

- 赤塚
- 最近、当時、働いていた子達が独立開業などをして活躍しています。新潟のご実家の菓子店に戻った子もいますし、うちの後に板橋区の「ラ・ノブティック」で働いていた子が独立して「ロゼ・ドゥ・マタン」という店を都内の清瀬市にオープンしました。「ムートン・ルージュ」を一緒に立ち上げて、約15年ずっと共にやってくれた子は、一度は専業主婦になった後、現在は宇都宮で「kotohogi(ことほぎ)」というデコレーションケーキ専門店を始めています。中には、ソムリエ―ルになった子もいます。8月には「ムートン・ルージュ」の同窓会をする予定なんですよ。
- 平岩
- それは楽しみですね!そんな「ムートン・ルージュ」とはまた異なる、この「ル・マルディ」ですが、なぜ、別のブランドでオープンすることになさったのですか?
- 赤塚
- 大人数のチームワークでやっていた現場も楽しかったのですが・・「ムートン・ルージュ」は、多い時には9人で作っており、今度は、自分1人で作る店をやろうと思ったんです。
実は、「ムートン・ルージュ」を閉店した後、山梨県に行く予定で、次の物件も決まっていたんです。でも、色々とあってその話は無くなりました。
ただ、「ムートン・ルージュ」の跡地は、居抜きで次の方にお譲りして別のパティスリーになっていたので、同じ町で菓子店をやるのもどうかと・・。しばらくは、お菓子教室などもやっていました。
でも、鷺沼という町には子供達もたくさんいて、保育園なども増えているのに比べると、そこまで菓子店が増えていないように思います。ママ友同士でちょっとした時に贈るギフトみたいなものがもっとあったらいいのになと思い、このお店を始めることにしました。今後、ネット販売も始めようと思って、準備しているんですよ。
- 平岩
- そうだったのですね。焼き菓子のネット販売も始められたら、なかなかお店までは足を運べない方々からも喜ばれると思います!
- 赤塚
- たとえば、店舗の定休日の中で、「週1度、火曜だけ発送」みたいな形でもいいのかなと思っています。

- 平岩
- 実際、ネット販売をなさっているお店の中で、そういう所も少なくありません。あらかじめそのように謳っておけば、理解してくださるお客様が注文してくださいますね。無理のない範囲で、続けられる形を確立していくことが必要だと思います。
- 赤塚
- 今の店は、パートさんと自分だけでやりたいと思い、人を増やす気はないんです。外販をするつもりもなく、直接の注文を受けて、店からの宅配の発送のみとしたいです。
- 平岩
- 今は、百貨店のオンラインショップや、有名店のお菓子をセレクトして販売しているショッピングモールなど、出店先も色々とありますからね。新たなお客様に興味を持っていただけるといったメリットはありますが、製造可能な量との兼ね合いもあります。
最近は、オンライン販売限定というお店も増え、そういうところはSNSの運用にも力を入れていることが多いですね。
「ル・マルディ」のInstagramは、赤塚シェフが投稿されているのですか?
- 赤塚
- はい。朝、キッチンに入る前に投稿するようにしています。仕事を始めてしまうと、なかなか手が空かないので・・。
- 平岩
- 朝はどのくらいから仕事を始めていらっしゃるのですか?
- 赤塚
- 午前11時オープンに向けて、朝5時半からキッチンに入っています。
- 平岩
- 早いですね!ご自身だけで製造されているお店だから出来ることかも・・。今、労働時間への配慮もあって、スタッフの方々の出勤時間を、そこまで早くはしていないお店が増えたと思います。
菓子職人の方々は、70代を過ぎても朝からバリバリ働いていらっしゃるという方も多く、そのパワフルさに驚かされるのですが、赤塚シェフも、本当にお菓子作りがお好きでいらっしゃるのですね。
いつ頃から、どのような経緯で、この仕事に就きたいと思われたのですか?
- 赤塚
- 小学校の時からお菓子屋さんになると決めていたんですよ。なので、高校生の頃から「東京製菓学校」の見学に行って、体験入学にも参加したりしていました。
- 平岩
- 私も「東京製菓学校」卒業生なので、先輩でいらっしゃいます!私の在学時代は、クラスも女子の学生が多かったですが、赤塚シェフがいらした頃は、まだ女性は少なかったのではないでしょうか?
- 赤塚
- そうですね。学校のクラスの7割は男子学生で、それも、お菓子屋さんの跡継ぎという方が多かったです。
学生時代からお菓子屋さんでアルバイトをしていて、さらにディズニーランドでもアルバイトをしていました。
最初の頃に働いた職場の中には、月2回しか休みがないし、朝6時から夜21時くらいまで仕事で、それでも月給が6万円程といったところもありました。まかないは出ましたけれど。
私は実家がお菓子屋さんという訳ではないので、父からは「そんな職場はおかしい!」と言われて。でも、その頃から独立したいと思っていましたし、学生時代に貯金はしていたこともあって、頑張っていました。ただ、結局その後、両親が店に来て頭を下げて、何とか辞めさせてもらったんですが・・。
- 平岩
- 今の時代だったら、大問題になりますね・・。でも、当時、修業されていた世代の方々からは、そういう感じだったというお話もよく伺います。

- 赤塚
- 将来、独立するならば個人店の菓子店で働きたいというイメージはありましたが、学校にも、女子を対象とした求人票が1枚も無かった。男性と女性とでは給料も全然違っていましたし、女性は、すぐには焼き場に入れてもらえないといったこともありました。
その後、世田谷の個人店で働けることになり、そちらのシェフが現在の「パティスリー・ドゥ・シェフ・フジウ」の藤生義治シェフと親しく、そこから繋がりが出来て、夏休みには、藤生シェフが当時シェフパティシエを務めていらした立川の「エミリーフローゲ」で研修もさせていただきました。フジウのお店では、周年記念の際にOB・OGの方々が集まっていらっしゃいますが、私もその場に呼んでいただいたりして本当に感謝しています。
- 平岩
- まさに、パティシエールのパイオニアとして、進む道を自ら切り拓いていらしたのですね。今でこそ、パティシエールの方々がいないと菓子業界が成り立たないほど、女性の菓子職人が製造現場で活躍していますが、赤塚シェフのような先輩方が、道筋をつけてくださってきたからこそだと思います。
- 赤塚
- その頃は、身近にフランス人の方もあまりいなかったですが、当時、恵比寿にあった「東京都洋菓子協会」で、ジャック・ベランジェさんというMOFショコラティエの方を招聘して講習会があり、田園調布「レピドール」の寒川正史シェフや、高円寺「トリアノン」の安西松夫シェフ、大田区荏原町「コルディアル」(現在は閉店)の小針由雄シェフなどが助手に入っていらっしゃいました。その洗い物と計量係に立候補して、寒川さんには、それ以来、ずっと可愛がっていただき、とても感謝しています。
フランスでは、ベランジェさんのお店のあるロワール地方のLe Mans(ル・マン)にも行きましたよ。
- 平岩
- やはり、パワフルで行動的ですね!フランスには、どのような経緯で行かれることになったのですか?
- 赤塚
- 学生時代に、一度、研修旅行で南仏のニースを訪れた時にすっかり魅せられて、ここで働きたいと思うようになりました。
卒業後、ニースにある菓子店を探しては、「働かせてほしい」と何度も手紙を書き続けましたが、どこも駄目でした。それでも諦めきれず、講習会で来日した菓子店の経営者に直談判して、ようやく前向きな返事をいただけたのです。そして、ニース近郊のMOF店「ル・パレ・デュ・シュクル」で働くことになりました。

経営者として人を育てるということ
- 平岩
- 当時は、フランスで働くということも今の感覚からは想像できないほど大変だったと思いますが、女性はなおさらですね。
パティスリーの製造現場で女性が働くことの厳しさに関して、経営者として気遣ってきたこと、業界がもっとこうなったらいいと思われることはありますか?
- 赤塚
- 昔は、小麦粉の袋は25kgで、砂糖は30kgでした。ちなみにフランスでは1袋50kgでしたが。「ムートン・ルージュ」でも、1人で持とうとしないでとスタッフに言っていました。日清製粉さんの「エクリチュール」が出た時、重さ10kgというので、「なんていい!全てのメーカーでそうすればいいのに!」と思いましたよ。
昔の店は、作業台の下にミキサーを置いていたものですが、重いボウルの上げ下げで、腰に負担がかかりますよね。今はうちも、ミキサーを台上に置くようにしましたが、この方が絶対にいいです。
手荒れがひどい子もいて、アトピー症でやめざるを得なかったということもありました。少しでも、洗剤を手にやさしいものにするとか、気を付けていました。
それでも、今から就職する女性の方々というのは、昔に比べるとかなり色々と改善されていると思います。

- 平岩
- 仰るとおりですね。男性の経営者の方々の意識も、大きく変わってきたと思います。
今は、性別に関わらず、若い職人の方々がモチベーションを保って働けるようにと、皆さん、かなり気を遣っていらっしゃいますよね。
- 赤塚
- あるお店のオーナーシェフの方から、「採用面接の際に、本人だけでなく親御さんも一緒にいらしていただき、どういう仕事なのかと初めに説明しておかないと」というお話を聞き、本当にそうだなと思いました。
「ムートン・ルージュ」では、自宅から通ってくるのだと時間もかかるし、疲れているのに長距離通勤をさせるのが心配だし、正直なところ、店の近所で1人暮らしが出来るという子しか面接しなかったですね。アパート探しは一緒にしていました。
- 平岩
- それはあると思います。私の製菓学校時代の同期の子でも、入社したい店が、近くに引っ越してくるというのが採用時の条件で、彼女はそれが難しかったので断念した、ということがありました。
- 赤塚
- 「エミリーフローゲ」で研修していた時は、朝は午前3時始まりでしたが、その分、終わるのは早くて昼前くらいに終わったりしていましたし、皆でご飯を作ったり、一緒に食べたりする「まかない」の文化がよかったですね。
今の子達は、コンビニで買ってきたカップ麺とかでご飯にしてしまったりする・・あれでは具合が悪くなってしまうと心配です。私なんかは「一食入魂」がモットーで、食事はとても大事にしてきましたから。
- 平岩
- 以前はまかないを交替制で出していたというお店も、勤務時間の短縮を迫られたり、そもそも人手不足だったりして、今やっているお店は稀少ですね。あるお店では、以前はまとめてお弁当を注文していたけれど、残すスタッフが多く、食べ物を捨てるのが我慢できないのでやめた、とシェフから伺ったこともありました。
若い世代の方々が、食べ物に対する敬意や感謝の思いを実感できるようにしていくということも、この業界の課題の1つですよね。
- 赤塚
- 「ムートン・ルージュ」の頃、夏休みにお子様向けのお菓子教室をやっていましたが、その時は、実際に厨房に入ってもらって、作ってもらうということをしていました。
- 平岩
- 「食育」ですね。お子さん達にとって貴重な経験ですね!菓子店がそういう場を提供できるというのは、意義のあることだと思います。
- 赤塚
- スタッフ達とは、年に1回、お洒落してきちんとしたレストランに食事に行くということをしていました。そういう場でも堂々として振る舞えるようにと。そしてデザートを食べて、何が入っているのかと皆で話し合ったり。体験することで、パティスリーのテイクアウトのケーキとの違いも感じられます。
それから、2年に1度はフランスに行くと決めていて、費用の半分くらいはこちらで補助して、残りはボーナスを充てていました。観光地とかでなく、小さな村とかに行くんですよね。コルシカ島なんかにも行ったなぁ。
- 平岩
- それは素晴らしいですね・・!そういうイベントも楽しみに、皆さん、張り合いのある働き方をされていたのでしょうね。
今は色々と難しくて、オーナーシェフがよかれと思って研修旅行などを企画しても、「それ行かないといけないんですか」「手当は出るんですか」と聞かれたりするという話も聞きます。でも、給料の対象になる、会社の業務の一環という形でも連れていくと、それがきっかけで変わる子もいるとか。人を育てるというのは本当に難しいですね。
「ムートン・ルージュ」さんは、女性のスタッフの方のみでしたか?
- 赤塚
- 女子しか採用しないと決めていた訳ではないのですが、結果的にそうなっていましたね。皆、仲がよかったですが、ダラダラしないけじめがありましたよ。社内で「絞り」の試験を実施したりもしましたし。
後半の方は、「にいがた製菓・調理専門学校えぷろん」の学生さんも、クリスマスの研修を経て、そのまま就職してくれたりしました。地方から上京してくる子というのは、それだけ心が決まっていて、しっかり続けてくれましたね。20人ほどOGがいるうち、「えぷろん」卒業生の子が7-8人いますよ。
- 平岩
- 社内試験までなさっていたとは、懇切丁寧ですね。 「ムートン・ルージュ」メンバーの絆の強さには、やはりそれだけの理由があるのですね。

※店舗情報及び商品価格は取材時点(2023年07月)のものです。最新の店舗情報は、別途店舗のHP等でご確認ください。