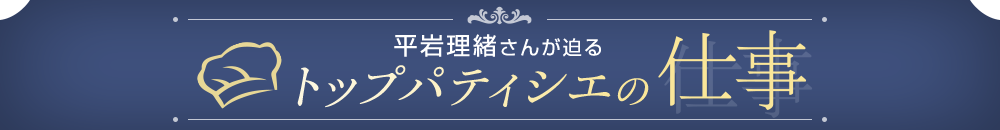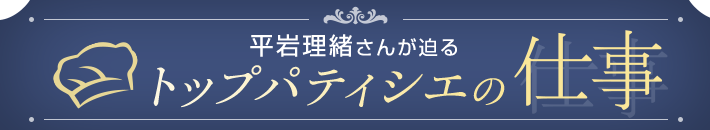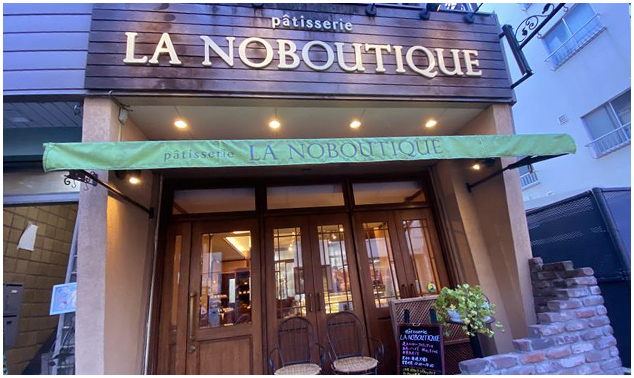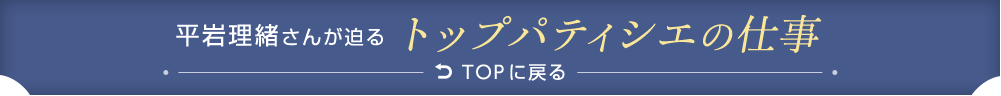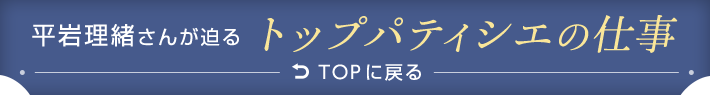誰もやっていないことをやる意味
- 平岩
- ところで、日髙シェフは、2013年に『低糖質 つくり方のコツ』というレシピ本も出版されました。当時、「低糖質スイーツ」というのが社会的に話題になり始めてはいたものの、フランス菓子をずっとやっていらしたパティシエの方々にとっては、“自分達の学んできた菓子とは別世界のもの”というイメージだったと思います。体系的に研究した方もあまりいらっしゃらず、日髙シェフがあの本を出されたことで、参考にすることが出来たというパティシエの方々の声を、何度も耳にしました。
基本的には、1個あたり糖質量を5gに抑えたお菓子を、1日2個まで食べていいよ、という考え方ですよね。
- 日髙
- 「糖質制限食」の第一人者である、糖尿病専門医の先生にもお会いして、自分も色々と勉強しました。その先生の夢が、全国のお菓子屋さんの片隅にでも、低糖質のお菓子があって、誰でも気軽に買えるようになるということだったので、低糖質のお菓子の作り手が1人でも増えたらいいなと、そのお手伝いができればと思いました。
- 平岩
- 大山シェフから、他の人がやっていないことをやるということを学ばれたと仰っていましたが、日髙シェフにとって、低糖質スイーツもその1つなのですね。
- 日髙
- コーヒーの焙煎もそうですね。自家焙煎までやっているパティスリーというのはあまり無いでしょう。
パティシエは焼くことに関してはプロなので、焙煎と通じ合う部分があります。焙煎士は、コーヒーの声が聞こえるそうですが、自分も、お菓子の声は聞こえるかな。「ちょっと温度が熱いよ・・」とか「まだ出すには早いんじゃない?」とか。
最近は、何℃で何分焼く、とマニュアル化しないとスタッフ達に伝わらないと言われたりしますが、季節や気温、そのお菓子を焼く前にオーブンで焼いていた物によってとか、変化するものなんですよね。それは体感していくしかないことなんです。



スタッフの能力をどう生かすか
- 平岩
- 今、パティスリーのスタッフの方は何人いらっしゃいますか?
- 日髙
- 社員が5人で、販売が1人、製造4人。それからアルバイトが販売2人、製造が2人。そのうち1人は、長年お菓子の製造補助をやってきたという方で、週に数回、入ってもらっています。
- 平岩
- それは頼もしいですね。菓子店に限ったことではありませんが、ご出産や育児のためにいったん正社員を離れた女性の方がパートタイムで勤務するなど、可能な時間帯だけでも経験者の方に入っていただくと助かるという話は、よく伺います。
- 日髙
- 一度、リタイアされた方の力も、もっと生かしていくべき時代になっていますね。そういった方々を受け入れるような環境づくりもしなくてはなりません。菓子店に勤務されていた方はもちろん、社会人経験のある方は人間としても大人で、お店にとってもありがたい存在です。何となく話も合う、というか、あちらが自分に合わせてくれます(笑)。
最近は、外国人の方が研修されたいということもありますよ。中国でお医者さんをされていて、パティシエになりたいと、製菓専門学校に入学されたという方などもいらっしゃいました。
- 平岩
- 少し前に『GATEAUX』誌(日本洋菓子協会連合会刊)でも特集されているのを拝見しましたが、海外の研修生の方を受け入れているお店のお話も聞きますね。お互いにとってメリットとなるよう、関係を築いていけるといいですね。

時代に合った原材料の検討
- 平岩
- お店で使っていらっしゃる原材料についても、お伺いさせてください。
まず小麦粉ですが、低糖質のスイーツも作っていらっしゃるので、通常の小麦粉だけでなく、糖質量の少ない粉もお使いですよね。
- 日髙
- 今は、薄力粉2種を、ジェノワーズとフールセックで使い分けていて、強力粉1種、それに低糖質のふすま粉を使っています。本当は、もう少し色々と使い分けしたいという気持ちはあるのですが、管理も大変になるので。
「エクリチュール」は使ってみたいと思っていました。10kg袋があるのもいいですね。25kgは重すぎるので。

- 平岩
- 女性が持つには25kgは重たいですし、少量で仕込む小規模なお店も、以前より多くなっていますものね。
ここ最近の問屋さんの展示会などでは、カカオの価格上昇でチョコレートの値段が上がるのにどう対応するかなど、原材料コストをいかに抑えるかといった提案が多いですね。円安の影響も鑑みて、国産素材のメーカーさんが商品開発や営業に力を入れている傾向も見られます。
- 日髙
- 最近は、国産のチョコレートなんかも品質が上がっているので、海外産のものから変える人も出てくるでしょうね。
ある乳業メーカーさんが、植物性油脂のクリームだけを使うのではなく、配合に少し混ぜて使うと、コストダウンも出来るし、扱いやすくなると説明しているのを聞いて、なるほどと思いました。質を下げられるのは困る。いい物はそのまま残してほしい。そこに一部ブレンドするならば味もそれほど変わらずにすむ、というならば、検討する余地はあるでしょうね。自分も、変えることで味に影響すると言うならば、やはり絶対に使わないですから。
実際に、100%乳脂肪分の生クリームは、ナッペするのが難しく、若い職人達には扱いづらいでしょうしね。

若い世代に求めることとは
- 平岩
- 昨今の「働き方改革」で、職人の技術が失われていくということが懸念されていますが、いかが思われますか?
やりたい仕事と違う、自分には合わないと、早々に辞めていく若い人が多いことも、この業界の大きな課題です。
- 日髙
- とにかく、続けてほしい、目標を持ってやってほしいと思います。
お菓子って、無くてもいいけれど、お店に入ってお菓子を見るとニコッと笑顔になる、そういうものを作っていることを誇りにしてほしいと思います。
そのうえで、続けていかなくては、成功はあり得ないんですよね。1つのことをやって出来ない人は、同じことを繰り返します。努力に勝ることはありません。いや、努力を努力と思わず自然にできるよう、夢中になれることにしてほしいです。
- 平岩
- 2020年4月に東京・三鷹にお店をオープンされ、東京都洋菓子協会の公認技術指導委員にもなられている「パティスリーエススドウ」の須藤サチシェフは、こちらのお店のご出身なのですよね。
- 日髙
- 彼女は、「明治記念館」の頃から共に働いていて、当時から、自店を開業するという目的意識がはっきりしていました。
お子さんが生まれてから独立開業していますからね。これからはそういう女性がどんどん増えていって欲しいと思います。
うちで働いた後に、独立開業したり、地元に帰って実家の洋菓子店を継いだりしたスタッフが何人かいますが、皆、女性ですね。
目的が決まらないと、そのために何をしていったらいいのかというプロセスが定まらないですから、うちの採用面接でも、将来どうなりたいのかを聞くようにしています。
- 平岩
- 最近は、女性のオーナーシェフも増えてきましたし、これからもさらに増えていくでしょう。こちらご出身の女性のご活躍や、日髙シェフがそれをどのように見守っていらっしゃるかということも、菓子業界にとって、有用な参考例になると思います。
日髙シェフも大山シェフと同じく、こうしなさいと言葉で仰る訳ではなくとも、ご自身が新たな挑戦や研究を続けることで、自然と語りかけ、伝えていらっしゃるのでしょうね。
今日は、色々なお話をどうもありがとうございました。

日髙宣博シェフ プロフィール
1961年、宮崎県生まれ。
東京・麻布「キャンティ」、成城「マルメゾン」など、数々の名店で修業。1987年に渡欧し、帰国後、神奈川のパティスリー「ラ・マーレ・ド・茶屋」製菓長に就任。国内外の製菓コンクールで受賞を果たす。1994年、明治記念館 製菓長に就任し、統括職を歴任する。2010年10月、板橋区のときわ台駅前に「パティスリー・ラ・ノブティック」を開店。「社団法人 日本洋菓子協会連合会」の公認技術指導員を定年まで務め、後進の育成にも力を尽くす。

※店舗情報及び商品価格は取材時点(2024年05月)のものです。最新の店舗情報は、別途店舗のHP等でご確認ください。