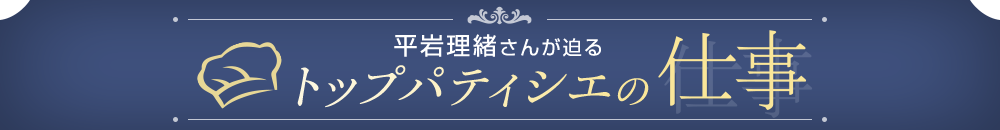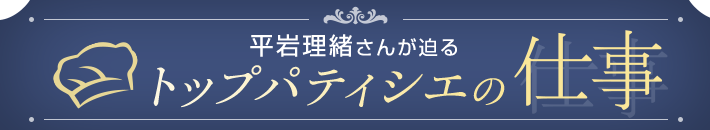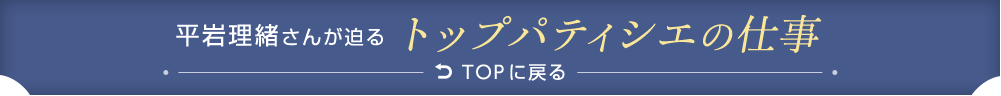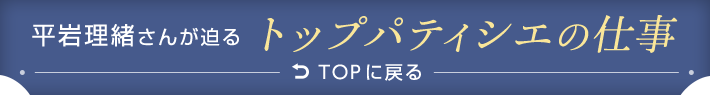旬の素材を大切に、価値を伝えていく
- 平岩
- 食に関する情報の氾濫という意味では、メディアの発信のやり方に問題が見られる場合もありますね。私も常々、勉強しなくてはと思っています。
- 中川
- 生クリームもチョコレートも、日本ほど多種多様に揃う国は無いですよね。うちは、「生クリーム」と言ったら純生クリームのみ、「バタークリームのお菓子」と謳っていたらバターしか使いません。コンパウンドクリームを使うお菓子もありますよ。でも、それはきちんと説明して理解してもらう必要があります。
- 平岩
- 日本の材料メーカーさんは本当に研究熱心で、様々な商品を開発されていますからね。
- 中川
- 生クリームが嫌い、と思っていた方に、「この店のものは食べられる」と言われることもあります。これから先、大手メーカーや流通のプライベートブランド菓子がどんどん増えていく中で、素材を選ぶことで棲み分けすることも必要ですね。
- 平岩
- 素材のお話が出たので、小麦粉についてもお伺いいたします。パンも、ヴィエノワズリーだけでなくパンドゥミなどもあって、選択肢が多いですね。小麦粉も何種類か使い分けていらっしゃるのですか?


- 中川
- パンやフィユタージュには、「リスドオル」を使っています。食感が特徴的で好みですね。粉は、色々と試行錯誤しています。日本の製粉会社の小麦粉は安定感がありますよ。日本で10年間経験してからフランスへ行って、粉の違いは大いに感じました。
でも、小麦自体も変化してきていて、10年前の物とは違っているように感じます。春と秋とでも水分量が違いいますし、自然のものですから、本来、変わってくるのが当然なんですね。
- 平岩
- ショーケースの上にも、お菓子に使われている旬のフルーツを飾っていらっしゃいましたが、そういった素材の季節感というのも大事にされているのですね。
- 中川
- 今はりんごや洋梨を置いていますね。栗も、茨城県の岩間から送られる生栗をコンポートにして、タルトに使ったりしていますよ。東京都洋菓子協会の仕事で地方出張に行くことも多く、各地の農家さんとの繋がりが広がっていきました。昔は、料理人的な感覚で素材を選ぶパティシエというのはあまりいなかったですが、最近は若い方でも、自分で素材を見に行って、農家から直接送ってもらうという人が増えてきましたよね。「アカシエ」の興野君なんかもそうだよね。
- 平岩
- 練馬区の地元の素材を使ったものというのもありますか?
- 中川
- キッシュに使っているジャガイモは、今年、うちの畑で収穫したものですよ。もうすぐサツマイモも収穫になります。あと、夏のチョコミントのお菓子なんかに使うミントも自家栽培品です。卵の殻とか、余った卵白なんかを有機肥料として、無農薬で育てています。
- 平岩
- なんと、あのキッシュはそうだったのですね。ぜひ、帰りに買って帰ります!
- 中川
- 苺も、ジャム用にする分なんかは自分の畑で作っていて、店のスタッフと一緒に収穫します。せっかく練馬という場所でやるのだからね。最近はすっかり畑で日焼けしてますね。

今後の菓子業界のあり方とは? さらに未来に向けて
- 平岩
- 2020年は様々なことが異例の1年となりましたが、今回のクリスマスはどのようになさる予定ですか? 個人店のお菓子屋さんのピークは、12月24日(木)・25日(金)の平日2日間に集中しそうですね。
- 中川
- 店内は現在と同じく、お客様5人までの入場制限にしますので、以前からそうしていましたが、予約は事前支払い制として、クリスマス当日には店内に入らなくても店の外で商品だけ受け取れるようにしたいと思います。うちは7月から袋も有料化していますので、手提げ袋も含めた価格設定にします。
- 平岩
- 今年は、並ぶことなくスムーズに持ち帰れることを重視して、予約しておこうというお客様が増えるかもしれませんね。
アントルメだけでなく、プティガトーも販売されるのですか?
- 中川
- クリスマスも、10種類程の売れ筋商品に絞って、プティガトーは販売します。お客様の立場になって考えた時、やっぱり、色々ある中から自分で選ぶ楽しさというのはあると思うので。


- 平岩
- クリスマスをどのような体制にするか、まだ悩んでいらっしゃる若手のオーナーシェフ達も多いようです。Withコロナ時代に迎える初めてのクリスマスですが、正解がある訳ではなく、お店によっても状況が異なるので、それぞれ試行錯誤する冬になりそうですね。
中川シェフは、「東京都洋菓子協会」や「クラブ・ドゥ・ラ・ガレット・デ・ロワ」に所属していらっしゃるので、幅広い世代のパティシエの方々と情報交換をなさる機会も多いですね。
- 中川
- そうですね。そういう場で、職人とはどういうものか、といったお話を伺う機会も多いです。「パティスリー・ドゥ・シェフ・フジウ」の藤生義治シェフや、「パティスリー タダシヤナギ」の柳正司シェフなど、素晴らしい方々ですよね。色々と学ばせていただいています。若い方々にそういう話をすることも大切ですよね。交流を通じて、お互いに刺激になる間柄であったらいいなと思います。
- 平岩
- 藤生シェフにも、柳シェフにも、以前にこのインタビューをさせていただき、含蓄あるお話をしていただきました。仰るとおり、世代を超えた交流の場は大事ですね。
この先、5年後、10年後を考えられた際、中川シェフは、どのような方向に進んでいきたいと思われますか?
- 中川
- お菓子の種類はどんどん増えていって、実は番号が重複しているものもあるんですが、通し番号は100番を超えています。ローカーボ(低糖質)のチョコレートタルトなんかもあるんですよ。今も、伝統菓子を今風にアレンジするなど、新作を考えるのは楽しいです。それがシェフならではの楽しみですし、作り手が楽しんでいないと、スタッフにも、お客様にも伝わると思うんですね。
私は来年60歳になりますが、何といっても、藤生シェフがお手本なんです。73歳になられた今もバリバリに現役でやっていらして、凄いですよね。自分も、その背中を追って、職人であり続けていきたいと思います。今よりもっと美味しいお菓子を追いかけ続けたいですね。
- 平岩
- ここから巣立って独立していくOB・OGの方も増えていくでしょうし、楽しみですね。今回の新型コロナも大きな転機となって、パティシエの生き方は、今後より多様になっていく気がしています。その中でも、生涯、職人としてお菓子づくりを続けていくことが出来たら素晴らしいですね。今日は、色々なお話をどうもありがとうございました。

中川二郎シェフ プロフィール
1961年、和歌山県生まれ。菓子店に生まれ自然と菓子職人を志すようになり、東京製菓学校で学ぶ。「東京カド」、「スヰング」勤務を経て、1990年に母校に教員として入社。1992年、渡仏してパリの製菓学校「ベルエ・コンセイユ」で学んだ後、「ジェラール・ミュロ」「ピエール・モデュイ」などで1年間修業。帰国後も東京製菓学校で約10年間、学生の指導に当たり、2003年5月に自店「パティスリー キャロリーヌ」をオープン。東京都洋菓子協会の理事・技術指導部委員も務める。

※店舗情報及び商品価格は取材時点(2020年9月)のものです。最新の店舗情報は、別途店舗のHP等でご確認ください。