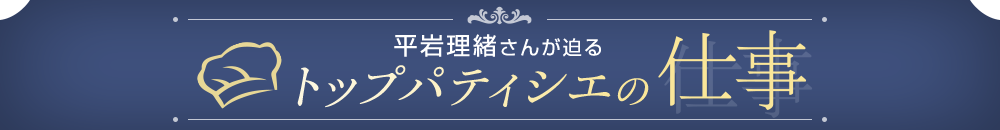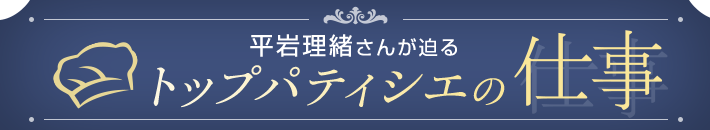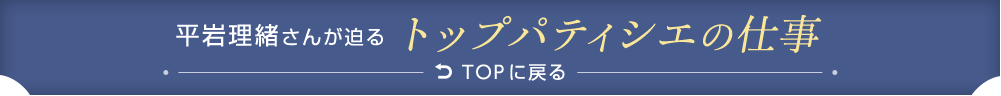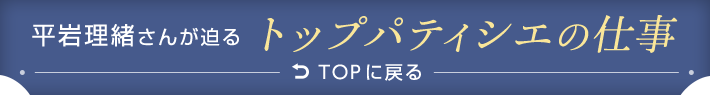菓子職人の方々へのインタビュー連載。今回は、日本を代表するフランス菓子店「パティシエ・シマ」の2代目、島田徹シェフをお訪ねしました。お父様の進シェフは、日本初のフランス菓子専門店「A.ルコント」を経て渡仏し、帰国後は日本にフランス菓子を広めてきた方。フランス共和国農事功労章オフィシエ、令和5年春には旭日小綬章を受章されるなど、そのご功績は国内外で知られています。そんなご家庭で生まれ育ち、ご自身も製菓の道に進まれ、オーナーシェフを引き継がれた現在までの経緯や、今後の展望などをお話しいただきました。
- 平岩
- 徹シェフ、こんにちは。今日はお忙しいところありがとうございます。今日は、「ラトリエ・ド・シマ」の方でお話をお伺いします。なんと、スペシャリテのガレット・デ・ロワまで出していただきまして・・ありがたくいただきます!
徹シェフは、SNSに投稿されているお菓子の画像も、ご自身のスマホで撮影されているのですよね?皆でガレット・デ・ロワをいただくこの写真、Instagramのストーリーズに上げられるんですか?
- 島田
- こんにちは。どうぞ、召し上がってください。はい、撮りますよー(笑)。iPhone も機種をProにすると絶対に写真が綺麗に撮れるって、「ブーランジェリー スドウ」の須藤秀男シェフに勧められて、そうしてるんですよね。
- 平岩
- お菓子の撮影も自撮りもお上手です。そういうところも、“次世代のパティシエ”ですよね。
先ほど、パティスリーの前で撮影した際、シェフにお声掛けされていた方は、ご近所の常連のお客様でしょうか?


- 島田
- あの方は、九段にあるご近所の小学校の生徒さんのお母様なんです。毎年10月に、3-4年生を対象に「味覚の授業」を担当させていただいていて、それがご縁でお店に来てくださる方も多いです。味覚の授業がフランスの教育プログラムの一環ということもあって、フランス語の授業の1コマとして入れてくださっているそうですよ。「甘・塩・酸・苦」という4つの味覚を体験してもらうために、海塩入りのサブレショコラなどを持っていきます。「エクリチュール」を使ったサブレ・ヴィエノワも持っていっていますよ。毎年、時期になるとガレット・デ・ロワも持っていくんですよ。
パティシエという職業は、フランスの食文化を伝える仕事と考えているため、自分の母校の小学校でも、父と一緒にボランティアで、毎年、「味覚の授業」をやらせてもらっています。

- 平岩
- フランス語の授業のある小学校!しかもガレット・デ・ロワをいただけるとは、グローバルな体験ですね。
まさに、お父様と共に、フランスの食文化を広めるために様々な形でご貢献されていますね。
- 島田
- 今は代表取締役を父から引き継いで、店全体を見るようになり、変化しているところもあります。
たとえば、父は一般的な苺のショートケーキは作っておらず、特注でしか作っていませんでしたが、僕がフランスから戻ってきてから通常アイテムとして店頭に並ぶようになりました。ただ、日本の洋菓子のショートケーキではなくて、1層はクレームディプロマットをサンドして、生地はジェノワーズですがフランボワーズの赤いソースをアンビベした、ちょっとフランス風のものなんですよね。
ただ、お客様のリクエストもあって、去年のクリスマスから、苺のジュレの層を底の方に入れて、ジェノワーズと生クリームだけで構成された「エアリーショートケーキ」というアントルメもやり始めました。僕も父もタカナシ乳業さんの北海道・浜中町で搾乳された生クリームが好きなので、今もタカナシさんの生クリームを使っています。
- 平岩
- あ、ショーケースに「本日のケーキ」という名で並んでいましたね。
- 島田
- 今、全体的なものの値段が上がっている中で、洋菓子を食べる頻度が減り、商品を選ぶ際に目新しさよりも安心感のあるベーシックな味に原点回帰しているように思いますね。

先代から店を継承するということ
- 平岩
- 味の想像がついて、なじみのあるお菓子が求められているということでしょうか。
徹シェフは、フランスから戻られて「パティシエ・シマ」に入られ、進シェフから受け継ぐに至るまで、どのような思いでお菓子を作っていらっしゃいましたか?
- 島田
- 自分が帰国した頃に、雑誌の取材などを受ける機会があると、「お父さんのお菓子はどれで、徹さんのお菓子はどれですか?」とよく聞かれました。父と息子を切り分けて考えようとする方が多いんですが、「パティシエ・シマ」という屋号は1つで、その名前の中でやっているので、そういう感じではないんですよね。
僕はそれを歌舞伎界にたとえるんですが。市川團十郎がそうですね。後継の人が物語の内容を変えることはないし、團十郎は中の人が変わっても同じ團十郎として物語を続けるといった感覚です。
- 平岩
- 以前にこちらのインタビューにもご登場いただきましたが、京都の「洋菓子マウンテン」の水野直巳シェフが、お父様から継承したお店の屋号と別に、「CELLAR DE CHOCOLAT by Naomi Mizuno」というチョコレートのブランドを立ち上げて、ご自身のお菓子のクリエーションを広げていらっしゃるみたいな感じでしょうか。


- 島田
- そうですね。僕も、父にとってもベースである「A.ルコント」で修業時代の最初を過ごしているので、実は違いがあまり無かったりもします。特に告知もしていませんが、昔からあるお菓子でも、レシピを変えているものもありますし。
ガレット・デ・ロワも、今は父のレシピではなく、どちらかというと真逆の配合に変えたんですよ。うちは中身がクレーム・フランジパーヌなんですが、父の配合は、卵が最大限界値まで入ったクレームダマンドでしたが、今は、よりアーモンドの濃厚な風味がある配合にしています。
- 平岩
- え!そうでしたか。実は先日、日経新聞の試食審査で、ブランド名は伏せてガレット・デ・ロワを食べ比べる機会があり、「パティシエ・シマ」もきっと出ているはずと思っていましたが、自分が何度かいただいた「パティシエ・シマ」のガレット・デ・ロワの記憶と一致するものがどうも見つからない気がして、判別できませんでした。
今も食べさせていただいて、あれ?パイ生地が軽くなったような?という気がしましたが、側面にシクテ(周りの縁取り)が無くなりましたよね。その分、抑えられていないので、浮きも感じられます。
- 島田
- そうですね。パイ生地も軽くしています。お菓子は、食べるシチュエーションによって変えていきたいと思っていて、自分の味の軸がぶれなければいいと考えているんです。
お客様も、昔は、お酒でヒタヒタにしたのがいいと仰られる方もいましたが、今のファミリー層のお客様はお酒NGですよね。どうするべきか悩ましいですが、今の自分だったらどっちがいいのか?と考える。うちの店には、最近の世の中全般のように、軽さを求める風潮とは違う、濃い味わいが欲しい方もいらっしゃいますからね。それでも、「ケーク・オ・フリュイ」なども、昔と比べるとアルコール量を減らしました。
- 平岩
- 「A.ルコント」から継承する、フルーツいっぱいのパウンドケーキは、「パティシエ・シマ」の看板商品の1つですね。
- 島田
- 老舗には味の歴史があって、過去に縛られることなく、ゆるやかな変化というのはつきものなんですね。一方で、ブランドを変えて別に大きくやる、というのもあり得ます。
- 平岩
- 「不二家」さんなども、100年以上の歴史を持つ定番のショートケーキも、生クリームの甘さを徐々に減らしてきたと言いますし、「変わらない味」と言われるようなロングセラー品でも、実は、目に見えないところで変えているんですよね。

フランス菓子の歴史やレシピの意味を伝えていく
- 平岩
- 今、お店のスタッフの方は何人いらっしゃいますか?
- 島田
- スタッフが11人、そのうち2人は販売担当で、あとはうちの家族です。
自分が入るより前に、実は色々な方が働いていらっしゃって、もと「パリ・セヴェイユ」のスーシェフ、今は横浜市に「バスキュール」をオープンした佐藤徹シェフなども、うちの店の出身ですね。
- 平岩
- 徹シェフは、幼少期からフランス菓子に囲まれて過ごされていた訳ですから、やはり、フランスの食文化への興味というのが、自然と身についていらしたのでしょうね。
- 島田
- そうですね。「A.ルコント」って、父がフランスから帰ってきてルコントさんの右腕を務めるようになって、お菓子が変わったんですよ。父は、帰国後に銀座の「マキシム・ド・パリ」のシェフパティシエになりましたが、伊勢丹新宿店にルコントの店舗がオープンすることになって、帰ってくるようにとルコントさんから言われ、総製菓長として戻りました。
父がフランスにいた当時は、「ジャン=ミエ」に急速冷凍庫が入って、シャルロット・ポワールとかムースのお菓子とかが出始めた頃でした。それって、ルコントさんからすると“ヌーヴェル(新しい)”なお菓子だったんですよね。因みに、サンマルクなんかも“伝統菓子”みたいに言われますが、「ジャン=ミエ」のスペシャリテだったので、比較的新しいお菓子なんだよね。

- 平岩
- フランス菓子について、“古典菓子”“伝統菓子”といった言い方が気軽に使われがちですが、ならば、1950年代に誕生したという「ダロワイヨ」の「オペラ」は伝統菓子と言えるのか?といった話もありますよね。
- 島田
- エルメさんの「イスパハン」ぐらいシンボリックで、その後も続いていくお菓子になると、いずれは“伝統菓子”と呼ばれるものになるのかもしれない・・。あとは、それを引き継ぐ作り手が、その菓子にゆかりがあるかどうか、ということも問われますね。
- 平岩
- 確かに「イスパハン」は、エルメさんが1986年よりシェフパティシエを務めたフォション時代に考案したお菓子ですが、もう30年程経っています。あと20年、あるいは50年先には、多くの人に共有される“伝統菓子”になり得るのでしょうかね・・?でも、ピエール・エルメ・パリで働いていた方が作っていると、なるほどオマージュなのだなと感じますが、そうでないと、フランボワーズとライチとローズって、「イスパハン」の真似じゃない?と思ってしまうところがあります。
- 島田
- 自分は「ぼくのスウリー」というお菓子を作りましたが、あれは「スウリー」が元々「A.ルコント」のお菓子だから、という意味でそう名付けました。
他にも、「ぼくの生チョコ」とか「ぼくのパイ」といった「ぼく」シリーズがあります(笑)。

- 平岩
- 「スウリー」は、白いネズミの姿が可愛らしいシュー菓子ですね。ルコントご出身の方々が何人か、継承されています。
「ぼくのスウリー」はいただきましたが、シリーズ化していたとは知りませんでした。 それにしても、徹シェフの世代で、このように日本のフランス菓子界の歴史を長い目で見て俯瞰できる方って、なかなかいらっしゃらないように思います。
- 島田
- 自分は、日本のフランス菓子の創成期を見聞きしながら育ってきていますからね。それが自分のアイデンティティであり、アドバンテージでもあると思っています。教えてもらった身として、自分も下の世代に伝えていきたいですね。
次の新しいものを考えるためには、フランス菓子のレシピも、どうしてそうなったかがわからないと、アレンジも出来ないんです。たとえば、フランスのレシピだと、小麦粉が「Farine」と「Type55」とで表記してある。でも、「Type55」みたいな粉が手に入らなかった時代に、足して2で割ったようなつもりで中力粉を使えばいい、というような解釈が生まれてしまったりもした。中力粉って、日本で昔からうどんとかを作るために栽培されてきた品種の小麦粉で、薄力・強力粉の中間という訳ではなく、全く性質が違うんですよね。「エクラ・デ・ジュール」の中山洋平君なんかは、作り比べた結果、中力粉がいい!と言って使っていたりしますが(笑)。
日清製粉さんの「リスドオル」も、バゲットを作るために開発された粉でしょう?
- 平岩
- 「リスドオル」は、1969年に、本場フランスの風味を追求したフランスパンを作るための専用粉として誕生したそうです。
日本における小麦粉の普及・開発の歴史を紐解いても、フランス菓子やパン文化をどのように追求してきたかが伝わってきますね。
そういう古い時代のことを知る方がだんだん少なくなる中で、語り継ぐことや、そもそもの経緯を学ぶことの重要性を、改めて感じます。

※店舗情報及び商品価格は取材時点(2023年11月)のものです。最新の店舗情報は、別途店舗のHP等でご確認ください。