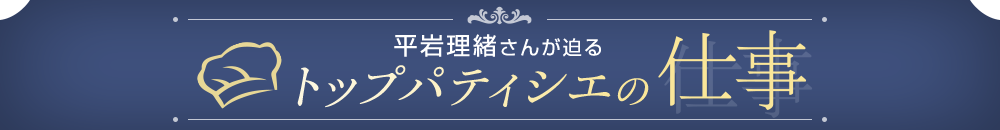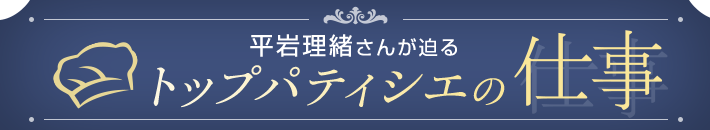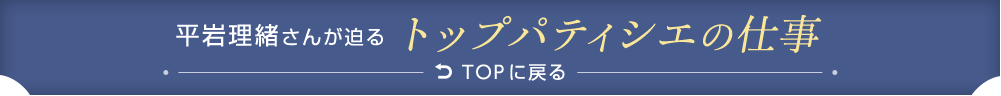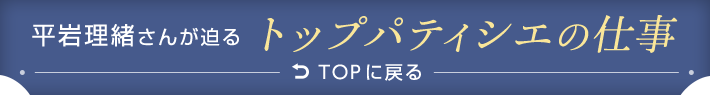世代間ギャップを埋めるもの、これからの展望
- 平岩
- 徹シェフが今後、作っていきたいお菓子や、目標についてお聞かせください。
- 島田
- 毎年開催されている「ジャパンケーキショー」で、指導委員によるレシピ集の『Sweets Collection』が発刊されますよね。
帰国して店に入って間もない頃、この冊子に載せていただいた1品が、父の菓子だと思われていたことがありました。 でもその時、「しめしめ」と思ったんですよね(笑)。
- 平岩
- 「徹シェフのお菓子」としてではなく、「パティシエ・シマのお菓子」として認識されたというのが、してやったり、という感じだったのですね。
「パティシエ・シマ」の名前でやっていく上では、ご自分の代になったから自分のカラーを強めるといったことでもなく、お客様から、「いつものシマのお菓子ね」と思ってもらえるようなお菓子を作っていきたい、ということでしょうか。
- 島田
- はい。「レザネフォール」の菊地賢一君も、フランス菓子をずっとやってきたけれど、師匠の「アルパジョン」の棟田純一シェフから中野の店舗を譲られて、あそこで店をやるようになってから、お菓子や意識が変わってきたと話していました。
- 平岩
- 地域に根差した洋菓子店、という感じのお店でしたから、お客様の希望に応えて、棟田シェフのお菓子を引き継いだものもあったそうですし、“フランス菓子”という肩書きにこだわらないようになったんでしょうね。
進シェフは1946年のお生まれですが、今のお菓子業界は、既に、その世代の方々より一回り若い世代の方々がトップに立って引っ張っていらっしゃいます。徹シェフ達のような40代の方々が、今も「若手」と言われていますものね。
とは言え、オーナーシェフになられて、より若いスタッフの方々と接する際に、世代間ギャップを感じられることもありますか?



- 島田
- 父が初代会長を務めた「クラブ・ドゥ・ラ・ガレット・デ・ロワ」の3代目会長をなさっている「ノリエット」永井紀之シェフとも一回り以上違いますが、「若手」と言われても、世間的にはそれほど若くないんですよね・・(笑)。
でも、今の20代のスタッフ達とも、育ってきた環境がかなり違うので、色々なギャップを感じることがありますよ。
その世代の人達は、学校で怒られる機会も減ったのだと思いますし、時代の変化が早すぎて、長いスパンで物事を考えるのが苦手な子が多いなと思いますね。目標を小さく区切って、細かいフェーズで達成感を得られるようにしてあげないと、続けさせるのが難しい。
- 平岩
- これまでのインタビューでも、「今の若者は打たれ弱い」とか「叱られると泣いてしまう」といった話を伺うことが、度々ありました。
- 島田
- 「そんなんじゃオーナーシェフになれないよ」と言っても伝わらないんです。「とりあえずカフェができればいい」くらいに思っている人が割と多くて、独立志向が弱くなりました。
ただそれを、「昔と熱量が違う」と言って断じてしまってはそこまでなので、「何かやりたいことがあるんじゃない?」と話してみたりするのですが。
「中途半端にやめてしまったらもったいないよ」と言いたくなることもしばしばですが、今の若者はゲームとか携帯電話の影響もあるのかもしれませんが、“リセット慣れ”してるんですよね。転職者が多いのもそのためかなと思います。
パティシエの仕事は技術職なので、積み上げる時間が必要なんですよね。
「続けた先にある技術をもっと信じてほしい」と、これは永井シェフが仰っていた言葉なんですが、本当にそう思います。
- 平岩
- 昔は、長年の地道な修業を乗り越えて、初めて一人前の職人として独立するというストーリーが一般的でした。でも今は、どこかのお店で数年修業したら、すぐに通販専門で開業するというような小さなお店も増えましたね。
- 島田
- もちろん、そういったお店もあっていいと思いますが、平岩さん達のようなジャーナリストの方々が、どのような視点で取り上げるかも大事ですね。
- 平岩
- 製造数が少ないためになかなか買えないといった品を、メディアが入手困難ともてはやすような傾向も見られます。
最近、自店のキャパシティを超えて製造した結果、品質管理が出来ておらず、危うく食中毒事故に繋がるような
菓子がイベントで販売され、ニュースで取り上げられました。
今後、製菓の仕事を志す若い方々には、単なる製法やレシピだけでなく、様々なことを幅広く学んでほしいですね。

- 島田
- 製菓学校に教えに行ったりすると、学生さんから、「フランスに行く必要はありますか?」と聞かれるんですよね。
それに対して言うのが、「外国でカリフォルニアロール寿司を作っている職人さんに、日本に行ったことがある、働いたことがあると言われたらどうかな?親近感、信頼感を持てるんじゃない?」って。職業として「パティシエ」とフランス語で名乗るからには、フランスに行って働いたということが、心の拠り所になるんじゃないかなと話しているんです。
- 平岩
- わぁ、それはとてもわかりやすく噛み砕いたたとえですね。
もっと上の世代のシェフから、「行った方がいいですか?なんて人に聞くくらいなら行かない方がいい」というお言葉を伺ったことがあります。私もどちらかと言うとそう思う性質なんですが、徹シェフのように説明すると、今の若い方達にも伝わるのでしょうね。
- 島田
- 自分自身が、そうやってフランスに行って色々な人達と出会って、充実した価値のある5年間を過ごしましたからね。 フランスで実際に見て知ったこともありましたよ。「レモンケーキ」を開発した時に、試してみてこれがいいと思い起泡剤を使ったところ、周りから色々言われましたが、使用したものと不使用のものをブラインドで食べ比べても違和感はなかったし、フランスの某有名パティシエも、ジェノワーズに起泡剤を使っていたんだけれど・・と思ったり(笑)。
- 平岩
- 広島県産のレモンを絞って使っていらっしゃる、人気のレモンケーキですね。あれは昭和にブームを呼んだお菓子ですが、「フランス菓子」のカテゴリーではないので、徹シェフだからこそ発売できた品だなぁと思っていました。

- 島田
- 今はお客様も色々な情報に詳しくなっていらして、「このお菓子に使っているのは国産小麦ですか?」と聞かれたりします。
僕は、材料についても教えてもらえるシチュエーションに恵まれています。講習会をさせていただいて、デモ用にサンプルをいただくことも多いので、色々試したりもできますね。それを講習会でも教えられる。今って、ただ作り方を説明するというのじゃなくて、材料の知識とかも学べる講習会の方が求められているでしょう?
- 平岩
- そうですね。徹シェフは、フランスで学んだ同年代のパティシエの方々や、菓子店の2代目の方達と共に、「セルクル・デ・シェフ」という活動も始められて、勉強会や講習会を続けていらっしゃいますよね。
- 島田
- 日本では、小麦粉や乳製品については特に、深掘りして勉強しなくてはいけないと思っています。他の原料は世界中どこでも同じ品質で使えるけれど、小麦粉と乳製品は日本独自の原料で使わなくてはいけないので、フランスのレシピも調整が必要なんです。フランスのレシピそのままでは出来ない、日本独自の素材で作らなくてはならないんですよね。
「小麦粉を制する者はフランス菓子を制する」ってどうですか?日清製粉さんにもぴったりの言葉でしょう?
- 平岩
- それはきっと喜ばれますね(笑)。
今回は、このインタビューの履歴を振り返っても、これまでにない視点からのお話をお伺いすることが出来ました。
徹シェフ、貴重なお話をどうもありがとうございました。

島田徹シェフ プロフィール
1976年東京都生まれ。
大学で経営情報学を学んだ後、2000年日本で最初のフランス菓子専門店「A.ルコント」入社。フランス菓子の基本を徹底的に学ぶ。
2004年渡仏。パリ13区にあるMOF「ローランデュシエーヌパリ」に勤務。
2005年パティスリー界のピカソと呼ばれる「ピエールエルメ」のパリ本店へ。ここでの3年半さまざまなポストを経験し、パティスリーの奥深さ、芸術性、価値を学び、そしてピエールエルメの才能やカリスマ性に大きく影響を受けパティシエとしての感性が研ぎ澄まされ、アイデンティティが築かれる。

2008年フランスで最上位格付けホテル「ル・ブリストル」へ。バンケット、レストランデセールの仕事から型にとらわれない自由な発想と洗練された装飾方法を知る。
その他5年間の在仏中「エコール・ヴァローナ」(ショコラ)、「アトリエ・ステファンクライン」(飴細工)、「エコール・オリビエバジャール」(氷菓)など数々の一流機関で研修を受ける。
2009年帰国後、東京麹町「パティシエ・シマ」シェフ就任
2010年フランス料理団体「トックブランシュ国際倶楽部」、「レザミドキュルノンスキー」、「フランスチーズ鑑評騎士の会」に入会を認められる。
2016年公益社団法人東京都洋菓子協会公認技術指導委員に任命される。
2022年フランスに本部を持つ世界最古のシェフの会「フランス料理アカデミー」に入会を認められ正会員となる。
パティシエはフランス文化の伝道師という考えから、「味覚の授業」をはじめ積極的にフランス食文化に関わる活動を行っている。またテレビ出演、製菓飲食業界向けイベント・展示会でのデモンストレーション、プロ向けの技術講習会(日本だけでなく北京や台湾など海外でも行っている)、原料メーカーとの商品開発協力や技術アドバイス、スイーツコンテスト審査員など、活動は多岐にわたる。
趣味では、日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート資格を有し、ワインへの造詣も深く、シャンパーニュ文化を愛するサーブルドール騎士団シュバリエサブラーでもある。
※店舗情報及び商品価格は取材時点(2023年11月)のものです。最新の店舗情報は、別途店舗のHP等でご確認ください。